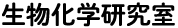化学感覚分野で、数多くの研究成果を挙げています。
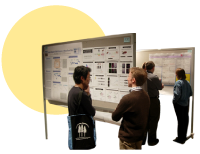
東原グループでは、発足1999年以降嗅覚研究を進めています。
その研究成果を論文や総説など様々なかたちで発表していますので紹介します。
主要な研究成果の概要
-
これ以降の論文は業績欄の「詳しい解説はこちら」をごらんください -
鼻がない植物が匂いを感知する「匂い受容体候補」を発見(J. Biol. Chem. 2019) -
匂いの価値や質が決まるしくみを受容体レベルで解明 ―求める香りをデザイン可能に―(Nature Communications 2019) -
仔マウスのシグナルを受け取ると雌マウスは雄の求愛を拒否する―幼少フェロモンESP22の脳神経受容機構を解明―(Nature Communications 2018)交尾抑制フェロモンESP22のなかで高い活性を有する合成可能なペプチド断片を特定(Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2019) -
嗅覚受容体遺伝子の比較が明らかにした霊長類嗅覚系の退化の要因 —目・鼻の形態変化、果実食から葉食への食性の変化—(Mol. Biol. Evol. 2018) -
マウスは ラットの性シグナルを天敵情報として認識して 身をすくめる(Current Biology 2018) -
マウスの流産を引き起こすブルース効果の一端を解明~半世紀以上も謎であった原因物質の一つを特定~(Current Biology 2017) -
マウスの性行動を促進させる脳神経回路を決定ー交尾相手と天敵を嗅ぎ分ける専用回路ー(Neuron 2017) -
ヒト乳幼児の匂いが親の養育行動に寄与する-子のの匂いに関する調査-(PLoS ONE 2016) -
ムスクの香りを感知する受容体の応答特異性と進化—たった一つの受容体がムスク香の感知に影響を及ぼす—(J. Neurosci. 2016) -
オスらしさを高めるフェロモンをマウスで発見—フェロモンに新しい概念—(Current Biology 2016) -
産業的に有用でミントの香りを呈するメントールの鏡像体を識別する嗅覚受容体の発見(Biosci. Biotechnol. Biochem. 2015) -
アミノ酸共進化理論に基づいた昆虫嗅覚受容体の立体構造モデル構築と機能ドメインの発見(Nature Communications 2015) -
Gタンパク質共役型受容体キナーゼ3は嗅覚受容体の脱感作にあまり関わっていない可能性を示唆(Chemical Senses 2014) -
アフリカゾウはイヌの2倍、ヒトの5倍もの嗅覚受容体遺伝子を持つ(Genome Research 2014) -
ムスクの香りを感知する受容体と脳領域の決定(Neuron 2014) -
オスマウスの性行動を抑制する幼少フェロモンを発見(Nature 2013) -
カイコ性フェロモン受容体の活性が環状ヌクレオチドで細胞外から制御されるという意外な事実を発見 (PLoS ONE 2013) -
マウスの性行動を制御するペプチド性フェロモンの立体構造と受容体相互作用機構を解明 (J. Biol. Chem. 2013) -
メスマウスを誘うオスの尿臭として新規不飽和脂肪族アルコールの発見 (Nature Chem. Biol. 2013) -
昆虫における匂いやフェロモンの受容体シグナル伝達メカニズムをめぐる論争に決着 (PLoS ONE 2012) -
昆虫における果糖の味覚センサーを発見 ー新規の受容体チャネル・腸にも発現ー (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011) -
世界最大級の花ショクダイオオコンニャクが放つ特異臭気成分を特定 (Biosci. Biotechnol. Biochem. 2010) -
鼻粘液中での酵素反応が匂いの感覚に影響を与えることを発見 (J. Neurosci. 2010) -
オスマウスの涙に分泌するESP1はメスの交尾受け入れ行動を増長させるペプチド性フェロモンである (Nature 2010) -
匂いをクンクンと嗅ぐ(スニッフィングする)ときの脳応答への影響を解析 (J. Neurosci. 2009) -
皮膚に浸潤し潰瘍を形成する癌患部が発する悪臭物質のひとつを特定 (Biosci. Biotechnol. Biochem. 2009) -
桑の葉から放出されるカイコを誘引する香りとそれを感知する受容体センサーを発見 (Current Biology 2009) -
嗅覚受容体のより効率の良いアッセイ系の確立 (Chem. Senses 2009) -
嗅覚受容体のGタンパク質共役部位の同定と活性型受容体への構造変化に関わる部位の発見 (J. Neurochem. 2008) -
昆虫の嗅覚受容体(匂い、フェロモン)はヘテロ複合体でリガンド作動性イオンチャネルだった (Nature 2008) -
外分泌ESPペプチドファミリーは性・系統で差があり鋤鼻神経のリガンドとなる (Current Biology 2007) -
嗅覚受容体からの匂い信号を嗅覚一次中枢の嗅球において可視化 (Neuron 2006) -
精子細胞には複数の嗅覚受容体遺伝子が発現 (Genes to Cells 2006) -
マウスのオス特異的な性フェロモンは涙にでていた!しかも新規ペプチド! (Nature 2005) -
嗅覚受容体の匂い結合部位の同定:匂いセンサー機能の構造的知見 (J. Neurosci. 2005) -
昆虫における匂いや性フェロモンの受容メカニズムの全貌解明 (Science 2005) -
カイコガ性フェロモン受容体の発見 (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004) -
マウス精子に発現する嗅覚受容体の機能を解明 (J. Cell Sci. 2004) -
嗅覚受容体の糖鎖の重要性とGタンパク質共役に関わる部位同定 (J. Neurochem. 2004) -
嗅覚受容体アンタゴニズムを発見 (EMBO J. 2004; Chem. Senses 2004) -
嗅上皮の前額断生切片で匂い応答を測定するアッセイ系を確立 (NeuroReport 2003) -
嗅覚受容体の匂い応答を測定する様々なアッセイ系を確立 (Biochem. Biophy. Res. Commu. 2003) -
活性化される嗅覚受容体の組み合わせが匂い物質のコードとなることを立証 (J. Neurosci. 2001) -
単一嗅細胞からの匂い受容体の機能的クローニング及び再構成 (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1999)
研究成果詳細説明
-
鼻がない植物が匂いを感知する「匂い受容体候補」を発見 要点:
1. 植物は鼻がないのに匂い物質を感じることができるという事実は1980年代から報告されていますが、そのメカニズムは不明でした。タバコをモデル植物として用いて匂い感知機構を調べた結果、匂い物質と結合して遺伝子発現制御に関わる転写制御因子を特定しました。
2. 植物においては、動物がもつ嗅覚受容体とは異なり、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している可能性を初めて示唆します。
3. 本研究成果を応用することで、香りを利用して食害に強い植物の作製が可能になることが期待されます。
成果の概要:
自然環境下において、昆虫に食べられた植物の周辺に生育している植物は、昆虫に食べられにくくなることが報告されています。近年、食害を受けた植物から放出される「匂い物質」によって、周囲の健康な植物にこのような変化が引き起こされていることが明らかになってきました。しかし、鼻や神経系のある動物とは異なり、植物がどのようにして匂い物質の情報を受け取っているのかは長らく明らかになっていませんでした。本研究ではまず、タバコ由来の培養細胞を用いて、植物から放散されることが知られているさまざまな匂い物質が、抵抗性遺伝子の発現を活性化するか検討しました。その結果、アロマオイルなどに含まれるß-カリオフィレンとこれに似た構造の匂い物質が、特異的に、ある抵抗性遺伝子の発現を誘導することを見つけました。さらに、タバコ植物体においても、ß-カリオフィレンはこの遺伝子の発現を活性化することがわかりました。これらの結果は、植物が匂い物質の構造を感知していることを強く示唆します。そこで、ß-カリオフィレンの分子構造を認識する「匂い受容体」を探索することとしました。その結果、TOPLESSという転写制御因子が、ß-カリオフィレンを「鍵と鍵穴」のように認識するタンパク質であることが明らかになりました。実際に、TOPLESS タンパク質を多く持つ組み替えタバコ培養細胞と組み替えタバコ植物体を作出して、ß-カリオフィレンに対する応答を解析したところ、TOPLESSは抵抗性遺伝子の発現制御に関わっていることが示唆されました。本研究の成果は、植物においては、動物がもつ嗅覚受容体とは異なり、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している可能性を初めて示唆します。本研究成果を応用することで、香りを利用して食害や病害に強い植物の作製が可能になることが期待されます。
詳細:
動物は食物や天敵などの匂いを感じ取ると、その匂い由来の情報に対して適切な行動をとります。その際、匂い物質は鼻の奥の嗅上皮に存在する、嗅覚受容体で感知されます。一方、鼻や神経系を持たない植物においても、周囲に生育する植物が食害を受けた際に放出する匂い物質を受容し、その情報に応答することが1980年代から報告されてきました。その後、植物間で伝達される匂い物質の一部が初めて特定されました。例えば、リママメの葉がダニに攻撃された際に放出する匂い物質の合成品を、無傷のリママメに曝露させると、防御応答遺伝子の発現量が上昇することが明らかになりました(Arimura et al., Nature, 2000)。また、同一の匂い物質に曝されても、植物種によって抵抗性が上昇する場合としない場合があることや、匂い物質に曝された時点では抵抗性遺伝子の発現は誘導されず、自身が食害された際の防御応答のスピードが上昇することなどが報告されました。これらの知見の蓄積によって、植物が匂い物質を受容し、受容シグナルが特定の応答を引き起こすことが強く示唆されるようになりました。しかし、植物において匂いがどのように感知されているかは不明であり、匂いの受容体は未だ同定されていませんでした。
本研究ではタバコ由来の培養細胞BY-2を用いて、植物から放出されることが知られている匂い物質による、抵抗性遺伝子誘導活性を検討しました。その結果、アロマオイルなどに含まれるß-カリオフィレンと、これに似た構造の匂い物質が、特異的に、ある抵抗性遺伝子の発現を3-6時間で誘導することを見出しました。さらに、タバコ植物体においても、ß-カリオフィレンはこの遺伝子の発現を、曝露開始から8時間で誘導することが示されました。これらの結果は、植物がß-カリオフィレンという匂い物質の特徴的な構造を識別していることを強く示唆するものです。そこで、タバコをモデルとして、ß-カリオフィレンの分子構造を認識する「匂い受容体」を探索することとしました。まず、ß-カリオフィレンに結合するタンパク質を釣り上げるプルダウンアッセイという実験を行ったところ、TOPLESSという転写制御因子がß-カリオフィレンに結合することがわかりました。そして、ß-カリオフィレンによる遺伝子の発現誘導に、TOPLESSが及ぼす影響を調べるため、TOPLESS タンパク質を多く持つ組み替えタバコ培養細胞と組み替えタバコ植物体を作出しました。これらを用いて、ß-カリオフィレンに対する応答を解析したところ、TOPLESSは抵抗性遺伝子の発現制御に関わっていることが示唆されました。以上の結果から、タバコにおいてTOPLESSがß-カリオフィレンを認識して、遺伝子発現誘導に関わっていることが示されました。
近年、植物が外部から取り込んだ匂い物質を材料として利用し、自身の抵抗性を高めるという機構が報告されています (Sugimoto et al., P.N.A.S., 2014)。しかし、匂い物質の情報を何らかのシグナルに変換し、遺伝子発現や成長の方向決定といった応答を引き起こす機構に関しては不明なままでした。本研究で、植物においては、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している1つの例が初めて示されました。今後、他の匂い物質に関してもこのような詳細な受容メカニズムが明らかとなれば、植物の生育環境の香りを調節することで、食害や病害に強い植物を作ることができることが期待されます。
本研究成果は、時事通信、毎日新聞で紹介されました。
●Nagashima, A., Higaki, T., Koeduka, T., Ishigami, K., Hosokawa, S., Watanabe, H., Matsui, K., Hasezawa, S., and Touhara, K.*
"Transcriptional regulators involved in responses to volatile organic compounds in plants"
J. Biol. Chem. in press (2019) -
匂いの価値や質が決まるしくみを受容体レベルで解明―求める香りをデザイン可能に― 要点:
1. 匂い物質が引き起こす好き・嫌い、誘引・忌避といった情動や行動が、嗅覚受容体レベルで規定される仕組みの解明を目指しました。その結果、一つ一つの嗅覚受容体は、好きや嫌いといった「価値(意味)」情報を持つことがわかりました。
2. 一般的に、匂い物質は複数の嗅覚受容体を活性化します。匂いが引き起こす情動や行動は、活性化されたそれぞれの嗅覚受容体が持つ「価値(意味)」情報が足し算され、そのバランスで決まることがわかりました。
3. ムスコンという匂い物質は、2種類のムスコン受容体それぞれがオスマウスにとって「好き」という情報を持ちます。また、(Z)-5-tetradecen-1-ol (テトラデセノール;Z5-14:OH)という匂い物質は、3種類のテトラデセノール受容体のうち一番感度の高い受容体にはメスマウスにとって「好き」という情報が、一番感度の低い受容体には「嫌い」の情報が規定されており、両方を活性化した時は「嫌い」の行動が現れることが明らかになりました。薄い濃度では良い匂いだが濃くなると嫌になる現象を説明しています。
4. ヒトの嗅覚では、匂いの「価値(意味)」は匂いの「質」と同等ですが、本研究の結果は、一つ一つの嗅覚受容体には「レモンのような香り」「バラのような香り」など、匂いの「質」が規定されていることを示しています。ヒト嗅覚受容体400個それぞれに規定されている匂いの「質」を明らかにすれば、求めるフレーバー(食品香料)やフレグランス(香粧品香料)をスクリーニングしたりデザインすることが可能になると期待されます。
成果の概要:
マウスは約1100種類、ヒトは約400種類の嗅覚受容体を持っていますが、一般的に1種類の匂い物質は複数の嗅覚受容体を活性化し、その結果、好き嫌い、誘引や忌避などの情動や行動が引き起こされることが知られています。しかし、匂いが持つ行動や情動といった価値情報が、嗅覚受容体レベルでどのように規定されているのか、例えば活性化された単一の嗅覚受容体で規定されるのか、複数の受容体が持つ価値情報の足し算なのか、あるいは受容体の活性化パターンが情報を規定しているのか、わかっていませんでした。今回、香粧品に汎用される匂いであるムスコンとオスマウスの尿中の匂いであるZ5-14:OH(テトラデセノール)に着目して、この問題に取り組みました。
ムスコンは2種類の嗅覚受容体、テトラデセノールは3種類の嗅覚受容体を活性化します。それぞれの受容体をノックアウトしたマウスを作製して解析した結果、ムスコンでは、2つの受容体それぞれがオスマウスにとって「好き」という価値情報を持っていること、テトラデセノールでは一番感度の高いテトラデセノール受容体は「好き」という価値、一番感度の低い受容体は「嫌い」の価値を持っており、両方の受容体が活性化される時は「嫌い」の忌避行動が表出することがわかりました。つまり、単一の嗅覚受容体が行動を引き起こす価値を規定していること、また、活性化された複数の嗅覚受容体の持つ価値情報の足し算とバランスにより最終行動が規定されていることが明らかになりました。
この成果の応用面としては、例えば、ある匂いの「価値(意味)」、すなわちヒトの嗅覚では匂いの「質」、を規定する嗅覚受容体を見つけることができれば、その受容体をターゲットにその匂いを呈するフレーバー(食品香料)やフレグランス(香粧品香料)をスクリーニングあるいはデザインすることが可能となります。この概念は、より美味しい食品やより芳しい香粧品を創成するためのツールのひとつになることが期待されます。
詳細:
生物にとって、外界のシグナルを感知し生存していくために、嗅覚は欠かせない感覚です。そのため、多くの生物は多数の嗅覚受容体を持っており、マウスでは約1100種類にも及びます。一般に、1種類の匂い物質で複数の嗅覚受容体を活性化し、例えばオイゲノールという匂い物質は約45個の嗅覚受容体を活性化します。近年、匂い物質に対して最も感度の高い受容体をノックアウトしたマウスでは、その匂いに対する感受性が下がることが明らかとなり (Sato-Akuhara et al., J. Neurosci., 2016)、単一嗅覚受容体と匂い感受性の関係が示されつつあります。
匂い物質は嗅上皮の嗅覚受容体で感知された後、その情報は嗅球、脳へと伝わっていき、情動・行動を引き起こします。多くの匂い物質はマウスにとって好きでも嫌いでもない中立的な匂いですが、例えばオスマウスの尿に含まれているテトラデセノールはメスマウスに先天的嗜好行動を (Yoshikawa et al., Nat. Chem. Biol., 2013)、キツネの糞に含まれているチアゾール系の匂い物質はマウスに先天的忌避行動を引き起こすことが知られています (Kobayakawa et al., Nature, 2007)。この忌避物質は複数の嗅覚受容体を活性化し、そのうちの1つの嗅覚受容体をノックアウトしても忌避行動はなくならないことが示されています (Saito et al., Nat. Commun., 2017)。一般に匂い物質は数多くの嗅覚受容体を活性化するため、一つ一つの嗅覚受容体と匂いの好き嫌いの関係はこれまで明らかになっていませんでした。
本研究では、比較的少数の嗅覚受容体を活性化する匂い物質であるムスコンとテトラデセノールに着目しました。これらの匂い物質を用いて、嗜好行動(「好き」)の観察に適しているTwo-choice odor-preference test(匂い選択嗜好テスト)という行動実験を行いました。この実験では、ケージに2つの穴が空いていて、その穴から匂いが吹き出しており、マウスがそれぞれの穴に興味を持って鼻を突っ込んでいる時間を測定します。また、嗜好と忌避行動両方の観察に適しているOdor investigation assay(匂い探索行動アッセイ)という行動実験も行いました。この実験では匂い物質をケージの床に置き、興味を持って匂い物質を嗅いでいる時間を測定しました。
ムスコンは2種類の嗅覚受容体を活性化しますが、その2種類の嗅覚受容体を同時に活性化しても、またはそれぞれ単独で活性化しても、オスマウスに「好き」という嗜好行動を引き起こせることが明らかになりました。一方、テトラデセノールは3種類の嗅覚受容体を活性化しますが、一番感度の高いテトラデセノール受容体だけを活性化すると嗜好行動が引き起こされ、3種類全てのテトラデセノール受容体を活性化すると忌避行動がおきました。一番感度の高いテトラデセノール受容体がノックアウトされたマウスでは、テトラデセノールへの嗜好行動は消失しましたが、忌避行動は残っていました。つまり、テトラデセノールの一番感度の高い受容体は「好き」の価値を持ち、感度の低い受容体は「嫌い」の価値を持つ受容体であり、その両方を活性化すると「嫌い」になることが明らかになりました。
嗜好・忌避行動など匂いの持つ価値が嗅覚受容体レベルでどのように規定されているかは不明でしたが、本研究で、それぞれの嗅覚受容体には匂いの「価値」や「質」などの情報が規定されていて、活性化される嗅覚受容体の持つ情報の足し算とそのバランスで情動や行動が規定されていることがわかりました。本成果はヒト社会での香りの開発に役立つ有効な知見を提供します。すなわち、一つ一つの嗅覚受容体には「レモンのような香り」「バラのような香り」など、匂いの「質」が規定されていることになりますので、ヒト嗅覚受容体約400個それぞれに規定されている匂いの「質」が明らかになれば、ターゲットの嗅覚受容体を見いだしてその匂いの「質」を持つフレーバーやフレグランスを開発することができます。本研究で明らかにした、匂いが持つ価値や質の情報を規定するしくみは、ヒト社会においてより美味しい食品やより芳しい香粧品を開発するために使える新しい基礎的概念となります。
●Horio, N., Murata, K., Yoshikawa, K., Yoshihara, Y., and Touhara, K.*
"Contribution of individual olfactory receptors to odor-induced attractive or aversive behavior in mice"
Nature Communications 10:209 (2019) -
仔マウスのシグナルを受け取ると雌マウスは雄の求愛を拒否する―幼少フェロモンESP22の脳神経受容機構を解明― さらに、交尾抑制フェロモンESP22のなかで高い活性を有する合成可能なペプチド断片を特定 雌マウスは、仔マウスの涙液中に含まれるフェロモンESP22 (Exocrine gland-Secreting Peptide 22)を受容すると、雄のマウント行動(求愛)を拒否する(雌マウスの性行動が抑制される)ことが明らかになりました。ESP22は生後2-3週令において時期特異的に仔マウスの涙液中に発現する幼少フェロモンで、その受容体は、フェロモンを受容する鋤鼻(じょび)神経細胞に発現するV2Rp4 (Vmn2r115) であることがわかりました。また、ESP22がV2Rp4に受容されてから雌マウスの性行動を抑制するまでに働く、一連の神経回路機構を明らかにしました。これまでにESP22が雄マウスの性行動を抑制することが知られていましたが、本研究で雌マウスの性行動の抑制にも働くことがわかりました。ESP22によって雌雄の成熟マウスの性行動が抑制されることは、仔マウスにとって、自らが十分に成長するまでの間、親マウスからの十分な養育を受け、安全かつ競争の少ない生息環境を維持するために有益であると考えられます。
マウスなどのげっ歯類において、性行動や攻撃行動といったさまざまな社会行動は、フェロモンなど化学感覚シグナルによって制御されています。タンパク性のフェロモンは、マウスの涙液中や尿に存在します。例えば、雄マウスの涙液中に含まれるESP1は、雌マウスの性行動を促進します。また、雄マウスの尿中に含まれるMUP3 (Major Urinary Peptide 3) は、雄マウスの攻撃行動を促進する働きを持ちます。フェロモンの中には、発現に性差が存在するものや、発現の時期に特異性があるものも存在します。その中の一つにESP1と同じペプチドファミリーに属するESP22があります。ESP22は生後2-3週令の仔マウスの涙液中において発現がピークとなり、性成熟後は発現が見られなくなります。 ESP22は周囲の雄マウスの性行動を抑制する働きを持つことが知られています。しかしESP22が、フェロモン受容器である鋤鼻器官 (Vomeronasal organ, VNO)にあるどの受容体によって感知されるのか、また、ESP22が雌マウスに対してどのような働きがあるかについてはわかっていませんでした。今回私たちは、ESP22が鋤鼻器官に発現している単一の受容体V2Rp4 (Vmn2r115) によって受容されること、また、ESP22が雄マウスだけでなく雌マウスの性行動も抑制し、その結果雌マウスの妊娠が遅れることを明らかにしました。さらに、その行動には脳内の分界条床核(BNST)から視床下部腹内側核の外腹側部(VMHvl)に投射している抑制性の神経細胞が関わっていることを解明しました。この成果は、性行動を制御する神経回路機構についての理解を深めるだけでなく、倉庫や都市部で問題となっているマウスの過繁殖や、それに伴う被害を抑制するための一助となる可能性があります。
マウスの尿や涙液中に含まれるペプチドの中には、フェロモンとして機能する分子が存在します。雄マウスの涙液中に含まれるESP1もその一つです。ESP1は雄マウスの攻撃行動を促進し、雌マウスの性行動を促進します (Haga et al., Nature 2010, Hattori et al., Current Biology 2016)。ESPペプチドファミリーに含まれる他のフェロモンとして、ESP22があります。ESP22は生後2-3週令に発現のピークが存在し、性成熟後はその発現は見られません。ESP22については、雄マウスの性行動を抑制することが明らかにされています (Ferrero et al., Nature 2013)。しかし、ESP22の受容体や雌マウスに対する機能はこれまでに解明されていませんでした。本研究では、雌マウスにおける幼少フェロモンESP22の脳神経受容機構とそのフェロモンによって引き起こされる行動出力を明らかにすることを目指しました。
まず、ESP22の雌マウスに対する働きを明らかにするため、さまざまな行動実験を行いました。その結果、ESP22をあらかじめ与えて嗅がせた雌マウスでは、雄マウスが交尾のためのマウント行動を仕掛けた際に、立ち上がったり、体をひねることで拒否する行動が、嗅がせていない雌マウスと比較して2-3倍多く観察されました。本研究グループはこれらの行動を拒否行動 (rejection) と定義しました。また、ESP22を雌マウスに約10日間連続して提示しながら雄マウスとの交配を行う実験を行いました。その結果、ESP22を提示した雌マウスでは、交配の開始から出産までに通常より2-3日長くかかる個体や、実験期間中に出産が観察されない個体がそれぞれ2-3倍多くなり、ESP22による性行動の抑制が交配の成功確率を低下させることで雌の妊娠ならびにその後の出産を遅らせることがわかりました。
次にESP22を受容する受容体の同定を試みました。鋤鼻器官には約120種類の鋤鼻2型受容体 (V2R) が存在し、不揮発性分子の受容に関わっています。タンパク性のフェロモンであるESP22の受容体を絞り込むために、まずdouble in situ ハイブリダイゼーションを行い、受容体候補V2R遺伝子を3つに絞り込みました。その後、CRISPR/Cas9ゲノム編集システムを利用して作製したノックアウトマウスを用いた実験を行い、単一の鋤鼻2型受容体V2Rp4 (Vmn2r115) がESP22の機能的な受容体であることが明らかになりました。V2Rp4はすでに同定されていたESP1の受容体V2Rp5ととても良く似た遺伝子配列を持つ受容体です。雌マウスの性行動を促進するESP1と抑制するESP22が、V2Rp5とV2Rp4という相同性の高い受容体で受容されながらも、雌マウスの性行動に対して正反対の行動をもたらすことは興味深い知見です。
鋤鼻受容体で受容されたシグナルは、鋤鼻神経細胞がその軸索を伸ばしている副嗅球 (AOB) へ伝達され、その後は、扁桃体内側核 (MeA) や視床下部腹内側核 (VMH) といった高次脳領域へと伝達されます。本研究では、ESP22が雌マウスのV2Rp4で受容された後、どのような神経回路を介して性行動が抑制されるのかについて解析を行いました。初期応答遺伝子を指標にした活性化細胞のマッピングや、人工的に合成された受容体分子への作動薬によって神経活動を制御する薬理遺伝学ツール(注6)によって、ESP22が雌マウスの性行動を抑制する機構には、MeAや分界条床核 (BNST) に分布する神経細胞が関わっていることが明らかになりました。また、ウイルストレーサーや光遺伝学による解析によって、ESP22が雌マウスの性行動の抑制を引き起こす際には、BNSTから視床下部腹内側核の外腹側部 (VMHvl) へと投射する抑制性の神経細胞の活性化が重要な役割を担っていることも示されました。本研究によってESP22は雌マウスにおいて、V2Rp4→AOB→MeA/BNST→VMHvlという経路を介して性行動を抑制することが明らかになりました。
本研究グループにおける先行研究によって、ESP1はV2Rp5→AOB→MeA→VMHd(視床下部腹内側核の背側部)という経路を介して雌マウスの性行動を促進することが明らかにされています (Ishii et al., Neuron 2017)。これらの研究成果をあわせて考えると、ESP22とESP1が相同性の高い鋤鼻受容体で受容されながらも、異なった神経回路によってその情報が伝達され、雌マウスの性行動に対して正反対の行動をもたらすということが明らかになりました。
仔マウスが分泌するフェロモンによって、周囲のマウスの性行動が抑制されることにはどのような生物学的意義があるのでしょうか。アカネズミなどの野生のマウスでは、主に雌マウスが縄張りを形成すること、また、雌マウスにおいて性行動が増加すると攻撃行動のモチベーションが上昇することも知られています。これらのことからESP22が周囲の雌マウスの性行動を抑制することで、母親以外の雌マウスによる自らや母親マウスへの攻撃行動を抑えている可能性が考えられます。また、ESP22が存在することで、周囲の繁殖を抑制し、仔マウスと生息空間や栄養を共有することになる同世代の個体の増加を抑制している可能性も示唆されます。その結果、仔マウスは自らが十分に成長するまでの間、安全な生息環境を維持しつつ、母マウスからの十分な養育を受けることができ、その後の生存につながる有益性を得ているものと考えられます。今後は、野生マウスを使った解析や、広い飼育フィールドを用いた解析を行うことによって、ESP22の自然環境下における意義が明らかにされることが期待されます。幼少フェロモンESP22が雄マウスだけでなく、雌マウスの性行動も抑制すること、また、その際の重要な神経回路基盤を明らかにした本研究の成果は、倉庫や都市部などで問題となっているマウスの過繁殖への対策につながる可能性があります。本研究成果は、Nature Communications 2018に掲載され、欧米のみならず中国やスペインなどのメディア16カ国で紹介されました。国内では日経新聞に取り上げられました。
さて、ESP22は約10kDaのタンパク質ですので、化学合成することは難しく、大腸菌などに作らせないと調整できません。そこで、ESP22の配列のなかで、最短で最大活性を有するペプチド断片を同定することを目指しました。その結果、24アミノ酸で非常に高い交尾抑制活性を持つペプチド断片を同定することに成功しました。この断片は化学合成することが可能なので、大量調整をして、マウスの繁殖制御に応用できることが期待されます (Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2019)。
●Osakada, T., Ishii, K.K., Mori, H., Eguchi, R., Ferrero, D., Yoshihara, Y., Liberles, S.D., Miyamichi, K.*, and Touhara, K.*
"Sexual rejection via a vomeronasal receptor-triggered limbic circuit"
Nature Communications 9, 4463 (2018) Osakada, T., Itakura, T., Kenmochi, R., and Touhara, K.*
"A sexual rejection peptide: potential use for controlling mouse overpopulation"
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry in press (2019) -
嗅覚受容体遺伝子の比較が明らかにした霊長類嗅覚系の退化の要因 —目・鼻の形態変化、果実食から葉食への食性の変化— 一般に、霊長類は視覚に依存した動物であり、嗅覚にはあまり依存していないと考えられていますが、霊長類の進化過程において嗅覚系の退化がいつどのようにして起きたかはよく分かっていません。私たちは、24種の霊長類について、ゲノムにコードされている嗅覚受容体(OR)遺伝子を詳細に比較し、OR遺伝子の退化のシナリオを明らかにしました。解析の結果、霊長類の中でも鼻腔の曲がったサル(曲鼻猿類)は鼻腔の真っすぐなサル(直鼻猿類)の約2倍のOR遺伝子を持つことがわかりました。また、対象とした24種の霊長類は目や鼻の形態、活動パターン(夜行性・昼行性)、色覚系、食性などが多岐に渡りますが、統計的な解析を行ったところ、鼻の形態と食性の違いが種によるOR遺伝子数の違いを有意に説明できることがわかりました。特に、葉をたくさん摂取する食性のサルほどOR遺伝子数が少ない傾向が見られました。一方、活動パターンや色覚系の違いはOR遺伝子数の違いにほとんど影響をおよぼさないことも示されました。また、霊長類の進化過程におけるOR遺伝子の消失速度を推定した結果、目と鼻の解剖学的な構造が大きく変化した直鼻猿類の共通祖先と、果実食から葉食へと食性が変化したコロブス類の共通祖先において、OR遺伝子の消失速度が速まったことが示されました。さらに、私たちヒトや類人猿では他の霊長類に比べてOR遺伝子の消失速度が速まっていることもわかりました。本研究は、ヒトの嗅覚系がどのように進化してきたかを理解する上で重要です。
匂いの認識は、鼻腔の嗅上皮にあるORに空気中の匂い分子が結合することにより始まります。これまでに調べられた哺乳類の多くは800~1200個のOR遺伝子を持つのに対し、ヒトやチンパンジー、ニホンザルではその数は300~400個です。それぞれの生物種が持つOR遺伝子の数は、その種の匂いの嗅ぎ分け能力を反映していると考えられます。私たちヒトを含む霊長類でOR遺伝子数が減少したのは、霊長類が視覚に依存した動物であり、嗅覚にはあまり依存していないことの証拠だと考えられてきました。しかし、霊長類の進化過程において嗅覚系の退化がいつどのようにして起きたかはよくわかっていません。そこで本研究では、目や鼻の形態、活動パターン(夜行性・昼行性)、色覚系、食性などが多様な24種の霊長類について、ゲノムにコードされているOR遺伝子の比較により、その退化のシナリオを明らかにしました。
霊長類は鼻の形態により曲鼻猿類と直鼻猿類の2つのグループに分けられます。解析の結果、曲鼻猿類は直鼻猿類の約2倍に相当する680~820個のOR遺伝子を持つことがわかりました。一方、コロブス類でOR遺伝子数が最も少なく、その数は約200個でした。つまり、サルの中にも、鼻の利くサルと鼻の利かないサルがいるのです。次に、系統関係を考慮した統計的な解析を行い、OR遺伝子数の種ごとの違いを説明する要因を探索しました。その結果、鼻の形態の違いを統計的に除去すると、活動パターンと色覚系の違いはOR遺伝子数を有意に説明しないことがわかりました。つまり、夜行性のサルがより鼻が利くということはないし、色がよく見えるからといって鼻が利かなくなるというわけでもありません。一方、食性の違いはOR遺伝子数を有意に説明していました。餌に占める葉の割合が大きいほど、また、果物の割合が小さいほど、OR遺伝子数が少ない傾向がありました。 次に、個々のOR遺伝子を進化的に追跡することによって、霊長類の進化過程においてOR遺伝子がどのくらいの速さで失われたかを調べました。その結果、直鼻猿類の共通祖先の系統でOR遺伝子の大規模な消失が起きたことが示されました。この系統では、網膜裏の反射板であるタペータムが失われるとともに、網膜に中心窩(ちゅうしんか)が形成され、高精度の視覚が実現したことが知られています。直鼻猿類の共通祖先の系統では、数百万年という比較的短い時間に嗅覚依存から視覚依存への移行が起きたと考えられており、OR遺伝子の大規模な消失もその過程の一環と考えられます。
霊長類の進化過程においてOR遺伝子の消失速度が最も速かったのは、コロブス類の共通祖先の系統でした。ニホンザルなどのオナガザル類は、果物を主な餌とするのに対し、コロブス類では主に葉を餌とします。コロブス類は、ウシのような反芻胃を持ち、胃の中の共生細菌の働きによりセルロースを消化することができます。そのため、固い葉や種子など、他のサルが食べられないものも餌とすることができます。果物を食べるサルにとっては匂いの情報は重要です。熟した果実は糖分を多く含み、特有の香りを発します。この香りは栄養分のシグナルであり、多くのサルは果実が熟したかどうかを判断するために匂い嗅ぎ行動(スニッフィング)を行います。一方、植物の側にとっては、サルに果実を食べてもらい、種を散布してもらうことが必要です。そのため、熟した果実の発する香りとそれを食べるサルの嗅覚は共進化したと考えられます。実際、果実を主な餌とするクモザルでは、熟した果実の香りの主成分に対する感度がラットやイヌに比べて高いことが報告されています。それに対し、葉を食べるためには匂い情報はあまり重要ではなく、コロブス類の一種であるテングザルが餌の葉をどのように選ぶかを調べた研究では、近くにたくさんある葉を食べるだけで、特にえり好みはしないことが報告されています。
本研究から、果実食から葉食への食性の変化が、霊長類の進化過程においてOR遺伝子の大規模な消失をもたらした主要な要因であることが示されました。私たちヒトは火を用いて調理を行い、哺乳類の中で最も豊かな食性を持ちます。またヒトや類人猿では、それぞれの種への進化過程でOR遺伝子の消失速度が速まっていることも示されました。以上のことから、本研究の成果は、ヒトの嗅覚系がどのように進化してきたかを理解する上で重要な示唆を与えるものです。本論文の成果は、朝日新聞で紹介されました。
●Niimura, Y., Matsui, A.,and Touhara, K.*
"Acceleration of Olfactory Receptor Gene Loss in Primate Evolution: Possible Link to Anatomical Change in Sensory Systems and Dietary Transition"
Mol. Bio. Evol. in press (2018) -
マウスは ラットの性シグナルを天敵情報として認識して 身をすくめる げっ歯類は鼻腔の鋤鼻器官で外界の匂いやフェロモンなどの化学シグナルを感知することで周囲の動物を認識し、そのシグナルに応じた行動を示すことが知られています。例えば、雄マウスの尿中タンパク質は同種の雌に性行動を促し、また、マウスの捕食者であるラットの尿中タンパク質はマウスに忌避行動を引き起こすことが知られています。近年、涙液中の化合物が同種の動物に行動を誘発することが分かってきましたが、異種の動物に対して化学シグナル分子を介した行動の誘発が見られるかどうかは明らかではありませんでした。今回私たちは、マウスの捕食者であるラットについて、雄の涙液中のタンパク質Cystatin-related protein 1(ratCRP1)がラットとマウス双方の鋤鼻神経系を活性化することを明らかにしました。同時にratCRP1は雌ラットに対して交尾行動に有利とされる一時停止行動を引き起こす一方、マウスに対しては鋤鼻受容体Vmn2r28を介した防御反応に関わる脳領域の活性化と、活動量の減少を引き起こすことが分かりました。以上の結果より、雄ラット涙液に含まれるタンパク質ratCRP1は、異性の雌ラットに対して性行動を促進するシグナルとして作用するだけではなく、マウスには異種動物の存在を示すシグナルとして感知されることが分かりました。哺乳類において、同種の異性間のシグナルが、被食者にとっての天敵の存在を示すシグナルとして認識および利用されることを示した初めて例です。
多くの動物は嗅覚から得られる周囲の情報に応じた行動をとります。例えば、天敵となる動物を感知すると逃げ、同種の異性を感知すると近づこうとします。げっ歯類においては、主嗅覚系と鋤鼻神経系という独立した2つの嗅覚システムにより、匂いやフェロモンなどのシグナルを受容します。主嗅覚系は主に匂い分子を受容するのに対して、鋤鼻神経系では主にフェロモン、異種の動物に由来する天敵の存在を示す分子などを受容します。例えば、尿中にフェロモンや天敵情報となる分子が含まれ、鋤鼻神経系で受容されることは知られています。また近年、涙液中にも鋤鼻神経系で受容されるフェロモンの存在が明らかとなっています。しかし涙液が異種の動物にも作用するかどうかは分かっていませんでした。そこで本研究では、自然界で捕食者‐被食者の関係にあるラットとマウスに着目し、涙液により嗅覚を介した異種動物への行動変化につながるかどうかの解明を目指しました。
まず、ラット涙液中にマウスの鋤鼻器官により受容される物質が含まれるかどうかを調べました。ラット涙液をマウスに嗅がせたところ、マウスの鋤鼻器官の多くの神経細胞で活性化が見られたため、ラット涙液成分をマウスに嗅がせる際の神経細胞の活性化を指標に、活性化物質の精製・同定を行いました。まずラット涙液をHPLCにより成分ごとに分画し、活性化成分をペプチドシーケンスにより同定したところ、Cystatin-related protein 1(ratCRP1)という、機能の解明されていないタンパク質であることが明らかになりました。また、発現解析の結果、ratCRP1は涙液を分泌するラットの眼窩外涙腺に多く存在すること、特に4週齢以降の性成熟した雄で発現が見られ、その量は男性ホルモンであるテストステロンにより制御されることが明らかになりました。
ratCRP1は雄だけに発現することから、ラットでは性行動に重要な意味を持つシグナルであると予想しました。ratCRP1をラットに嗅がせたところ、雌ラットの鋤鼻器官の神経細胞のみを活性化すること、さらに雌ラットはratCRP1を塗布したコットンに興味を持ってかみつき、その後その場で立ち止まる行動が増えることが分かりました。ラットでは交尾につながる性行動の一部として一時停止行動が知られており、ratCRP1は交尾行動に有利に働くと推測されます。
一方、マウスにおいてはどのような働きを示すのでしょうか。まずratCRP1の刺激により活性化される脳領域を調べました。その結果、扁桃体や視床下部腹内側核といった防御反応に関わる領域の活性化が見られました。次に、ratCRP1の刺激を受けたマウスではどのような行動・生理的変化が見られるかを調べました。遠ざかったり固まって動かなくなったり(フリーズ)するなどの忌避行動やリスクのレベルを判断する行動は見られませんでしたが、ratCRP1を塗布したコットンへのかみつき行動の減少、活動量や体温、心拍数の低下が見られました。また、ratCRP1はマウスの鋤鼻器官に発現する鋤鼻受容体のうちVmn2r28により認識されることが明らかになりました。さらにCRISPR/Cas9システムを用いて受容体Vmn2r28の遺伝子を欠損させたところ、ratCRP1によるマウスでの防御反応に関わる脳領域の活性化や行動変化は消失しました。つまり、ratCRP1はマウスの鋤鼻受容体によって感知され、その結果ratCRP1のある場所にいかなくなるとともに、体温や心拍数の低下を伴う活動量の減少といった「身をすくめる」体勢に入ることが分かりました。
まとめると、雄ラットの涙液に分泌されるratCRP1は、異性の雌ラットに対して性行動へと導くシグナルであると同時に、異種のマウスに対して天敵の存在を示すシグナルとして作用することが分かりました。1つの分子が、同種間だけではなく異種間のコミュニケーションにも関わるという今回の知見は、それぞれの種の生存のために、天敵の動物で使われているシグナルを有利に活用しており、進化の過程に嗅覚シグナルを介した駆け引きが行われたことを示しています。本論文の成果は、国内は朝日新聞など、国外ではNational Geographic, Science Daily, Science Newsline, Alphr, Valuewalkなど多くのメディアに取り上げられました。
●Tsunoda, M., Miyamichi, K., Eguchi, R., Sakuma, Y., Kikusui, T., Kuwahara, M., and Touhara, K.*
"Identification of an intra- and inter-specific tear protein signal in rodents"
Current Biology in press (2018) -
マウスの流産を引き起こすブルース効果の一端を解明~半世紀以上も謎であった原因物質の一つを特定~ 妊娠した雌マウスにおいて、交尾相手以外の別系統の雄マウスとの接触により流産が引き起こされることが1959年に報告され、この現象は発見者の名前に因み「ブルース効果」と名付けられました。しかし、現在に至る半世紀以上の間も、この流産の原因物質は特定されていませんでした。本研究では、雄フェロモンであるESP1の分泌量がマウス系統ごとに異なることに着目し、ブルース効果におけるESP1の関与を検証しました。その結果、雌は交尾後、交尾相手とはESP1の分泌量が異なる雄マウス系統と接触するとブルース効果(流産)が起きることがわかりました。そこで、雌マウスに対し、ESP1分泌のない雄マウスとの交尾後にESP1を暴露すると、通常流産が確認できない同系統との接触においても流産することがわかりました。このESP1による流産は、ESP1に対する受容体を欠損した雌マウスでは確認できませんでした。また交尾後の雌マウスに対してESP1を暴露すると、受精卵着床に必要なホルモンであるプロラクチンの分泌が見られないことがわかりました。本研究の成果は、交尾相手以外の雄マウスとの接触による流産という劇的な生理現象について、原因となるフェロモン分子の特定から内分泌系を介した生殖への影響に至る、分子から個体機能をつなぐ初めての報告です。
ブルース効果の検証実験は次のように行います。まず雌マウスと雄マウスを一晩同居させ、交尾を確認した後、雌マウスを1日単独飼育します。次に、交尾相手の雄マウスとは別系統の雄マウスを、交尾後の雌マウスに2日間接触させます。そしてその1週間後、子宮内における受精卵の着床を確認することで、妊娠か流産かをチェックします。この方法を用いることで、複数の実験用マウス系統について流産の起きる組み合わせを探しました。その結果、同じ系統同士の組み合わせでは流産は起きませんでしたが、Balb/CまたはDBA系統とそれ以外の系統の組み合わせでは流産が確認されました。一方、Balb/CとDBAの組み合わせ、またBalb/CとDBA以外の系統間の組み合わせでは流産は起きませんでした。
この結果を受けて、私たちは雄フェロモンの一つであるESP1という分子に着目しました。なぜならばESP1はBalb/C及びDBA系統において分泌が見られますが、その他の系統では分泌しないからです(Haga et al. Nature 2010)。そこでブルース効果はESP1を分泌する系統と分泌しない系統の組み合わせで生じるという仮説を立て、ESP1がブルース効果の原因物質である可能性を検証しました。まず雌マウスと同系統の雄マウスの組み合わせでは通常流産は起きませんが、ESP1を交尾前の雌マウスに暴露すると、同系統の雄マウスの場合でも流産が起きることがわかりました。また、交尾後、通常流産が起きない同系統の別の雄と接触する前にESP1を暴露しても流産が起きることがわかりました。この場合の流産はESP1の受容体を欠損した雌マウスでは確認できないことから、ESP1に依存して起きる現象であることが示唆されました。ただしESP1のみでは流産は起こらず、雄マウスとの接触も必要であるため、個体ごとに異なる尿中の因子とESP1の協調的な働きが重要と考えられますが、その因子はまだ不明です。また、受精卵着床時に分泌量が増加するホルモンであるプロラクチンについて、その分泌時期にESP1を暴露した場合、雌マウスでの分泌量増加は確認できなくなりました。これらの結果を総合すると、交尾後に雌マウスがESP1の分泌量の異なる別系統雄マウスと接触した場合、プロラクチンが正常に分泌されず、受精卵は着床に失敗し、流産が引き起こされると考えられます。
今回、ブルース効果の原因物質の一つがESP1であることがわかりましたが、それではブルース効果の生物学的意義は何でしょうか。雄にとっては交尾相手の確保を確実にするため、雌では優勢雄の仔を残せることや、コロニー(集団)を乗っ取った新たな雄の仔を産むことによって将来の仔殺しを回避する、などのメリットが挙げられています。ただしブルース効果は実験用マウスで発見された事象であり、野生のマウスについては現在も確認されていません。また他の動物についてはキヌゲネズミ科のネズミや霊長類のゲラダヒヒでブルース効果が報告されていますが、その生物学的意義に関しては不明です。今回の発見は、ブルース効果の生物学的意義に迫る第一歩になると考えられます。また、ヒトのブルース効果は見られないと考えられますが、今回の着床とホルモンに関連する新たな知見が、着床率を高めることで妊娠成立を補助するための有用な基礎的知見につながることも期待されます。今回の成果は、化学感覚シグナルである「フェロモン」による生理状態や生殖などの個体機能制御について、フェロモン分子とその受容体から内分泌系に至る多階層での理解につながるものです。今後、脳神経系での情報伝達や処理など、ヒトをはじめとする哺乳類での複雑な化学感覚シグナル受容の理解につながる有用な基礎研究基盤となる可能性があります。
●Hattori, T., Osakada, T., Masaoka, T., Oyama, R., Horio, N., Mogi, K., Nagasawa, M., Haga-Yamanaka, S., Touhara, K.* and Kikusui, T.*
"Exocrine gland-secreting peptide 1 is a key chemosensory signal responsible for the Bruce effect in mice"
Current Biology in press (2017) -
マウスの性行動を促進させる脳神経回路を決定ー交尾相手と天敵を嗅ぎ分ける専用回路ー マウスは性行動や攻撃行動、天敵からの忌避行動といった様々な本能的な行動の制御に、匂いやフェロモンなどの化学感覚シグナルを利用しています。しかし、特定の化学感覚シグナルの入力が適切な行動出力へと変換される脳内の神経基盤は明らかになっていませんでした。雄マウスの涙液に分泌される約7 kDaのペプチドESP1は、雌マウスに対しては性行動促進、他の雄マウスに対しては攻撃行動促進の作用が見られます。私たちは、本論文で、ESP1による雌マウスでの性行動促進に関わる神経回路について、細胞レベルでその構造と機能を明らかにしました。その過程において、扁桃体という脳の一部の領域がESP1シグナルの伝わり方を性別によって変えるスイッチの役割を果たすことを発見しました。また、マウスの天敵であるヘビ由来のシグナルとESP1が脳内の同一領域を活性化することが知られていましたが、細胞レベルではそれぞれ専用の神経細胞を使って情報処理されることが分かりました。“性”行動の相手となる雄マウス由来のシグナルと、自然界で遭遇した際には個体の“ 死” に直結する天敵からのシグナルには、それぞれ専用の神経回路が割り当てられるという今回の発見は、本能的な行動を制御する神経基盤のモデルを提供するものです。
生物は、外界からの様々なシグナルを感知し、それに基づく対応する行動を起こすかどうかを判断します。多くの場合、このプロセスには学習が必要ですが、中には学習を必要としない、特定の本能的な行動を引き起こすシグナルもあります。例えばマウスにおいて、異性や同性、天敵由来の化学感覚シグナル (匂いやフェロモンなど) は、性行動や攻撃行動、忌避行動をそれぞれ引き起こすことが分かっています。では、特定の化学感覚の入力を受けた適切な行動出力の選択は、どのような神経基盤によるものでしょうか。この疑問を解決するためには、末梢の受容器官から行動を引き起こす脳の中枢に至るまでの、化学感覚シグナルの情報が伝達される神経回路を詳細に明らかにすることが必要でした。しかし、動物の行動を制御する化学感覚シグナルの多くは、多様な脳領域を活性化させる混合物なので、これまでその基盤となる神経回路の解析が困難でした。私たちは、それだけで一種類の受容体を介して行動に影響を与えるESP1というフェロモンに着目することで、このフェロモン情報を処理する専用の神経回路について、その構造と機能を細胞レベルで明らかにしました。
ESP1は成熟した雄マウスの涙液中に分泌されるフェロモンです。雌マウスがESP1を受容すると、雄との交尾を受け入れる姿勢であるロードシス反射を示す頻度が上昇します。また、雄マウスがESP1を自分とは異なる系統の雄マウスの尿と同時に受容すると、攻撃行動が促進されることも分かっていました。ESP1は鋤鼻器官に発現するV2Rp5という単一種類の鋤鼻受容体によって受容されます。その後、末梢の細胞で受け取られた情報は、様々な脳領域に分布する神経細胞群を経て、行動の制御に深く関わる脳の中枢の神経細胞へと、順々に伝達されていきます。本研究では、その伝達されていく様子を、感染した神経細胞を起点に、その細胞から情報を受け取る下流の細胞へと伝染していく性質を持った順向性ウイルストレーサーを用いることで明らかにしました。順向性ウイルストレーサーをV2Rp5発現細胞に感染させることで、その下流に位置する中枢の神経回路を可視化しました。その結果、V2Rp5発現細胞から扁桃体や視床下部といった情動や行動を制御する脳領域に情報が伝達される順序が明らかとなりました。次に、V2Rp5の下流として同定された脳領域において、薬理遺伝学を用いて、その領域のみを阻害することで、ESP1による雌マウスの性行動促進作用に必要な領域を探索しました。その結果、扁桃体の中でも鋤鼻器官からの情報をよく受け取る内側扁桃体という脳領域の後腹部(MeApv)の必要性が明らかになりました。
さらに詳細な観察から、MeApvの中には特定の視床下部領域に偏って情報を伝達するタイプの神経細胞集団が存在することが分かりました。興味深いことに、ESP1の刺激によって雌マウスではMeApvから視床下部の腹内側核背側部(VMHd)へ情報を伝達するタイプの神経細胞が活性化されました。これに対して雄マウスでは、VMHdではなく視索前野(MPA)へ情報を伝達するタイプの神経細胞が活性化されていました。このように、MeApvはESP1の情報を受け取る際、シグナルを伝達するルートを性別により変更する“スイッチ”として機能することが分かりました。これは、ESP1が雌雄において異なる作用を持つための神経基盤と考えられ、性別による脳神経回路の機能的な差異を研究するための優れたモデルを提供するものです。
さて、雌マウスにおいてESP1の情報が伝達されることが明らかとなったMeApvからVMHdへの経路は、これまで忌避行動を引き起こす天敵のシグナルの伝達に深く関わっていることが知られていました。では、この一見すると同じ経路の中で、ESP1による性行動の促進と、天敵のシグナルによる忌避行動の促進は、どのように区別されて処理されているのでしょうか。本研究ではESP1とヘビの抜け殻 (天敵のシグナル) によって活性化される神経細胞の集団が異なることを示しました。次に、特定の化学感覚シグナルの刺激によって活性化される神経細胞のみを標識する手法(TRAP法)によって、ESP1に応答する神経細胞のみを操作する系を確立しました。これを用いてVMHdのESP1応答神経細胞を光遺伝学で活性化すると、あたかもESP1を受け取ったかのように雌マウスのロードシス反射が促進されました。この結果は、これまで忌避行動の中枢と思われていたVMHdの中に、雌の性行動を正に制御する神経細胞が別個の集団として存在することを示しています。すなわち “性”行動の相手となる雄マウス由来のシグナルと、自然界で遭遇した際には個体の“ 死” に直結する天敵からのシグナルは、隣り合う専用の神経細胞によって処理されています。このような特異的な構造が進化してきた理由や発生段階でどのように形成されるのかについては今後の研究が必要です。
一つの感覚シグナルに対して脳の”専用回線”が割り当てられているというしくみは、動物にとって重要な意味を持つ感覚シグナルが適切な行動出力へと変換されるのに好適です。今回の成果は、マウスの本能行動がどのように制御されているかの理解を深めるのみならず、本能行動に影響を与える様々な感覚シグナルを研究するための汎用的な方法論を提供するものです。加えて、雌の性行動を制御する脳神経回路に関する新たな知見は、中枢性の性機能障害を理解するための基礎的知見を提供するものです。本論文の成果は、朝日新聞、ヤフーニュース、時事メディカル、日経などに取り上げられました。
●Ishi, K., Osakada, T., Mori, H., Miyasaka, N., Yoshihara, Y., Miyamichi, K.*, and Touhara, K.*
"A Labeled-Line Neural Circuit for Pheromone-Mediated Sexual Behaviors in Mice"
Neuron in press (2017) -
ヒト乳幼児の匂いが親の養育行動に寄与する-子のの匂いに関する調査- 乳幼児は、乳幼児期特有の容貌、笑顔、泣き声など、親の養育行動を引き出す特性を備えていると考えられています。このような乳幼児の特性は、今までにヒトでは視聴覚を介するものが多く研究されてきました。一方、乳幼児の体から発せられる匂いが、日々の養育に寄与しているのかどうかは、これまで殆ど調べられていませんでした。私達は、未就学児の父母を対象としたインターネット質問紙調査を行い、父母が我が子の匂いに気付いたり嗅いだりすることがあるか調べました。その結果、未就学児の父母、とりわけ0歳児のお母さんは、日常の育児で子供の匂いに気付き、自発的に嗅いでいることが分かりました。0歳児のお母さんが最もよく嗅ぐ体の部位は、赤ちゃんのお尻と頭で、お尻はオムツ交換など衛生ケアのために、頭はよい匂いがする、愛おしいなどの愛着に関わる理由で嗅いでいました。この他、赤ちゃんの額、口、首、手の匂いに対しても、愛おしいという気持ちを抱いたり、清潔か確認したりする際に嗅いでいました。これらの結果を総合すると、子の匂いが親の養育行動につながっており、養育行動の頻度や内容は、子の発達段階や親の性別(父母)によって異なることが示唆されました。 親の養育行動に対する子のシグナルの影響については、ヒトでは笑顔や泣き声など、視聴覚の物理的なシグナルを中心に研究されてきました。今回の調査により、乳幼児の匂いという嗅覚による化学的なシグナルも、愛おしいという気持ちの誘起や、衛生状態を知る手がかりとして、親の養育行動につながっている可能性が示唆されました。また、頭やお尻など、匂いの源として特に重要な体の部位が特定されました。今後、これらの部位を中心に、子の匂いの成分を詳しく調べていくことにより、匂いを介した養育行動・親子関係構築の支援につながる可能性があります。本研究の成果は、養育行動に対する子の感覚シグナルの役割の解明や、ヒトの嗅覚の機能を明らかにする研究の進展に貢献すると期待されます。
●Okamoto, M.*, Shirasu, M., Fujita, R., Hirasawa, Y., and Touhara, K.
"Child odors and parenting: A survey examination of the role of odor in child-rearing"
PLoS ONE 11(5): e0154392 (2016) -
ムスクの香りを感知する受容体の応答特異性と進化—たった一つの受容体がムスク香の感知に影響を及ぼす— ムスクの香りは、その魅惑的な香りゆえ、古代から香料として用いられています。しかし、近年、ムスコンを代表とする天然ムスク香料は入手困難となり、これに代わる、新たな合成ムスク香料の開発は産業界で常に課題となっています。一方で様々な化学構造をもつ合成ムスク香料や天然ムスク香料が、なぜ我々の鼻で同じようなムスク香と感じられるのかは、化学界・香料業界において長年の謎でした。今回私達は、先に同定されたマウスのムスコン受容体MOR215-1とヒトのムスコン受容体OR5AN1に加えて、4種の霊長類のムスコン受容体を新たに同定しました。さらに、ムスク系香料への応答特異性の解析から、これらの受容体の匂い感知メカニズムを明らかにしました。また、ヒトやマウスがムスクの香りを感知する際には、特定の嗅覚受容体の働きが重要であることを明らかにしました。本研究の成果は、ムスクの香りの感知メカニズムを解明すると共に、ヒトムスコン受容体の匂い応答特性を評価系とする新たなムスク香料開発に繋がると期待されます。
ムスクは、その魅惑的な香りから、多くのトイレタリー製品や香粧品に用いられます。最初に発見された天然ムスク香料であるムスコンは、ジャコウジカの雄の臭腺から分泌され、性フェロモンのような役割をもちます。しかし、ジャコウジカは現在保護動物に指定されているため、天然ムスクは非常に希少となっています。そのため、同じムスク香をもつ様々な化学構造の合成ムスク香料がこれまで開発されてきましたが、中には皮膚への感作性をもつものや難分解性のものがあり、安全性と香気性を兼ね備えたより良いムスク香料の開発は、未だに香料業界の課題となっています。さらに、化学構造の異なるこのような化学物質が、受容体レベルでどのように感知されているのか、長年疑問でした。私たちは、鼻の奥にある嗅覚受容体というセンサータンパク質に、匂い分子が結合することで、その匂いを感じることができます。通常、匂い分子は複数の嗅覚受容体に認識され、その受容体の組み合わせによって、物質による匂いの違いが生じます。近年当研究室では、天然ムスクのムスコンを感知するマウスとヒトの嗅覚受容体を同定しました(Neuron 2014)。さらに、マウスではムスコン受容体が非常に少数であり、ムスコンのような大環状ケトンにのみ応答する高い選択性を示すことがわかりました。
本研究では、系統解析と培養細胞を用いた実験を組み合わせて、新たに6種の哺乳類のムスコン受容体を同定しました。まず、13種の哺乳類における嗅覚受容体の遺伝子配列から、先に同定されたマウスとヒトのムスコン受容体周辺の系統樹を作成しました。ヒトムスコン受容体OR5AN1が含まれる遺伝子グループには、マウスの遺伝子の他、複数の霊長類の遺伝子が存在しました。一方、マウスムスコン受容体MOR215-1の遺伝子グループに含まれる遺伝子群は、齧歯目の遺伝子のみでした。また、これら2つの遺伝子グループのちょうど間に位置するグループには、複数種の霊長類の遺伝子が含まれていました。そこで、これら3つの遺伝子グループに着目し、これらに含まれる嗅覚受容体遺伝子の、ムスコンへの応答性を調べることにしました。嗅覚受容体の匂い物質に対する応答の解析には、HEK293培養細胞を使ったルシフェラーゼアッセイを用いました。上記3つの遺伝子グループに含まれる嗅覚受容体を培養細胞に発現させ、ムスコン刺激を行ったところ、それぞれの種で1~2個の嗅覚受容体が応答を示しました。ここから、3つの遺伝子グループに含まれる嗅覚受容体は、ムスコンへの応答能を有しており、マウスからヒトに至るまで、その応答能は保存されていることがわかりました。
次に、これらのムスコン受容体の、様々なムスク香料に対する応答性を解析しました。ムスク香料は、ムスコンのような大環状構造をもつ大環状ムスク、ベンゼン環にニトロ基のついたニトロムスク、環状構造が連なる多環式ムスク、炭素鎖をもつ鎖状ムスク、並びにムスク香料ではないもののムスコンと構造的に関連した化合物、計25種を使用しました。その結果、全てのムスコン受容体は大環状ムスク、特にムスコンと同じくケトン基をもつ大環状ケトンに対して応答を示しました。また興味深いことに、ヒトムスコン受容体OR5AN1は、ムスコンとは全く異なる化学構造をもつニトロムスクに対しても強い応答を示しました。さらに、ニトロムスクだけでなく、大環状中に二重結合をもつ、不飽和大環状ケトンといった、私たちが実際に匂いを嗅いでみてムスク香が強いと感じる物質に対して、OR5AN1は強い応答を示しました。ムスコンには鏡像異性体が存在し、l (R) 体は強く華やかなムスク香をもつのに対して、d (S) 体はムスク香が弱いことが知られています。ルシフェラーゼアッセイを用いて、ヒトムスコン受容体OR5AN1のムスコン鏡像異性体に対する応答性を調べたところ、l体に対して、d体よりも強い応答を示すことがわかりました。この結果はOR5AN1の応答性がヒトのムスク香に対する感覚と一致していることを示しています。
さらに花王株式会社にいる当研究室の卒業生たちが、約400種存在するヒト嗅覚受容体から、ムスク香料のムスコンとニトロムスクに応答する受容体を探索するスクリーニングを行ってくれました。その結果、どちらのムスク香料も、強い応答を示したのはOR5AN1のみでした。OR5AN1はムスコンに限らず、ヒトのムスク香の感知に大きく寄与している可能性が示唆されました。マウスでは、最も感度の高いマウスムスコン受容体MOR215-1を欠失させた変異マウスを作製しました。匂い探索実験の結果、この変異マウスは野生型マウスに比べて大幅にムスコンの香りを感知しづらくなることがわかりました。このことはマウスにおいても、ムスクの匂いの感知には、ムスコン受容体であるMOR215-1が重要な役割を果たしていることを示唆しています。
本研究により、“ムスク香料が異なる化学構造をもつにも関わらず、同じようなムスク香をもつのは、同じ受容体で認識されるからである”ということがわかりました。また、ヒトのムスコン受容体の匂い応答特性を用いた匂い物質スクリーニング技術について国内特許を取得中であり、受容体応答性を評価指標とした産業的に有用なムスク香料の開発に繋がると期待されます(現在国内企業2社に実施許諾中)。
●Sato-Akuhara, N., Horio, N., Kato-Namba, A., Yoshikawa, K., Niimura, Y., Ihara, S., Shirasu, M.*, and Touhara, K.*
"Ligand specificity and evolution of mammalian musk odor receptors: the effect of single receptor deletion on odor detection"
J. Neuroci. 36, 4482-4491 (2016) -
オスらしさを高めるフェロモンをマウスで発見—フェロモンに新しい概念— オスマウスの涙には、ESP1というフェロモンが含まれることが知られています。外に分泌されたESP1は、メスの鼻の下部にある鋤鼻器官を刺激して、メスの性行動を促進させます(Haga et al. Nature 2010)。しかし、他のオスに対してどのような作用があるかは不明でした。本研究では、ESP1が、尿の存在下、オスに攻撃を促す効果があることを見いだしました。さらに、オスは、性成熟とともに分泌が増加するESP1が自分自身にも作用することによって、自身が持つ攻撃性がさらに高まることがわかりました。本研究の成果は、性フェロモンが異性に作用するだけでなく、同性の他個体や、さらには分泌する自分自身にも作用するという、フェロモンの新しい概念を提供する発見です。
匂いやフェロモンといった化学感覚シグナルは、哺乳類のさまざまな行動や情動を制御しています。なかでも、尿、涙、唾液、汗などの外分泌液に含まれるフェロモンは、受け取った個体の嗅覚系を介して脳にその情報が伝達され、その結果、社会行動や性行動など、哺乳類にとって重要な行動を引き起こします。つまり、フェロモンによって、哺乳類のさまざまな行動が適切に管理され、生命の維持と種の存続が保証されます。
オスマウスの涙には、ESP1というフェロモンが含まれています。メスマウスは、オスと接触することによって、鼻腔下部に存在する鋤鼻器官でESP1を受容します。すると、背中をそらしてオスマウスの交尾を受け入れやすくする体勢(交尾受け入れ行動)をとります。すなわち、オスから分泌されたESP1は、メスの性行動を促進させる性フェロモンとして機能します。それでは、ESP1は他のオスに対してどのような効果があるのでしょうか。また、ESP1はオスの性成熟時に男性ホルモンの上昇に伴って分泌され始め、自分自身のESP1を受容しますが、そのときオス自身の身体でどのような変化が起きるのでしょうか。私達は今回これらの疑問を明らかにしました。
オスは別のオスが住処に侵入してくると攻撃しますが、去勢したオスに対しては攻撃を仕掛けません。しかし、ESP1を分泌しないオスに、ESP1をあらかじめ与えて嗅がせておくと、去勢したオスが入ってきても攻撃することがわかりました。一方で、その攻撃はESP1の受容体であるV2Rp5を欠損しているオスでは見られませんでした。また、この攻撃には尿のシグナルも必要であることがわかりました。つまり、ESP1は尿の存在の下で、オスに対しては攻撃のシグナルとして作用することがわかりました。また、ESP1を分泌するオスは、分泌しないオスにくらべて攻撃性が高いことがわかりました。そこで、ESP1を分泌するオスのV2Rp5を欠損させたところ、ESP1を分泌しているにも関わらず、分泌しないオスと同じ程度の攻撃性しか見られませんでした。これらの結果は、性成熟時に分泌されたESP1を自分で受容することによって、攻撃性が上昇することを示唆しています。すなわち、ESP1は他のオスに対して攻撃を促す機能を持つだけでなく、分泌している自分自身に対しても攻撃性を高めるために働いているということがわかりました。
つまり、本研究では、ESP1というオスのフェロモンは、メスには性行動促進、オスには攻撃性亢進という異なったアウトプットを引き起こすということを明らかにしました。また、遺伝学的な手法を用いることによって、メスとオスとでの行動アウトプットの違いは、脳神経回路の性的二型によることが示唆されました。一般的に、性フェロモンは異性に対しての作用がよく知られていますが、分泌している自分自身にも効果があるという今回の結果は、既存のフェロモンの概念にはなかったものです。自然界において、ほとんどの野生マウスのオスはESP1を分泌しており、ESP1は成熟してオスの攻撃性を高めるための重要な因子といえます。今回の成果は、マウスの行動がどのような化学感覚シグナルによって制御されているか、その理解を深めるもので、今後、哺乳類の情動や行動を支配・制御する脳神経回路の解明に向けて、有用な基礎研究基盤となるものです。
本研究は、東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授研究室と故森裕司教授研究室(菊水助教:当時)との共同研究でスタートし、その後、同研究科の東原和成研究室と麻布大学獣医学部動物応用科学科の菊水健史研究室との密な共同研究で達成されたもので、故森裕司教授に捧げる論文となりました。本論文は、朝日新聞、日刊工業新聞、Yahoo!ニュース、時事通信、マイナビニュースなど多くのマスメディアに取り上げられ、また一般向けの雑誌のニュートンの記事にもなりました。
●Hattori, T., Osakada, T., Matsumoto, A., Matsuo, N., Haga-Yamanaka, S., Nishida, T., Mori, Y., Mogi, K., Touhara, K.* and Kikusui, T.*
"Self-exposure to the male pheromone ESP1 enhances male aggressiveness in mice"
Current Biology 26, 1229-1234 (2016) -
産業的に有用なミントの香りを呈するメントールの鏡像体を識別する嗅覚受容体の発見 私達の鼻は、多種多様なにおいを識別することができます。右手と左手の鏡像体関係にある匂い物質も、化学的特性が同じにも関わらず、違うにおいを呈することが多々あります。私達は鏡像体が鼻でどのように感知されているのかに興味を持ち、商業的に有用でミントの香りを呈するメントールを用いて、マウスの嗅覚のおける応答特性を解析しました。マウスをl-メントールとd-メントールで刺激すると、嗅球において、一部重なるが異なる応答パターンが見られました。つまり、片方の鏡像体に特異的に応答する受容体と両方を認識する受容体があることがわかりました。この事実が鏡像体でもにおいの質が異なる科学的な理由です。さらに、l-メントールとd-メントールに特異的な嗅覚受容体の遺伝子を単離することに成功して、構造活性相関を調べました。鏡像体特異的な受容体は、匂いに対する選択性も高いことがわかりました。今回の成果は、鏡像体のにおいを評価する上で、有用な知見となります。
今回の成果にはもうひとつ重要な知見があります。今回用いたメントールは、高砂香料工業(株)から、純度99.925%、光学純度>99.99 eeという大変きれいなものを特別にいただいて用いています。私達の結果は、嗅覚受容体は匂いによって100倍くらい感度が違うものもざらに存在するということを示しているので、もし1%でも不純物が混ざっていると、匂い応答に影響する、つまりにおいの質にも影響するということになります。嗅覚の世界では、99%純度でも十分だろうと思ってはいけないということです。ある匂い物質を、香りとして商業利用するときには、純度はもちろん、光学純度も高いものを使うことに意義があるということを示しています。
●Takai, Y., and Touhara K.*
"Enantioselective recognition of menthol by mouse odorant receptors"
Biosci. Biotechnol. Biochem. 79, 1980-1986 (2015) -
アミノ酸共進化理論に基づいた昆虫嗅覚受容体の立体構造モデル構築と機能ドメインの発見 昆虫において、匂いやフェロモンを感知する嗅覚受容体は、7回膜貫通型のタンパク質のヘテロ複合体であり、リガンド作動性のイオンチャネルです。他のタンパク質と相同性がないため、どのような立体構造をしているか全く不明でした。本研究では、アミノ酸共進化理論に基づいて、昆虫嗅覚受容体チャネルの立体構造予測に初めて成功しました。得られたモデル構造は、以前に機能解析によって予測されていた匂い結合やチャネルポアの部位を支持するものでした。また、モデル構造をもとに、新規に機能をもつ部位の同定にも成功しました。嗅覚をターゲットとした昆虫の行動制御へ向けての新たな視点を提供する成果です。
匂いやフェロモンは、嗅覚受容体によって感知されます。哺乳類の嗅覚受容体は7回膜貫通型のGタンパク質共役型受容体ファミリーに属します。一方、昆虫の嗅覚受容体は、同じ7回膜構造をとるにも関わらず、N末端が細胞質側に存在するというユニークな構造をとります。さらには、ヘテロ複合体を形成してリガンド作動性のイオンチャネルとして機能します(Sato et al. Nature 2008)。昆虫嗅覚受容体は、各々の昆虫種で約60-300個もの多重遺伝子として存在していることから、最大の受容体チャネルファミリーを形成すると考えられています。しかし、他のイオンチャネルとの相同性はまったくありません。そこで、立体構造に大変興味がもたれていますが、大量発現の困難さから結晶化が遅れています。
本研究では、空間的に相互作用するアミノ酸はお互いに制約しあって共進化するという最先端のタンパク質構造予測理論に基づき(Marks et al. Nature Biotech. 2012)、現在わかっている昆虫嗅覚受容体すべてのアラインメントから、進化的に制約しあっているアミノ酸の「contact map」を作成し、それをもとに立体構造モデルを構築しました。以前に当研究室で同定したチャネル活性に関わるアミノ酸は(Nakagawa et al. PLOS One 2012)、モデル構造上でタンパク質表面のお互いに隣接した空間に存在しており、ヘテロ複合体のチャネルポアの形成に関わっているということをうまく説明できます。また、細胞質側にでているN末端部分が高い共進化相互作用の可能性が示唆されたので、この部分の欠損体や部位特異的変異体を作製したところ、活性が失われることがわかりました。新しい理論のもとに構築した立体構造モデルの信憑性が支持されたのと同時に、新規の機能ドメインが同定され、本研究で使ったアミノ酸共進化相互作用理論が有効であることが証明されました。これらの知見は、嗅覚をターゲットにした昆虫の行動制御における新たな試薬のデザインのために、有益な情報となると期待されます。
本研究は、ローザンヌ大学の指揮のもと、ハーバード大学がコンピューターモデリングを担当、東京大学が機能解析を担当して共同でおこなったものです。
●Hops, T.A., Morinaga, S., Ihara, S., Touhara K., Marks, D.S., and Benton, R.*
"Amino-acid coevolution reveals three-dimensional structure and functional domains of insect odorant receptors"
Nature Communications 6:6077 doi: 10.1038/ncomms7077 (2015) -
Gタンパク質共役型受容体キナーゼ3は嗅覚受容体の脱感作にあまり関わっていない可能性を示唆 私達の嗅覚は、匂いを嗅ぎ続けるとわからなくなるという順応(慣れ)をおこします。順応は、匂いを感知する嗅覚受容体レベル、嗅覚一次中枢である嗅球レベル、さらに高次脳レベルと様々な部位でおきることが知られています。嗅覚受容体の脱感作については、他のGタンパク質共役型受容体と同様に、リン酸化酵素によるリン酸化によるものと考えられています。Gタンパク質共役型受容体キナーゼ3(GRK3)が嗅神経細胞に発現しており、匂いが嗅覚受容体に結合すると、嗅覚受容体はGRK3によるリン酸化を受けて脱感作するというメカニズムが提唱されています。しかし、直接的かつin vivoでの証拠はありませんでした。
私達は、in vitroおよびin vivoでの解析が詳細にされているオイゲノール受容体mOR-EGを用いて、リガンド依存的な受容体の脱感作がおきるか検証しました。GRK3が存在する条件下でHEK293培養細胞に発現させたmOR-EGは、cAMPおよびCa2+の両方のアッセイ系で、オイゲノールに曝され続けると応答強度が弱まることがわかりました。一方で、繰り返し刺激に対する応答性や、応答の減衰時間は、GRK3のあるなしで変化は見られませんでした。実際にin vivoの嗅神経細胞で検証したところ、GRK3があるときとノックアウトされて存在しないときでは、mOR-EGのオイゲノールの応答性には、ほとんど変化が見られませんでした。これらの結果は、嗅覚受容体の脱感作には、以前に考えられていたほどGRK3は関わっていないということを示しています。本研究は、いままでの定説に疑問を投げかけて、嗅覚受容体の脱感作のメカニズムについては振り出しに戻したということでは意義のあるものです。匂いに対する順応現象のメカニズムの解明には、まだまだ今後の研究を待つことになります。
●Kato, A., Reisert, J., Ihara, S., Yoshikawa, K., and Touhara, K.*
"Evaluation of the Role of G Protein-Coupled Receptor Kinase 3 in Desensitization of Mouse Odorant Receptors in a Mammalian Cell Line and in Olfactory Sensory Neurons"
Chemical Senses 39, 771-780 (2014) -
アフリカゾウはイヌの2倍、ヒトの5倍もの嗅覚受容体遺伝子を持つ —ゲノムの比較が明らかにした哺乳類の嗅覚受容体遺伝子の多様性— アフリカゾウは、これまでに報告されたどの動物よりも多い、約2000個(偽遺伝子を含めると約4300個)もの嗅覚受容体遺伝子(OR遺伝子)を持つことを見出しました。この数はイヌの2倍以上、ヒトの約5倍です。これまでに報告された中ではラットの約1200個が最多なので、ゾウは他の動物よりもはるかに多くのOR遺伝子を持っていることになります。これまでの研究で、ゾウは実際に鼻が良いことが示唆されています。アジアゾウを用いた行動実験によれば、アジアゾウは、ヒトを含む霊長類が識別できないような微妙な匂いの違いを嗅ぎ分けることができます。また、野生のアフリカゾウは、マサイとカンバというケニアに住む2つの民族集団を匂いで区別できるという報告もあります。マサイは槍を用いてアフリカゾウの狩りを行う風習があるのに対し、カンバは農耕民族なので、アフリカゾウはマサイを避けようとするのです。ゾウの鼻はだてに長いのではなく、その能力も非常に優れているといえます。
また、ゾウのOR遺伝子が非常に多いことを利用して、個々のOR遺伝子がたどってきた進化の道筋を明らかにするための新しいバイオインフォマティクスの手法を確立しました。この手法を用いて、アフリカゾウを含む13種の有胎盤類の持つOR遺伝子を同定・比較した結果、ほとんどのOR祖先遺伝子は少数の子孫遺伝子しか残していませんが、遺伝子重複を繰り返すことによって非常に多くの子孫遺伝子を残したOR祖先遺伝子も存在することが分かりました。また、有胎盤類の進化の過程において、遺伝子の重複や欠失がなく、しかも遺伝子配列もほとんど変化していないような、進化的に安定して維持されてきた特殊なOR遺伝子を3種類発見しました。それらのORは、匂い分子の受容という機能だけでなく、あらゆる有胎盤類に共通した重要な生理機能を担っていることが示唆されました。ある生物が持つOR遺伝子のレパートリーは、その生物が匂い情報を用いてどのように外界を認識しているかということを反映しています。今回のように、さまざまな生物種のOR遺伝子を進化的な視点から比較することで、ヒトの嗅覚に対する理解もより深まることが期待されます。
本研究成果は、時事通信、Yahooニュース、日経産業新聞、毎日新聞,東京新聞などだけでなく、ワシントンポスト、AFP通信、National Geographic, Discovery Channel, Livescienceなど多くのマスメディアに取り上げられました。
●Niimura, Y., Matsui, A., and Touhara, K.
"Extreme expansion of the olfactory receptor gene repertoire in African elephants and evolutionary dynamics of orthologous gene groups in 13 placental mammals"
Genome Research 24, 1485-1496 (2014) -
ムスクの香りを感知する受容体と脳領域の決定ー産業的に有用な新規ムスク系香料開発にヒントー 日常生活において、香りは生活の質を高める重要な要素のひとつとなっています。多々ある香りの成分の中でも、ムスク系香料は、香粧品に広く用いられる魅惑的な香気をもち、動物種を越えてフェロモン様の生理作用をもつという興味深い性質があります。しかし、ムスク系香料はどのような嗅覚受容体(センサータンパク質)で認識されて、脳のどの部分に情報が伝わるのか、生物学的に解明されていない点が多くありました。私達は、ムスク系香料の代表的な匂い物質、ムスコンが、一般的な匂いと比較すると極めて少数の嗅覚受容体で受容されること、また、ムスコンの匂い情報が、嗅覚の一次中枢である嗅球の限局された特定の領域に入力され、高次脳へと伝わることを明らかにしました。本研究で同定されたムスコンを認識するマウスおよびヒトの嗅覚受容体は、特定の構造を有するムスク香料のみを認識するので、産業的に有用な新規ムスク香料の開発につながると期待されます。
ムスクの香りは、有史以前からインドや中国において、薬や香油等に用いられてきました。この香りは、香調表現用語でMusky(ムスキー、動物臭、温かみがあり肉感的で艶っぽい香調)と表現され、他の香料にはない官能的な匂いを有するため、現代でも、フレグランスから洗剤に至るまで多くの香粧品に用いられています。もともとムスクは、ジャコウジカ、ジャコウネコなどの臭腺(香嚢(こうのう))を腹部から切除し、乾燥することにより得られてきました。ジャコウジカの雄は発情期になると、臭腺から出るこの匂いで自分のテリトリーを示し、雌を呼び寄せるといわれています。またムスクの香りは、ヒトに対して、性ホルモンの量の変化を誘発するなどの生理作用を持つという報告もあります。1926年に化学者レオポルト・ルジチカにより、ジャコウジカの分泌物の主要香気成分が大環状ケトン構造を有することが見出され、ムスコンと名付けられました。しかし、現在はジャコウジカの捕獲が禁止されているため、天然のムスコンは非常に希少となっています。また、工業的側面からみても、ムスコンは合成が非常に困難であったため、香粧品に用いるムスクの香りとして、ムスコンの香気を模した数百種類のムスク系香料が合成されています。
匂いを認識する嗅覚受容体(センサータンパク質)をコードする遺伝子は、マウスとヒトの染色体上に、それぞれ1063個と396個あることが知られています。この10年くらいで、ひとつひとつの嗅覚受容体がどの匂い物質を認識するかという研究が進み、受容体と匂い物質は複数対複数の組み合わせで認識されていることがわかっています。しかし、未だに、全体の数十%ほどの受容体の匂いリガンドが同定されているだけで、ムスコンの受容体は見つかっていませんでした。ムスコンは、産業的有用性をもつだけでなく、さまざまな動物で生理的作用をもち、特徴的な大環状化学構造をもつので、何個くらいの嗅覚受容体で、どのようなメカニズムで認識されて、脳のどの部分に情報が伝わるのか、生物学的にも大変興味がもたれていました。そこで、研究グループはムスコンの受容体を同定し、嗅覚神経系でのムスク系香料の情報処理メカニズムを解明することを目指しました。
まず、マウスを用いて、嗅覚一次中枢である嗅球上の、ムスコンに応答する糸球体を探索しました。既存の手法では測定不可能だった領域の匂い応答イメージング手法を確立したところ、内側前部の限局した領域の一部の糸球体のみがムスコンに応答すること(ムスコンの応答糸球体)がわかりました。また、免疫組織化学的手法を用いても、ムスコンの匂いに応答したことを示すシグナルが、同様の領域に見られました。さらに、その領域を外科的に除去したマウスはムスコンを感知できませんでした。つまり、ムスコンの匂い信号は、せいぜい数個の嗅覚受容体を介して脳に伝わって認知されていることを示しています。興味深いことに、ムスコンとは異なる構造を持つニトロムスク、多環式ムスク、大環状エステルも、ムスコンの応答糸球体とは異なるものの、嗅球内側前方の領域で受容されます。ムスク系の香り全体を象徴する動物的かつ官能的な香調は、嗅球の内側前部という特定の領域の活性化により生み出されている可能性があります。
次に、ムスコン応答糸球体に投射している嗅神経細胞に発現している嗅覚受容体を探索したところ、MOR215-1という受容体が見つかりました。実際に、MOR215-1を発現させたアフリカツメガエル卵母細胞やHEK293培養細胞はムスコンに応答を示しただけでなく、MOR215-1を発現する嗅神経が投射するマウスの糸球体もムスコン刺激に対して応答を示しました。また、MOR215-1のアミノ酸配列に類似したアミノ酸配列をもつヒトの受容体OR5AN1が、ヒトのムスコンの受容体であることも初めてわかりました。MOR215-1は、生分解性に優れていて産業界でも重用されている大環状ケトン構造を持つムスク香料のみを認識し、他のムスク系香料やアミン、アルコール、アルデヒド、酸、エステル、ラクトンなどの香料には応答を示しませんでした。MOR215-1受容体の匂い応答特性を利用した香料スクリーニング系を利用することで、産業的に有用なムスク系香料の新規開発につながると期待されます。
●Shirasu, M., Yoshikawa, K., Takai, Y., Nakashima, A., Takeuchi, H., Sakano, H., and Touhara, K.
"Olfactory receptor and neural pathway responsible for highly selective sensing of musk odors"
Neuron 81, 165-178 (2014) -
オスマウスの性行動を抑制する幼少フェロモンを発見 匂いやフェロモンといった化学感覚シグナルは、哺乳類の様々な行動や情動を制御しています。なかでも、尿、涙、唾液、汗などの外分泌液に含まれるフェロモンは、嗅覚神経回路を介して脳にその情報が伝わり、その結果、社会行動や性行動など、哺乳類にとって重要な行動が制御されます。例えば、マウスの尿からは、異性を引き付ける揮発性のフェロモン物質が発せられます。その他にも、オスマウスの涙にはESP1というメスマウスが背中をそらしてオスマウスの交尾を受入れやすくする体勢(交尾受け入れ行動)を促進するフェロモンが含まれています。フェロモンがあることによって、動物の様々な行動が健全に管理され、種の維持と存続が保証されます。
今回、私達は、性成熟する前の幼少メスマウスの涙に特異的に分泌されるタンパク質を発見しました。それは、ESPファミリーに属しているESP22という分子量約10 kDaのタンパク質で、生後2-3週令で分泌量が最大になり、性成熟する4週令になると急に減少しはじめ、大人になるとほとんど分泌されなくなります。この分泌の変化は、ESP22は「まだ性成熟していないよ」という幼少メスマウスからの信号であるという仮説を立て、マウスの行動を観察する実験と脳の情報処理機構を明らかにする実験とを行いました。
多様な系統のマウスを調べたところ、CBAとC3Hというマウスの系統ではESP22が分泌されていないことがわかりました。驚くべきことに、大人のオスマウスは、2-3週令のESP22を分泌する他のマウス系統(C57BL/6やBALB/c)のメスマウスに対してより、同じ週令のCBAやC3H系統のメスマウスに対して交尾行動(マウント)を3-5倍多くしかけることがわかりました。具体的には、大人のオスマウスはC57BL/6やBALB/c系統の幼少メスマウスには30分に5-15回の頻度でマウントをしかけたのに対して、CBAやC3H系統の幼少メスマウスに対しては30-40回ほどでした。一方、ESP22を分泌しないC3H系統の2-3週令の幼少メスマウスにESP22を塗ると、大人のオスマウスは全くマウントをしかけなくなりました。加えて、性成熟した大人のメスマウスにESP22を塗ると、塗らない場合と比べて、大人のオスマウスは3分の1程度しかマウントをしかけなくなりました。具体的には、大人のオスマウスは大人のメスマウスに対して通常30分に40回程度マウントをしかけるところ、ESP22を塗られた大人のメスマウスに対しては30分に15回程度まで減少しました。
次に、ESP22がどこで感知され、脳のどこで情報処理されているかを調べました。ESP1などのフェロモンは、鼻腔の下部の鋤鼻器という組織で感知されていることが知られています。そこで、鋤鼻器の機能を欠損した大人のオスマウスを用いたところ、ESP22による交尾行動の抑制は見られませんでした。また、ESP22を大人のオスマウスの鋤鼻神経に投与すると神経の活性化(電気信号)が見られました。さらに、そのESP22によって引き起こされる信号は、扁桃体という情動や本能的行動が制御される脳領域に入力されていました。つまり、ESP22はフェロモンを感知する鋤鼻神経系で情報処理されるということです。
これらの結果を総合すると、ESP22は、性成熟する前のメスマウスに交尾をしかけるような余計なことをしないように、大人のオスマウスの性行動を抑制する幼少フェロモンであることがわかりました。一方、ESP22 をコードするDNAの塩基配列は、ヒトゲノム上には存在せず、鋤鼻器もヒトでは機能しておらず、直接、ヒトへの応用に結びつくものではありません。本研究の成果は、マウスの行動がどのような化学感覚シグナルによって制御されているか、その理解を深めるもので、今後、哺乳類の情動や行動を支配・制御する脳神経回路の解明に向けて、有用な基礎研究基盤となるものです。また、倉庫や製造所などで問題になっているマウスの過剰繁殖の制御など、応用面への展開も期待されます。
この研究は、数年前に、ハーバード大学のSteve Liberles博士が、幼少期にでているESPを発見したと私達に共同研究を持ちかけてきたときが始まりで、その後、Marc Spehr博士のグループも巻き込んで、嗅覚分野の若手研究者らによって密接な共同研究をおこなった結果の成果です。その間、東原がハーバード訪問、Liberlesが東京大学を訪問をして、情報交換などをおこなってきました。
●Ferrero, D.M., Moeller, L.M., Osakada, T., Horio, N., Li, Q., Roy, D.S., Cichy, A., Spehr, M., Touhara, K., and Liberles, S.D.
"A juvenile mouse pheromone inhibits sexual behavior through the vomeronasal system"
Nature 502, 368-371 (2013) -
カイコ性フェロモン受容体の活性が環状ヌクレオチドで細胞外から制御されるという意外な事実を発見 私達の2008年のSato et al. Nature論文では、昆虫のにおい・フェロモン受容体は、Gタンパク質に共役する受容体ではなく、リガンド作動性カチオンチャネルであると結論付けています。ところが、Back-to-BackのWicher et al.論文では、受容体がチャネルという結論は同じものの、リガンド刺激によってGs-cAMP経路が作動して、それによって上昇したcAMPがチャネルを開くというメカニズムを主張しています。私達は、cAMPの上昇は全く見られないものの、確かに、弱いながらもcAMPアナログによって受容体のチャネルが開くことは確認できていました。そこで、本論文では更なる検証をおこないました。まず、cAMPアナログによる受容体の活性化は、細胞外からなのか細胞内からなのかを検証したところ、驚いたことに細胞外から作用していることがわかりました。これは明らかにWicher et al.の主張とは異なります。次に、活性が弱いので、もしかしたらアンタゴニスト活性があるかもしれないと仮説をたてて検証したところ、非競合的阻害の活性をもつことがわかりました。構造活性相関を調べたところ、cAMP, cGMPだけでなく、ATP, GTPにも活性がありました。しかし、興味深いことに、この阻害活性は、現在のところ、カイコ性フェロモン受容体でしか見られません。実は、15年ほどまえに、カイコ性フェロモンによる神経の活性化はcGMPアナログで阻害されるという報告がなされていますが、その現象を説明するメカニズムではないかと考えています。生理的な意味についてですが、フェロモン刺激を受けた触角内で環状ヌクレオチドの上昇が見られるという報告もありますが、今後の更なる研究が必要です。いずれにしても、環状ヌクレオチドによる昆虫の嗅覚受容体の活性化について、Wicher et al.論文の主張から更に異なる結論に至ったと考えています。
● Nakagawa, T. and Touhara, K.
"Extracellular modulation of the silkmoth sex pheromone receptor activity by cyclic nucleotides"
PLoS ONE 8(6), e63774 (2013) -
マウスの性行動を制御するペプチド性フェロモンの立体構造と受容体相互作用機構を解明 ESP1は、オスマウスの涙に分泌され、メスの性行動を促進させる、分子量約7 kDaのペプチド性のフェロモンです。本論文では、核磁気共鳴分光法を用いてESP1の立体構造を明らかにし、さらに、ESP1の受容体であるGタンパク質共役型受容体V2Rp5と相互作用する部位を明らかにしました。哺乳類のペプチド性フェロモンと受容体の構造的知見を提供するのは本研究が初めてです。
オスマウスの涙には、ESP1と名付けられた分子量約7 kDaのペプチドが分泌されています。メスがオスと直接接触すると、オスの顔や手についたESP1が、メスマウスの鋤鼻器官に取り込まれます。そして、ESP1によって鋤鼻神経が活性化すると、その情報は脳の扁桃体や視床下部に伝わって、メスは交尾受け入れ態勢であるロードシスという性行動をとります。ESP1があると、交尾の確率が3−4倍上昇することから、ESP1はマウスの繁殖に重要な性フェロモンと考えられています。
ESP1は、鋤鼻器官に発現する約300種類ほどの鋤鼻受容体のうち、V2Rp5という受容体一つによって感知されます。V2Rp5はN末端が長いグルタミン酸受容体と同じクラスCファミリーに属するGタンパク質共役型受容体であり、V2Rp5のノックアウトマウスではESP1によるロードシス行動が消失することから、ESP1とV2Rp5の相互作用は、ESP1が引き起こすロードシス行動に必要十分と考えられます。
本研究では、ESP1とV2Rp5の構造的知見を得るために、核磁気共鳴分光法(NMR)を用いて、ESP1の立体構造を明らかにし、さらに部位特異的変異解析によって、ESP1の配列のなかで、V2Rp5を活性化するのに重要なアミノ酸残基を同定しました。ESP1は、ひとつのジスルフィド結合と三つのヘリックスとからなる比較的コンパクトな構造をもち、マウス尿主要タンパク質MUPなどいままで知られていたフェロモン候補タンパク質の構造とは異なり、アメフラシや単細胞繊毛虫のフェロモンに似た構造をもつことがわかりました。さらに、表面が電荷に富んでおり、そのうち67番目のグルタミン酸に変異を導入すると、鋤鼻神経活性が顕著に減少したことから、E67がV2Rp5との相互作用に関わるアミノ酸であることが示唆されました。そこで、グルタミン酸受容体の立体構造をもとにV2Rp5のN末端領域のモデル構造を構築し、グローブの様な隙間にESP1を配置してドッキングシミュレーションしたところ、サイズと電荷の相互作用的に、結合部位として整合性のある結果が得られました。
本結果は、哺乳類におけるペプチド性フェロモンとその受容体の構造的知見としては初めてものであり、グルタミン酸受容体を含むクラスCのGタンパク質共役型受容体とペプチド性のリガンドとの相互作用に関して新たな情報を提供するものでもあります。また、ESP1の相同ペプチドがマウスゲノム上に38種類、ラットゲノム上に10種類存在します。このESPペプチドファミリーは、性行動や社会行動など様々な齧歯類の行動に関わっていることが推測されているので、本研究で明らかになったフェロモンー受容体相互作用の構造的知見は、ネズミの行動を制御する物質のスクリーニングや開発のきっかけになると期待されます。本研究は、熊本大学が構造解析、東京大学が機能解析を分担して共同でおこなわれたものであり、文科省ターゲットタンパク研究プログラム、文科省特定領域研究、JST ERATOの研究費サポートを受けて行われました。
● Yoshinaga, S.*, Sato, T.*, Hirakane, M., Esaki, K., Hamaguchi, T., Haga-Yamanaka, S., Tsunoda, M., Kimoto, H., Shimada, I., Touhara, K., and Terasawa, H. (* equal contribution)
"Structure of the mouse sex peptide pheromone ESP1 reveals a molecular basis for specific binding to the Class-C G-protein-coupled vomeronasal receptor"
J. Biol. Chem. April 10, 2013 Epub ahead of print (2013) -
メスマウスを誘うオスの尿臭として新規不飽和脂肪族アルコールの発見 私たちの鼻で匂いを感知している匂いセンサーは、嗅覚受容体と呼ばれるタンパク質です。嗅覚受容体は1991年にBuckとAxelによって一千種類にものぼる遺伝子群として発見され、90年代の終わりに実際に匂い物質と結合できることが証明されました。その後、それぞれの嗅覚受容体がどのような匂い物質を認識できるのかを調べるために、「合成香料レパートリー」の中からリガンド探索が行われてきました。その一方で、嗅覚受容体が実際に自然界でどのような情報物質を認識しているのかは良く分かっていませんでした。自然界で動物は、嗅覚を使って、えさや天敵、交配相手などの存在に関する情報を得ます。この過程において嗅覚受容体は重要な役割を担っているはずです。今回、マウスが他のマウスと出会ったときに嗅覚受容体で感じている新規の情報物質を同定しました。
マウスの個体から発せられる匂い物質の産生源として、尿、涙、唾液などの体液を作る7つの外分泌腺に着目しました。それぞれの外分泌腺に含まれる物質を抽出し、嗅覚受容体のひとつであるOlfr288(Olfactory receptor 288)を強制発現させたアフリカツメガエル卵母細胞に投与したところ、尿を作る外分泌腺である包皮腺の抽出物が電気応答を引き起こしました。この応答活性を指標に包皮腺から活性物質を精製し構造解析を行った結果、Olfr288のリガンドとして、哺乳類で新規の物質である(Z)-5- tetradecen-1-ol (Z5-14:OH) が同定されました。さらに解析を行った結果、Z5-14:OHは性ホルモンの制御を受けて雄マウスでのみ包皮腺から尿に分泌されることが分かりました。したがって、Z5-14:OHは雄という性の情報をもつ物質であると考えられました。実際に行動実験を行うと、雌マウスはZ5-14:OHを含む雄マウスの尿に嗜好性を示すことが明らかになりました。以上のことから、自然界で雌マウスがOlfr288を使って感じている情報物質、すなわちナチュラルリガンドの一つは、雄の尿から発せられるZ5-14:OHであるとわかりました。
本成果が導き出されるためのキーポイントとなったことは、多様な物質の複合物である生体試料から嗅覚受容体のリガンドを探索できる実験方法を確立したことです。その方法を用いて同定した天然のリガンド物質が、どのような生理的意味をもつかを明確にしました。今後、同じアプローチによって、嗅覚受容体だけでなく他の多くの化学感覚受容体についても、ナチュラルリガンドと対応づけることによって、自然条件下での役割が分かってくると期待されます。 Z5-14:OHはその化学構造から脂肪酸の代謝産物であると考えられます。我々ヒトの体臭も様々な脂肪酸代謝産物から構成されています。ヒト同士の嗅覚コミュニケーションにも、Z5-14:OHやそれに類似する物質が用いられているのかどうかは今後の興味深い課題です。本研究は、掲載号の News&Viewsで取り上げられました。また、ヤフーニュース、毎日新聞、ニュートン、雑誌「細胞工学」の論文の舞台裏コーナーなどのメディアでも取り上げられました。
卒業生の黒木さんが本論文を表すキュートな絵を書いてくれました。残念ながら雑誌の表紙のコンペでは不採用になってしまいましたが。。
● Yoshikawa, K., Nakagawa, H., Mori, N., Watanabe, H., and Touhara, K.*
"An unsaturated aliphatic alcohol as a natural ligand for a mouse odorant receptor"
Nature Chem. Biol. 9, 160-162 (2013)
● 吉川敬一、東原和成
"マウス嗅覚受容体のナチュラルリガンドの同定"
細胞工学 32, 586-587 (2013)
● 吉川敬一、東原和成
"哺乳類の行動を制御するエコロジカルボラタイルとその受容体の同定法"
アロマリサーチ 54, 180-184 (2013)
(吉川君は、2013年4月より花王に就職しました) -
昆虫における匂いやフェロモンの受容体シグナル伝達メカニズムをめぐる論争に決着 昆虫は、食物の匂いや同種の他個体から分泌されるフェロモンを、触角に存在する嗅覚受容体で感知します。近年、私たちは、昆虫嗅覚受容体は、匂いやフェロモンによって開くイオンチャネルであることを明らかにしました。しかし、昆虫嗅覚受容体がイオンを透過させる分子メカニズムに関しては2つの異なるモデルが提唱されており、これを解決することが重要課題のひとつとなっていました。今回、私たちは、昆虫嗅覚受容体複合体の両方のサブユニットが、イオン透過させるポア構造を作るのに貢献していることを示し、昆虫嗅覚受容体のチャネル機構をめぐる数年間の論争に決着をつけました。
昆虫は、匂いやフェロモンを、触角に存在する嗅神経細胞で受容します。嗅神経細胞には、数十種類の通常の嗅覚受容体(Olfactory receptor: OR)のうち一種類と、Orcoファミリー受容体(Olfactory receptor co-receptor)を共発現しており、これらはヘテロ複合体を形成して匂い・フェロモン受容体として機能します。近年、私たちは、昆虫嗅覚受容体複合体は、匂いやフェロモンによって直接活性化される陽イオンチャネルとして機能することを明らかにしました(Sato et al., Nature. 2008)。私たちと同時に、もうひとつの研究グループも、同様の結論の論文を発表しましたが(Wicher et al., Nature. 2008)、複合体がイオンを透過させる分子メカニズムに関しては、私たちが提唱するモデルと異なっていました。すなわち、私たちは昆虫嗅覚受容体複合体のポア構造(イオン透過路)は通常のORとOrcoの両方のサブユニットにより形成されると主張する一方で、Wicherらは、ポア構造がOrco側のサブユニットのみにより形成されると主張していました。
今回、私たちはこの議論に決着をつけることを目指し、昆虫嗅覚受容体複合体のイオン透過機構について詳細に解析しました。実際に解析する分子として、カイコガ性フェロモン受容体(BmOr-1)とカイコガOrco(BmOrco)の受容体複合体を用いました。一般に陽イオンチャネルのポアには、Glu, AspまたはTyrのアミノ酸が存在します。昆虫嗅覚受容体複合体も陽イオンチャネルであることから、複合体のポアにはGlu, AspまたはTyrが存在すると予想しました。そこで、BmOr-1とBmOrcoに存在するGlu, Asp, Tyr計83カ所の点変異体を作製して、アフリカツメガエル卵母細胞に発現させ、複合体のイオン透過能への影響を電気生理学的に解析しました。その結果、BmOr-1の2つのアミノ酸およびBmOrcoの1つのアミノ酸への点変異により、複合体のイオン透過能に影響が生じることを見出しました。また、これらの変異を導入したトランスジェニックハエを作製したところ、in vivoの嗅神経細胞でもチャネル活性に影響がおきていることを確認しました。昆虫嗅覚受容体複合体のポアは、通常のORとOrcoの両方のサブユニットで形成されているということが実証され、私たちが提唱していたモデルが正しいことがわかりました。
昆虫はゲノム上に60〜340個程度の嗅覚受容体遺伝子を有しているので、本研究の結論は、それと同じ数の種類のイオンチャネルが存在することを示しており、すなわち、昆虫嗅覚受容体が最大のイオンチャネルファミリーを形成していることを意味しています。今後、受容体複合体の結晶化によって、詳細な立体構造が解明されるのが待たれます。また、今回明らかになった機構を利用して、昆虫嗅覚受容体活性を制御する薬剤を開発すれば、マラリアやデング熱を媒介する蚊や、農作物を食いあらす害虫などを撹乱し、その被害を軽減することができます。本研究はそうした応用面へつながる重要な知見を提供するものです。
● Nakagawa, T., Pellegrino, M., Sato, K., Vosshall, L.B., and Touhara, K.*
"Amino acid residues contributing to function of the heteromeric insect olfactory receptor complex"
PLoS ONE 7, e32372 (2012)
(中川君は、2012年4月よりJTに就職しました) -
昆虫における果糖の味覚センサーを発見-新規の受容体チャネル・腸にも発現- 動物は、甘味、苦味、酸味、塩味、うまみなどの化学シグナルを、味細胞から高次脳中枢へシグナル伝達することで、食物の味を感じています。今回、私たちは、昆虫の味覚受容体候補遺伝子群のなかから、蜂蜜や果物に多く含まれる果糖(フルクトース)の受容体を発見しました。昆虫の味覚受容体候補タンパクが実際に味物質を認識するということをin vitroの再構成系で実証した初めての報告です。また、その受容体は果糖によって開くイオンチャネルであることを見出しました。これにより、昆虫は、味物質という化学シグナルを直接電気信号に変換するセンサーを使って、果糖を感知していることが明らかになりました。
食品の味は、口の内部に分布する様々な味細胞を介して知覚されます。これらの細胞には味覚受容体が分布しており、味物質と受容体が結合すると電気信号が発生し、そのシグナルが脳へと伝わることで味を感じます。私たち人間を含めた脊椎動物では、これまでに甘味、苦味、酸味、塩味、うまみの基本五味を感知する味覚受容体が見つかっており、味物質という化学シグナルがどのように電気信号へ変換されるのか、その全容はほぼ明らかにされています。一方で脊椎動物以外では、味を感じる仕組みはほとんど明らかにされていませんでした。近年、私たちの研究グループでは昆虫が匂いを感じる器官である触角に、匂い物質と結合すると細胞内にナトリウムやカルシウムを流入させる機能を持つイオンチャネル型の匂い受容体が存在することを明らかにしています(Sato et al., Nature (2008))。今回、私たちは、蜂蜜や果物に多く含まれる果糖(フルクトース)で活性化される味覚受容体を、カイコとショウジョウバエより発見し、この受容体が匂い受容体と同様に、イオンチャネルの機能を持つことを明らかにしました。
カイコの遺伝子データベースを利用してカイコの味細胞が分布する口から、幾つかの味覚受容体遺伝子候補を取り出しました。これらの遺伝子を一つずつ、アフリカツメガエルの卵母細胞に注入し、様々な味物質で刺激し、味を感じる神経細胞と同様に電気的な反応が生じるか測定しました。その結果、BmGr-9(Bombyx mori gustatory receptor-9)と名付けられた受容体が果糖に応答することを見出しました。ショウジョウバエがもつBmGr-9類似遺伝子も調べたところ、同様に果糖に対する味覚受容体であることがわかりました。この結果は、様々な昆虫に存在するBmGr-9の類似遺伝子が果糖に対する味覚受容体をコードしていることを示唆しています。次にBmGr-9が果糖という化学物質の信号をどのように電気信号へ変換しているのか、検討しました。そこで哺乳類の培養細胞にBmGr-9を導入すると、その細胞膜上には果糖で活性化されるイオンチャネルが合成されていることがわかりました。つまりBmGr-9そのものが、果糖で活性化されて開くイオンチャネルであることが明らかとなりました。また果糖と同じ分子式を持つブドウ糖などの他の糖類のいくつかは、BmGr-9と果糖の結合を阻害する作用を持つことも明らかになりました。
本研究で、昆虫が味を感じるメカニズムの一つとして、味物質で直接活性化されるイオンチャネルが化学シグナルを直接電気信号に変換していることが明らかになりました。昆虫が味シグナルを電気信号に変換する機構はこれまで全くわかっておらず、本研究により初めてその一端が明らかとなりました。特にこれまで昆虫では、味細胞内でGタンパク質を経由するなど様々な化学反応を経て電気信号へ変換される、と考えられていたので、果糖で活性化されるイオンチャネルの発見は定説を覆す驚くべき発見といえます。
果糖はブドウ糖や蔗糖とともに昆虫の摂食を促進する甘味物質です。また、BmGr-9は腸にも発現しており、消化器末梢系における栄養代謝状況をモニターしている可能性もあります。つまり、昆虫の摂食行動を調節する神経機構を解明する糸口にもなると期待されます。
また、清涼飲料などに多く含まれる果糖は、ブドウ糖よりも糖化タンパク質として結合しやすく、またインスリンやレプチン抵抗性を引き起こしやすいため、糖尿病合併症や内臓肥満を招く有力な原因の一つとして、近年、注目を集めている糖です。2010年には厚生労働省よりその過剰摂取への警告も出されました。BmGr-9は果糖のシグナルを高精度に電気信号に変換できるので、今後、尿や血液中の果糖の簡便な計測など糖尿病リスク評価への応用が期待されます。
● Sato, K., Tanaka, K., and Touhara, K.*
"Sugar-regulated cation channel formed by an insect gustatory receptor"
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108, 11680-11685 (2011)
(佐藤君は、2011年6月より東京大学生産技術研究所特任講師として栄転しました) -
世界最大級の花ショクダイオオコンニャクが放つ特異臭気成分を特定 サトイモ科のショクダイオオコンニャク(Amorphophallus titanum、別名スマトラオオコンニャク)は、インドネシアのスマトラ島に自生する世界最大の花(正確には、雄花と雌花の集合体)として知られています。世界でも開花例は極めて少なく、国内においても2010年7月22日に、小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)で、19年ぶり6例目の開花が確認され世間をにぎわしたことは記憶に新しいと思います。
ショクダイオオコンニャクはその奇異な見た目だけでなく、開花時に腐った肉のような強烈な臭気を放つことから、イギリスの王立園芸協会から、「世界で最も醜い花」にも選ばれております。ショクダイオオコンニャクが開花時に放つ臭気は、授粉を媒介する昆虫を引き寄せるといわれています。しかし、開花が稀であることから、この花が有する臭気に寄与する匂い成分の分析例はこれまでにほとんど報告されておりません。本研究では、2010年7月に本学小石川植物園で開花したショクダイオオコンニャクの花の匂いを、経時変化を追って観察、分析しました。
まず、ショクダイオオコンニャクの花の匂いを人間の鼻で評価しました。開花開始から1〜2時間の間は10〜20分間隔で周期的に腐った果物の様な香りがします。そして、開花開始から4時間後に花が完全開花しますと、中心部(花序付属体)が体温程度(約35-36度)の熱を帯びるのに合わせて、腐肉臭の様な臭気が最も強烈になることが分かりました。また、開花開始から8時間程すると、花序付属体から液体分泌物が出始め、腐肉臭の他に腐った魚のような匂いが加わります。
そこで、ショクダイオオコンニャクが完全開花し、臭気が最も強い時間帯の花の内部の空気を捕集し、匂い嗅ぎガスクロマトグラフ質量分析計を用いて、匂い成分の分析を行いました。その結果、完全開花時の臭気には、いくつかの短鎖脂肪酸や含硫黄物質が寄与していること、その中でも特に、腐った肉や野菜のにおいを呈する「ジメチルトリスルフィド」という含硫化合物が大きく寄与していることが示されました。興味深いことに、浸潤性の癌患部から放出される匂いと同じ成分でした(成果5:Shirasu et al. BBB 2009)。その後、8月に鹿児島フラワーパークでさいたショクダイオオコンニャクでも同じ結果が得られました。
また、匂いセンサー(FF-2A)を用いて、ショクダイオオコンニャクの放つ臭気を客観的に官能評価しました。すると、完全開花時のショクダイオオコンニャクの匂いは、匂い嗅ぎガスクロマトグラフ分析で臭気への寄与が強く示唆された「ジメチルトリスルフィド」や、浸潤性癌の患部が持つ臭気と非常に良く似たパターンを示すことが分かりました。
本研究では、人間の鼻と最先端の匂いセンサーを用いることにより、ショクダイオオコンニャクが開花時に放つ匂いの詳細な分析、人間が感じる臭気の原因成分の同定に、世界で初めて成功しました。今回同定された匂い成分がどのようなメカニズムで産生されるのかを調べることにより、未だ謎の多いショクダイオオコンニャクの生態が明らかになると期待されます。本成果は、朝日、毎日、日経の各新聞にとりあげられ、また時事通信、共同通信で配信されました。
● Shirasu, M., Fujioka, K., Kakishima, S., Nagai, S., Tomizawa, Y., Tsukaya, H., Murata, J., Manome, Y., and Touhara, K.*
"Chemical Identity of a Rotting Animal-like Odor Emitted from the inflorescence of the Titan Arum (Amorphophallus titanum)"
Biosci. Biotechnol. Biochem. 74, 2550-2554 (2010)
● 白須未香、東原和成
"世界最大級の花ショクダイオオコンニャクが放つ特異臭気成分の特定"
アロマリサーチ 47, 242-243 (2011) -
鼻粘液中での酵素反応が匂いの感覚に影響を与えることを発見 鼻腔内に入った匂い物質は、嗅粘液に溶け込み、嗅覚受容体に結合し、嗅神経細胞を活性化することで匂いとして知覚されます。つまり、嗅粘液への溶け込みは匂い受容の最初のステップであると言えます。近年、我々の研究グループは、いくつかの嗅覚受容体に関して、生体レベルでの匂い応答と培養細胞系での匂い応答を比較すると、応答特性に違いがあることを見出しました(Oka et al. Neuron 2006)。また、マウス生体において嗅粘液を除去すると、ある匂い物質に対する嗅神経細胞の応答強度が増大することから、嗅粘液が個体レベルでの匂い知覚に影響を与えることが示唆されていました。今回我々は、嗅粘液中の酵素が匂い物質を変換する現象を発見し、匂い応答への影響を嗅神経レベル、行動レベルで明らかにしました。
まず、マウス嗅粘液には、アルデヒドやアセチル基を持つ匂い物質を代謝する酵素活性があることを見出しました。また、マウスに匂いをかがせた後に嗅粘液を採取すると、酵素反応によって生成したと考えられる匂い物質が検出されました。したがって、吸気とともに鼻腔内に取り込まれた匂い物質が、嗅粘液中で酵素変換されることがin vivoで示されました。次に、嗅覚系の一次中枢である嗅球において、酵素反応の阻害剤処理前後で、匂いに応答した糸球体の分布パターンを比較しました。その結果、嗅粘液中で変換を受ける匂い物質に対する応答パターンは、阻害剤処理前後で異なりました。したがって、嗅粘液中の酵素反応は、匂い物質が嗅覚受容体に到達するよりも前に起きていることが示唆されました。最後に、変換を受ける匂い物質に対する知覚が、酵素反応の阻害剤処理前後で変化するか検証しました。マウスに匂いと報酬を対応づけて学習させた後、阻害剤処理を行った結果、マウスは嗅粘液中で酵素変換反応を受ける匂いを識別しにくくなることが明らかになりました。
本研究で、嗅粘液に溶け込んだ匂い物質の一部はすばやく酵素変換されており、この反応は活性化される嗅覚受容体の組み合わせと匂い知覚に影響を与えることがわかりました。匂いの種類によっては、その匂いを純粋に感じているのではなく、その匂いと酵素代謝物の混合物を感じているという驚くべき発見です。本来、嗅粘液内の酵素は、外界からやってきた匂いや有害物などを分解したり除去したりするために存在すると思われますが、その反応が早い故に、匂いの知覚にも影響をあたえていたのです。酵素の量は、年齢、性、人種、体調によって異なることもあるでしょうから、その違いによって匂いの感じ方にも違いがでる可能性もあります。つまり、今回の結果は、我々がとらえている匂いの世界の少なくとも一部が、嗅粘液というフィルターを通してつくられているという新しい知見を提唱しています。掲載日に、Science Newsにとりあげられました。またYahooニュースにも取り上げられました.
● Nagashima, A., and Touhara, K.*
"Enzymatic conversion of odorants in nasal mucus affects olfactory glomerular activation patterns and odor perception"
J. Neurosci. 30, 16391-16398 (2010)
● 永嶌鮎美、東原和成
"マウス嗅粘液中で起きる匂い物質変換反応は匂い知覚に影響を与える"
アロマリサーチ 45, 48-49 (2011) -
オスマウスの涙に分泌するESP1はメスの交尾受け入れ行動を増長させるペプチド性フェロモンである 我々は2005年にオスマウスの涙腺から性特異的に分泌される7kDaの新規ペプチドを発見しました(Kimoto et al. Nature 2005)。ESP1と名づけたこのペプチドは、フェロモンを感知する組織である鋤鼻器官の神経を刺激するので、オスフェロモンの候補と考えられましたが、どんな生理的効果をもつかは不明でした。そこで、ESP1が引き起こす行動あるいは生理的効果を見出すこと、そしてESP1の受容体を特定して、そのシグナルが脳のどこへ伝わるかを見出すこと、この2つの実験戦略を平行して走らせることによって、ESP1の機能の全貌解明を目指しました。行動実験に関しては麻布大学の菊水教授(当時、東大森裕司研助教)、受容体の解析で遺伝子改変マウスの作製には理研の吉原博士に協力を得ながら研究を推進しました。
まず、鋤鼻器官の基底部に発現するV2Rタイプの受容体に着目したところ、V2Rp5と名づけた鋤鼻受容体のみが、ESP1刺激でc-Fosの発現誘導がかかる鋤鼻神経にでていることがわかりました。そして、蛍光タグをつけてV2Rp5を強制発現させたマウスを作製して、c-Fos発現誘導とカルシウムイメージングの2つの実験系でV2Rp5がESP1の受容体であることを実証しました。さらに、ESP1-V2Rp5のシグナルは副嗅球へ、そして扁桃体や視床下部領域に性特異的に入力していることがわかりました。この結果はESP1が性行動を制御していることを強く支持するものでした。
ESP1を鋤鼻に取り込ませたメスマウスのオスに対する性行動を詳細に解析した結果、ロードシスと呼ばれる交尾受け入れ行動が顕著に増加していることがわかりました。ロードシスは、交尾の際にオスをより受け入れやすくするため、反射的に背中を反らすようメスに本能的にそなわっている体勢です。ロードシスが本当にESP1によるものかを検証するために、V2Rp5ノックアウトマウスを作製したところ、ESP1に対する鋤鼻神経での応答、副嗅球や高次脳でのc-Fos応答がすべて消えただけでなく、上昇したロードシス行動も綺麗に消失しました。オス涙に分泌されたESP1は、メスの鋤鼻に取り込まれてV2Rp5というひとつの受容体を介してロードシス行動を引き起こす性フェロモンである決定的な証拠を得ることができました。
さらに興味深いことに、研究室で何世代も交配されてきた近郊系のマウスのほとんどでESP1の分泌が見られないのに対して、野生由来のマウスでは、大量のESP1が分泌されていることがわかりました。小さなケージで飼われ続けたマウスではこのフェロモンの必要性が低下して、遺伝子に選択圧がかかって発現しなくなってしまったようです。遺伝子進化の早さと、性行動様式の世代を超えた変化の早さには驚くばかりです。ESP1をだすマウスは明らかに交尾効率が高いこともわかったので、ESP1は「マウスの繁殖効率をあげる物質」として特許を申請しています。また、動物の本能的な行動を左右する神経回路を解明するうえで、良いモデルシステムとなると期待されます。本成果は、NHKニュースで報道され、読売、日経、時事、朝日、京都、中日、西日本などの新聞に掲載、YahooニュースおよびSicence Now, Discover Channel Magagineでも取り上げられました.
● Haga, S., Hattori, T., Sato, T., Sato, K., Matsuda, S., Kobayakawa, R., Sakano, H., Yoshihara, Y., Kikusui, T., and Touhara, K.*
"The male mouse pheromone ESP1 enhances female sexual receptive behavior through a specific vomeronasal receptor"
Nature 466, 118-122 (2010)
● 𡌶紗智子、東原和成
"オスマウスの涙に分泌されるペプチドESP1のフェロモン作用機構の解明"
実験医学 28, 2643-2647 (2010)
● 𡌶紗智子、東原和成
"マウスのオスフェロモンESP1の受容機構の解明"
ライフサイエンス新着論文レビュー (2010)
● 𡌶紗智子、東原和成
"マウスオスフェロモンESP1の受容機構の解明"
アロマリサーチ 44, 334-335 (2010)
(𡌶さんは博士を取得した後、博士研究員として研究を継続したのち、現在、米国Stowers Instituteに留学中です) -
匂いをクンクンと嗅ぐ(スニッフィングする)ときの脳応答への影響を解析 私たちは以前、マウス嗅球の糸球体でのin vivoの匂い応答感度は、そこに発現する嗅覚受容体のin vitroでの感度よりも高いことを示しました(Oka et al. Neuron 2006)。その理由は、鼻腔内に入ってきた匂い分子が、効率よく嗅粘液に吸着して溶け込んでいるからだと予想されました。このプロセスで重要なのが、クンクンと嗅ぐ行動(スニッフィング)だと言われています。スニッフィングすると、鼻腔内にクンクンと空気を取り込む頻度と量が多くなり、匂いをより良く識別できるようになります。そこで、私たちはこのスニッフィングという行動が応答感度をあげるのに役立っているのではという仮説をたてました。鼻腔内へ入る匂いの頻度と流速をそれぞれ別個に制御できるシステムを組んで、発現受容体がわかっている糸球体での匂い応答を測定したところ、流速が感度に影響を与えることがわかりました。さらに、流速による感度の変化は、受容体の性質ではなく、匂い物質の化学的性質に依存していることがわかりました。すると、様々な匂い物質の混合臭の場合は、流速が早いときと遅いときとでは、嗅球の匂い地図が異なりました。以前に米国Wachowiakのグループが、自由行動下のマウスを使ってin vivoではスニッフィングによる感度上昇はおきないと報告しています。しかし、今回の私たちの報告は、閾値付近の薄い匂いの場合は、鼻により早いスピードで匂いを取り込むほうが感知するのに有利であること、そして、混合臭のときは、スニッフィングしているときとしていないときでは、感じる匂いの質が異なる可能性を示唆しています。私たちがクンクンと匂いを嗅ぐときに、脳レベルではどのように反応しているかということがだんだんわかってきました。
● Oka, Y., Takai, Y., and Touhara, K.*
"Nasal airflow rate affects the sensitivity and pattern of glomerular odorant responses in the mouse olfactory bulb"
J. Neurosci. 29, 12070-12078 (2009) -
皮膚に浸潤し潰瘍を形成する癌患部が発する悪臭物質のひとつを特定 疾病に伴う体臭の変化は古くから知られており、嗅覚で診断するということで「嗅診」ともいわれていました。最近では、「犬ががんを見つける」などということで、国内外で話題となっています。しかし、システマティックに物質レベルで匂いの変化を解析した研究はほとんどありません。様々な疾病と匂いの関係がいわれるなかでも、皮膚に浸潤し潰瘍を形成する進行癌の局所は、独特の悪臭を伴い、患者のQOLを著しく下げる要因のひとつとなっています。われわれは、国立がんセンターの長井先生と協力してこの悪臭の原因物質の同定を目指しました。乳癌および頭頸部癌の患部から匂いを採取し、匂い嗅ぎガスクロマトグラフ質量分析計を利用して、この悪臭の原因物質の同定をおこないました。その結果、悪臭の原因は、ジメチルトリスルフィドであることがわかりました。ジメチルトリスルフィドは、いわゆる「たくあん臭」「強いたまねぎ臭」とも表現できるような匂いで、キャベツやブロッコリーなどの野菜の過熱臭、微生物の代謝産物として知られる物質です。がん細胞自体から発生している匂いというよりか、微生物由来の可能性が高いですが、がん細胞と微生物の共生によってうまれている匂いである可能性もあります。今後、この匂いの発生源を特定することによって、癌患部からのジメチルトリスルフィドの発生を制御することができると期待されます。匂いで悩む患者さんのQOLを改善するための第一歩をふみだしたといえるでしょう。本成果は、日経産業新聞で取り上げられました.
● Shirasu, M., Nagai, S., Hayashi, R., Ochiai, A., and Touhara, K.*
"Dimethyl trisulfide as a characteristic odor associated with fungating cancer wounds"
Biosci. Biotechnol. Biochem. 73, 2117-2120 (2009)
● 白須未香、東原和成
"進行ガンの患部が発する悪臭物質の同定"
アロマリサーチ 40, 47 (2009) -
桑の葉から放出されるカイコを誘引する香りとそれを感知する受容体センサーを発見 カイコは、絹生産に欠かせないものであるとともに、日本人にとっても親しみ深い身近な昆虫のひとつです。養蚕産業にとっての重要性から、カイコの摂食行動についての研究は古くからなされてきました。20世紀の中頃には、カイコがなぜ桑を食べるのかということで、桑の葉から発する揮発性のカイコ誘引物質、カイコが好む味物質、カイコが食べ続けるための因子などの探索がなされました。その結果、カイコを誘引するいくつかの匂い物質が報告されています。今回、私たちは、日中共同プロジェクトでカイコゲノムの解読が終了したことをうけて、カイコが桑の葉の香りに引き寄せられるときに働く嗅覚受容体(匂いのセンサータンパク質)を同定することを目指しました。私たちが興味をもったのは、以下の点です。カイコは、桑の葉からでる単一の香りに引き寄せられているのか?それとも複数の香りの組み合わせを感じているのか?そして、それらの香りを単一の嗅覚受容体で認識しているのか?それとも複数の受容体の組み合わせを信号として感知しているのか?
まず、ガスクロ・質量分析計による匂い分析とカイコの誘引行動アッセイをおこなったところ、桑の葉から微量に放出されているシスジャスモンという香りに強力な誘引活性があることがわかりました。次に、シスジャスモンを感知する嗅覚受容体の探索をおこなった結果、カイコゲノムの66個の嗅覚受容体遺伝子のうちひとつの嗅覚受容体(BmOr56と命名)がシスジャスモンに対して高感度かつ特異的応答を示しました。BmOr56の構造活性相関と誘引活性の強さは完全に一致しました。この結果は、カイコが桑の葉に対して誘引行動をひきおこすのに重要なのは、シスジャスモンとBmOr56の結合であり、すなわち、カイコの場合は、単一の香り物質と単一の嗅覚受容体が、桑の葉への誘引行動に関わっている可能性を示唆しています。
もともと、シスジャスモンは、ジャスミンの花の一成分として見つかりました。シスジャスモン自体もジャスミン様の香りを呈します。一方で、シスジャスモンは、植物ホルモンのジャスモン酸由来の物質ですので、多くの植物に共通の物質と考えられますが、実際に、葉からシスジャスモンを発しているという報告は少なく、害虫に食害されたタバコとか綿の葉からでるという報告程度です。私たちもいくつかの種類の葉をためしてみましたが、ヘッドスペース(葉から自然に空間に発せられる匂い)にはシスジャスモンは検出されませんでした。養蚕の歴史の過程で、なんらかの理由でカイコが好きな匂いになったということを示唆しています。クワコのような野生に近い種でどうなのかが興味深いところです。
カイコの桑の葉への誘引行動はもう理解できていると信じられていましたが、過去に報告されていた誘引候補物質は、誘引活性も弱く、受容体レベルでも行動との相関は見出せませんでした。そして、今回、シスジャスモンという単一の匂い物質に強力な誘引活性を示し、その誘引活性は、BmOr56という単一嗅覚受容体レベルで見事に相関がでました。近年の分子生物学の進展に伴い、カイコの桑の葉への匂い誘引行動を、分子レベル、センサーレベル、そして脳神経レベルで理解するための第一歩を踏み出すことができた成果といえると思います。そして、応用面として、このような研究の方向性は、カイコの生産向上にも役立つ可能性があります。また、カイコだけでなく、作物生産にとって害虫となるような食草性の昆虫が、ホスト植物のどんな匂いに誘引されるか、そしてその匂いを感知する受容体を明らかにすることができれば、その機能をブロックすることによって、害虫の行動制御をすることができると期待されます。本成果は、朝日新聞に掲載されました。
● Tanaka, K., Uda, Y., Ono, Y., Nakagawa, T., Suwa, M., Yamaoka, R., and Touhara, K.*
"Highly selective tuning of a silkworm olfactory receptor to a key mulberry leaf volatile"
Current Biology 19, 881-890 (2009)
● 田中佳奈、東原和成
"カイコを誘引する桑の葉の匂い物質およびそれを認識する嗅覚受容体を特定"
細胞工学 28, 828-829 (2009)
● 田中佳奈、東原和成
"カイコを惹きつける桑の葉の香り"
未来材料 11, 6-9 (2011)
(田中さんは修士号を取得した後、就職し、ラボマネージャーとして一時もどりましたが、再就職しました。) -
嗅覚受容体のより効率の良いアッセイ系の確立 近年、嗅覚受容体を培養細胞などで機能発現させるためのシャペロン分子が見つかり、嗅覚受容体と匂い分子との対応付けが飛躍的に進んできました (Saito et al. Cell 2005)。しかし、嗅覚受容体はGタンパク質との共役効率が悪いことから、未だに多くの嗅覚受容体で効率よく匂いの応答を検出することが困難でした。最近、Gタンパク質Galpha-s, Galpha-olfのguanine nucleotide-exchange factorであるRic-8Bが嗅覚受容体のcAMP応答を飛躍的に上昇させることが報告されました (Von Dnnecker et al. PNAS 2006)。そこで私たちはカルシウムイメージング系でも効率をあげるために、ミリストイル化したRic-8Aに着目し(Nishimura et al. Genes Cells 2006)、Galpha-15を介した嗅覚受容体のカルシウムアッセイ系に導入した結果、とても効率のよい応答を得ることができました。このアッセイ系を用いて、私たちは新たにリガンド未同定だった嗅覚受容体の機能解析に成功しました。新たに開発した本アッセイ系は、オーファン嗅覚受容体の匂い応答解析、鼻以外に発現している嗅覚受容体のリガンド同定などに応用できると期待される画期的な方法です。
● Yoshikawa, K., and Touhara, K.*
"Myr-Ric8A enhances Gα15-mediated Ca2+ response of vertebrate olfactory receptors"
Chem. Senses 34, 15-23 (2009)
● 吉川敬一、東原和成
"嗅覚受容体ー匂いやフェロモンの感知"
医学のあゆみ 233, 870-874 (2010)
● Touhara K.
"Deorphanizing vertebrate olfactory receptors: recent advances in odorant response assays"
Neurochemistry Internatl. 51, 132-139 (2007) -
嗅覚受容体のGタンパク質共役部位の同定と活性型受容体への構造変化に関わる部位の発見 嗅覚受容体と匂い物質の対応付けは進んできていますが、一方で、匂いが結合した嗅覚受容体がどのような構造変化をおこし、その結果、どのような分子メカニズムでGタンパク質を活性化するかという嗅覚受容体の構造ダイナミクスについての解明は遅れています。私たちは、部位特異的変異導入法を用いた生化学的解析をすることによって、嗅覚受容体の活性型への構造変化およびGタンパク質との相互作用に関わるアミノ酸の同定をめざしました。その結果、C末端にあるヘリックスと第三細胞内ループの一部がGタンパク質との共役に関わっていることがわかりました。また興味深いことに、第六膜貫通ヘリックスにあるKAFSTCという嗅覚受容体で保存されているモチーフ中のSerに変異をいれると、活性が高いハイパーアクティブな嗅覚受容体になることがわかりました。すなわち、第六膜貫通部位の構造変化が嗅覚受容体の活性化に重要であることを示唆しています。本研究は、嗅覚受容体が活性型へ変化してGタンパク質を活性化する際の構造動態の一端を初めて明らかにしたものであります。多くのGタンパク質共役型受容体は創薬のターゲットにもなっていることから、今回得られた結果は、製薬業界でも役立つ知見であると思われます。
●Kato, A., Katada, S., and Touhara, K.*
"Amino acids involved in conformational dynamics and G-protein coupling of an odorant receptor: targeting gain-of-function mutation"
J. Neurochem. 107, 1261-1270 (2008)
● Kato, A., and Touhara, K.*
"Mammalian olfactory receptors: pharmacology, G protein-coupling and desensitization"
Cell. Mol. Life Sci. 66, 3743-3753 (2009)
● 加藤綾、東原和成
"匂いを感じ取るセンサーとしての嗅覚受容体"
ファルマシア 43, 417-421 (2007)
(加藤さんは博士号を取得した後、花王に就職しました。) -
昆虫の嗅覚受容体(匂い、フェロモン)はヘテロ複合体でリガンド作動性イオンチャネルだった ヒトなど哺乳類で、匂いや香りを感知する嗅覚受容体は、細胞膜を7回貫通している構造をもつタンパク質で、細胞内メッセンジャー分子を介したシグナル経路を活性化することが知られていました。今回、昆虫の嗅覚センサーは、7回膜貫通型の構造をとっているものの、哺乳類と違い、ヘテロな複合体を形成し、その複合体が、匂いや香りを感知する機能とイオンを透過させて膜電位差を生み出すチャネル機能の両方の機能をもつという、全く新しいタイプの感覚センサーであることを発見しました。今回見出したセンサー機能をターゲットにすれば、マラリア蚊などの有害昆虫を撹乱させる薬剤などの開発ができると期待されます。また、昆虫の嗅覚センサーは、細胞内因子やエネルギーを必要としないことがわかったので、この機能を使えば、セルフリーの匂いバイオセンサーの開発も可能と考えられます。さらに、7回膜貫通型の受容体は、創薬の半数近くの標的となっている重要なタンパク質ファミリーであるので、今回のような7回膜貫通型受容体の新規機能の発見は、製薬業界にも大きな影響を与えるでしょう。
私たちは下記成果7で昆虫の嗅覚受容体は「atypical signal transduction」機構をもっていると最後ににおわせるような結論で締めくくっています。つまり、この時点で私たちは,昆虫の嗅覚受容体はリガンド作動性のチャネルなのではという仮説をたてて、実験を積み重ねてきました。その後、ロックフェラー大学のVosshall博士の協力を得て、論文発表にいたっています。実は今回、ヨーロッパのBill HanssonのグループとのBack-to-backの論文となっていますが、彼らの結論は私たちの結論と若干異なります。私たちは、Gタンパク質を介さないイオノトロピック型のイオンチャネル活性を見出していますが,彼らはGタンパク質Gsを介したcAMP経路が動き、生じたcAMPによって受容体チャネルが開くと結論しています。私たちもcyclic nucleotideによるチャネル開口活性は検出していますが、リガンド刺激によるcAMPの上昇は検出できていません。実際、彼らも明確なGs/cAMPの上昇は検出できていないこと、また、cAMPによって開口するチャネル活性が見えるのは時間的にとても遅いことなどを考えると、今後の更なる検証実験が答えをだしてくれるでしょう。いずれにしても、7回膜貫通型の嗅覚受容体がヘテロな複合体を組んで、そのもの自身がリガンド作動性のチャネルになっているという事実は,新規知見であり、基礎学術的にとても興味深いものだと思います。4月24日の論文掲載号にはNews&Viewとしてとりあげられ、5月30日号のCell誌でもPreviewとしてとりあげられました。
● Sato, K., Pellegrino, M., Nakagawa, T., Nakagawa, T., Vosshall, L.B., and Touhara, K.*
"Insect olfactory receptors are heteromeric ligand-gated ion channels"
Nature 452, 1002-1006 (2008)
● 佐藤幸治、東原和成
"昆虫嗅覚受容体は匂いに活性化されるイオンチャネルである"
実験医学 26, 2101-2104 (2008)
● 佐藤幸治、東原和成
"イオンチャネルとして機能する昆虫の匂い受容体"
蛋白質・核酸・酵素 53, 1968-1975 (2008) -
外分泌ESPペプチドファミリーは性・系統で差があり鋤鼻神経のリガンドとなる 以前、私たちはオスマウスの涙腺から7 kDaほどのペプチドが分泌され、そのペプチドESP1はメスの鋤鼻器官にとりこまれて鋤鼻神経を活性化することを見出しました (Kimoto et al. Nature 2005)。「男の涙からフェロモン」と話題になりましたが、残念ながら人間のゲノムからはなくなっていました。今回、私たちは、様々な生物でESPペプチドファミリーを探索した結果、マウスで計38個、ラットで計10個のESPファミリーペプチドを見つけました。げっ歯類にのみで見つかったので、ESPファミリーはとても早い速度で分子進化している遺伝子群だと考えられます。マウスのESP38個のなかには、メスにだけでているESPを見つけ、ESP36と命名しました。オス特異的なESP1とメス特異的なESP36は、両方とも、男性ホルモンであるテストステロンによって発現制御されており、思春期以降に性差が確立されることがわかりました。ところが、この発現パターンは系統によって差があり、系統によってはESP1が発現していないもの、ESP36がオスにもでているものなどがあることわかり、ESPファミリーは性差があるだけでなく、系統差もあることが判明しました。もともと系統はある一個体の野生マウスから確立されたものなので、系統差は個体差でもあります。今後、野生マウスでどうなっているのかが興味深いところです。
さらに、マウスESPファミリーの発現解析をおこなったところ、15種類のESPが外分泌腺で発現していました。これらのペプチドをすべて大腸菌で作り、鋤鼻器官での応答をみたところ、すべてに電気応答を引き起こす活性があることがわかりました。さらにTim Holyのグループとの共同研究で、単一鋤鼻神経軸索での応答解析をしたところ、鋤鼻神経のESP受容体の選択性は高いことが示されました。ESPペプチドは、鋤鼻器官のフェロモン受容体のリガンドレパートリーのひとつを形成している可能性が強いです。この論文は、ESPファミリーという多重遺伝子ファミリーの分子進化解析、発現解析、そして鋤鼻での機能解析を詳細に解析した最初の論文です。
● Kimoto, H., Sato, K., Nodari, F., Haga, S., Holy, T., and Touhara, K.*
"Sex- and strain-specific expression and vomeronasal activity of mouse ESP family peptides"
Current Biology 17, 18879-1884 (2007) -
嗅覚受容体からの匂い信号を嗅覚一次中枢の嗅球において可視化
ーin vivoとin vitroの匂い応答性の違いを受容体レベルで検証ー生物は匂いを鼻でとても敏感に感じることができます。その感度はppbからpptのレベルといった高感受性をしめします。匂いを感知するメカニズムは、嗅覚受容体の発見と機能解析によって決着がついたかに考えられていますが、実際に、in vitroで嗅覚受容体の匂い応答アッセイをしてみると、せいぜいマイクロM (ppm)レベルの感度で、生体の感受性には千倍ちかくの差がありました。この矛盾が何から生まれるのか検証するために、嗅覚の脳一次中枢である嗅球での生理的な匂い応答と、培養細胞で再構築した受容体の匂い応答を比較測定できる新手法を開発しました。具体的には、嗅球においてカルシウムイメージングによって匂い応答糸球体を同定し、そこからレトログレードに蛍光色素を神経に導入して、単一細胞RT-PCRの手法を組み合わせることによって、生理的条件下で嗅覚受容体と匂いの対応付けをおこないました。すると、同じ嗅覚受容体に対して、生理的な条件での匂い応答は、in vitroでの嗅神経細胞レベルでの応答より、千倍もの感度を示しただけでなく、反応する匂いの種類の選択性もより高いことがわかりました。また、鼻の嗅上皮を覆っている鼻粘液という薄い液層を洗い流して測定をしたところ、反応しなかった匂いに対する糸球体の反応が復活するなど、匂い応答性が変化しました。
これまでは匂いの信号伝達には嗅覚受容体を介した情報伝達と神経回路における発火シグナルだけが重要と考えられていましたが、今回の結果は、粘液層があるかないかで匂いの感じ方が変化するということを示しています。また、嗅球において、各々の匂いに特徴的な「匂い地図」ができることが知られていましたが、嗅覚受容体レベルでその地図を詳細に調べたところ、個体差があるだけでなく、左鼻と右鼻の左右差もあることがわかりました。今回の成果は、嗅覚一次中枢における匂い応答を受容体レベルで解析をした初めての研究であるだけでなく、鼻粘液の匂い制御あるいは修飾部位としての重要性をはじめて実験的に実証した研究です。
● Oka, Y., Katada, S., Omura, M., Suwa, M., Yoshihara, Y. and Touhara, K.*
"Odorant receptor map in the mouse olfactory bulb: in vivo sensitivity and specificity of receptor-defined glomeruli"
Neuron52, 857-869 (2006)
● 岡勇輝、東原和成
"生理的条件下での嗅覚受容体の匂い応答特性"
細胞工学 26, 190-191 (2007)
● 岡勇輝、東原和成
"嗅球での匂い応答を指標とした新規嗅覚受容体同定法"
アロマリサーチ 29, 40-41 (2007)
(岡君は博士号を取得し、当研究室での半年のポスドク後、現在、Columbia Univ.のZuker研のポスドクとして留学中です) -
精子細胞には複数の嗅覚受容体遺伝子が発現していて核内局在という興味深い発現様式を示す 先の論文(Fukuda et al. J. Cell Sci. 2004)で、マウス精子に発現する嗅覚受容体MOR23がリガンドを認識すると。精子内カルシウムイオンの上昇が引き起こされ、その結果、精子の運動性が制御されることを示しました。それでは、精巣にはどのくらいの種類の嗅覚受容体遺伝子が発現しているのでしょうか?また、ひとつひとつの精子細胞には何種類の嗅覚受容体を発現しているのでしょうか?精子形成段階のどのステージに発現がみられるのでしょうか?そこで、縮重プライマーを用いてmRNAに転写されている嗅覚受容体遺伝子をRT-PCR法で解析し、in situ hybridizationで発現を確認したところ、せいぜい10個程度の嗅覚受容体遺伝子が発現していることがわかりました。RT-PCRで増幅された嗅覚受容体の多くはin situでは検出されなかったことから、ある程度の量を発現している嗅覚受容体は、いままで報告されていた数(50-100個)よりもずっと少ないことがわかりました。嗅覚受容体の精巣における発現をin situで明確に示した初めての報告です。
次に、精子形成段階のどのステージで発現しているか調べたところ、すべての受容体がすべてのステージに発現しているのではなく、前期、中期、後期の3つのステージのいずれかに発現がみられることがわかりました。それぞれの嗅覚受容体遺伝子の発現がステージごとで制御されていることが示唆されます。また、二重染色in situを行ったところ、ひとつの精細胞に複数の嗅覚受容体mRNAが検出されました。鼻の嗅細胞とは異なり、個々の細胞で複数の嗅覚受容体遺伝子の転写がおきていることがわかりました。さらに興味深いことに、嗅覚受容体mRNAは、細胞質ではなく、核内に凝集されて局在することがわかりました。
以上、本論文では以下の興味深い新規知見を報告しています。1)以前から曖昧だった精巣における嗅覚受容体遺伝子の発現をin situレベルで明確に示したこと、2)各々の嗅覚受容体遺伝子の発現時期に違いがみられること、3)個々の精子細胞に複数の嗅覚受容体遺伝子の発現がみられること、4)嗅覚受容体mRNAは核内に凝集していること。今後、これらの嗅覚受容体がMOR23受容体のようにタンパク質に翻訳されて機能しているかどうかを調べ、精子形成のおける嗅覚受容体の機能を解明する必要があります。また、これら嗅覚受容体の内在性リガンドの同定も今後の課題です。
● Fukuda, N., and Touhara, K.*
"Developmental expression patterns of testicular olfactory receptor genes during mouse spermatogenesis"
Genes to Cells 11, 71-81 (2006)
● 福田七穂、仲川喬雄、東原和成
"嗅覚研究からわかった7回膜貫通型タンパク質の新規機能"
細胞工学 24, 492-493 (2005)
(福田さんは博士号を取得し、理研御子柴研のポスドク三年間後、現在スウェーデンのカロリンスカ研究所に留学中です。) -
マウスのオス特異的なフェロモンは涙にでていた!しかも新規ペプチド! フェロモンはカイコのボンビコールなど特定の行動を誘発するリリーサーフェロモンと生理的影響を与えるプライマーフェロモンに大別されます。プライマーフェロモンは、発情促進、妊娠阻害、性周期同調などの効果を引き起こし、マウスなど齧歯類でよく知られている現象です。マウスでは、フェロモンは鼻腔下部にある鋤鼻器官(じょびきかん)というところで感知されます。今まで、フェロモン候補として尿由来の低分子有機化合物やペプチド性物質がいくつか単離されていましたが、いずれも自由に行動しているマウスの鋤鼻器官で感知されるという実証はありませんでした。
私達は実際に鋤鼻器官で感知されている物質を探索するために、鋤鼻神経における遺伝子発現誘導を指標としたアッセイ系を確立しました。マウスを飼っている床敷きに性特異的な活性がみられたので、活性の出所を探しました。最初は尿から分泌されていると予測しましたが、なんと、涙腺や顎下腺など顔周辺の外分泌腺に活性が認められました。そこで、活性物質を涙腺から単離、精製、構造決定をしたところ、約7kDaの分子量をもつペプチド性の物質であることがわかりました。このタンパク質をコードしている遺伝子は、数十種類からなる新規の多重遺伝子ファミリーのひとつであることが判明しました。外分泌腺からでてくるペプチドなので、ESP1 (excrine gland-secreted peptide)と命名しました。
興味深いことに、ESP遺伝子ファミリーは、第17番染色体の主要組織適合性複合体(MHC)遺伝子群のすぐ隣に位置していました。MHCの違いが個体の匂いの違いを生み出しているという知見ともリンクして面白いと思っています。また、ゲノムプロジェクトが進み網羅的遺伝子の解析が盛んに行われている現代で、新規遺伝子しかも多重遺伝子ファミリーがまだ見つかったという事実は、今回のような現象を見極めた王道的な活性物質や遺伝子の「ものとり」の研究の重要性を再認識させます。
ESP1は、オス特異的に涙腺で作られ、目から外へ分泌され、メスの鋤鼻器官にとりこまれて、鋤鼻神経の電気的応答を引き起こします。 活性化される鋤鼻神経には、ある特定のV2Rタイプのフェロモン受容体が発現しているので、 ESP1の受容体はV2Rタイプであると考えられます。ESP1はペプチド性で不揮発性ですので、オスとメスが直接接触することによって鋤鼻器官にとりこまれます。確かによく観察すると、マウスは顔をくっつけあってコミュニケーションをとっている様子が見れると思います。ESP1は、赤ちゃんや子供のオスはだしていなく、思春期以降の大人のオスがだしています。そしてメスがオスのシグナルとして認識するものなので、性識別や性行動に関わる性フェロモンであると思われます(Haga et al. Nature 2010で実証)。また、オス特異的に発現する遺伝子なので、性決定と内分泌の関連を理解するうえでも貴重な発見です。
さて、ESPとかエスパーという言葉はどっかで聞いたことがあるひとがいると思いますが、ESPはextrasensory perception(超感覚的知覚)の略でもあります。フェロモンはどこか超感覚的な第六感的な現象でもあります。私達はその神秘の全面解明に少しづつ近づいているのかもしれません。今後、ESP1がメスに対してどんなフェロモン効果をもたらすかを解明するのが課題です。
● Kimoto, H., Haga, S., Sato, K., and Touhara, K.*
"Sex-specific peptides from exocrine glands stimulate mouse vomeronasal sensory neurons"
Nature 437, 898-901 (2005)
● Kimoto, H., and Touhara, K.*
"Induction of c-Fos expression in mouse vomeronasal neurons by sex-specific non-volatile pheromone(s)"
Chem. Senses 30 (suppl 1), i146-i147 (2005)
● 木本裕子、東原和成
"マウスの涙腺から分泌されるオス特異的ペプチド:涙にフェロモン?"
実験医学 23, 2935-2937 (2005)
● 木本裕子、東原和成
"マウスの鋤鼻器官で受容されるオス特異的ペプチド"
アロマリサーチ 7, 78-83 (2006)
● 東原和成
"性フェロモンを介した空間コミュニケーションと生物進化"
現代化学 417, 56-60 (2005)
● 東原和成
"雄マウスの涙腺から分泌されるペプチド性フェロモン:ゲノムに埋もれていた多重遺伝子ファミリーの発見"
化学と生物 44, 218-220 (2006)
● 東原和成
"性フェロモンと進化:嗅覚コミュニケーションの多様性"
細胞工学 25, 393-397 (2006)
(木本さんは博士号を取得した後、当研究室でのポスドク1年後、第一三共製薬に就職しました。) -
嗅覚受容体の匂い結合部位の同定:匂いセンサー機能の構造的知見 匂い分子はどのようにしてキャッチされるのでしょうか?約半世紀ほど前、この疑問に対して、立体構造説・分子振動説・膜吸着説など、いくつかの説が提唱されました。その後、1991年の嗅覚受容体候補遺伝子の発見、そして、1998−1999年にかけての受容体による匂い応答の実証研究をとおして、立体構造説が有力となりました。しかし、匂い分子が結合する部位が同定されていなかったため、匂いがどのようにして受容体によって認識されるか、その分子メカニズムは不明でした。コンピュータシミュレーションをつかった結合部位予測はされていたものの、実験的な実証はされていませんでした。我々は、今回、計算機的手法と実証実験を組み合わせて、はじめて、哺乳類嗅覚受容体の匂い結合部位を決定しました。3番目、5番目、6番目の膜貫通へリックスによって、匂い分子がはまるポケットが形成されています。そのポケットで匂い分子認識に関わるアミノ酸のほとんどが疎水性であることは、嗅覚受容体が他のGPCRと比べてリガンドへの親和性が低いことを説明してます。一方で、複数のアミノ酸によって作られている結合空間は、匂いリガンドの高選択性を生み出しています。嗅覚受容体の「広範囲にわたる高選択的リガンドスペクトル」の分子基盤が明らかになったわけです。本研究のハイライトは、匂い結合部位内のアミノ酸を操作することによって、匂い分子に対する特異性を思うように変化させることができたことです。嗅覚受容体は、進化の過程で、結合部位を少しづつ変化させることによって多様な匂い物質に対応できるように多重遺伝子化してきたということを支持する結果であるとともに、新規の嗅覚受容体のデザインや、匂い物質のデザインへ応用ができる概念でもあります。
● Katada, S., Hirokawa, T., Oka, Y., Suwa, M., and Touhara, K.*
"Structural basis for a broad but selective ligand spectrum of a mouse olfactory receptor: mapping the odorant binding site"
J. Neurosci. 25, 1806-1815 (2005)
● Katada, S., Hirokawa, T., and Touhara, K.*
"Exploring the odorant binding site of a G-protein-coupled olfactory receptor"
Current Computer-Aided Drug Design 4, 123-131 (2008)
● 堅田明子、東原和成
"匂い認識の分子基盤:嗅覚受容体の薬理学的研究"
日本薬理学雑誌 124, 201-209 (2004)
● 堅田明子、東原和成
"嗅覚における匂い認識の分子基盤"
Aroma Research 4, 78-83 (2003)
(堅田さんは博士号を取得し、学振員として理研吉原研で1年半後、現在、UC IrvineのSassone-Corsi研のポスドクとして留学中です) -
昆虫における匂いやフェロモンの受容メカニズムの全貌解明 昆虫は数キロも離れた自分の交尾相手を化学シグナルによって見つけますが、その感度と選択能力の高さは、生物界における究極の化学センサーと言われていました。先の論文(PNAS 2004)で、カイコガのボンビコール受容体を報告しましたが、その高感度かつ高選択性がうみだされる仕組みは不明でした。このたび、その高感度、高選択性を生み出すメカニズムを解明しました。ハエや蛾など多くの昆虫において特に保存されている嗅覚受容体BmOR2に着目した結果、フェロモン受容体とBmOR2は同じ神経に共発現していることがわかりました。そこで、フェロモン受容体とBmOR2を一緒にアフリカツメカエル卵母細胞に発現させたところ、フェロモンに対する感度が数百倍あがり、また、効率よく電気信号に変換されることがわかりました。この電気信号は、既存のGタンパク質共役型受容体から生じるものとは全く異なっており、新規の情報伝達経路であると思われます。この電気信号への変換がフェロモンへの感度を高め、雄を惹きつける力の分子基盤となっていると思われます。
BmOR2ファミリーはハエと蛾が分かれて以来2億年の進化の過程で機能が保存されてきているタンパク質です。ロックフェラーのVosshallグループは、ショウジョウバエでBmOR2ファミリーに属するタンパク質をノックアウトすると匂えないハエになることを示しています。本論文でも、一般の匂いを感知する嗅覚受容体は、BmOR2によって発現と匂い応答が促進されることを示してます。つまり、昆虫においてBmOR2ファミリーは、匂いとフェロモンの受容の両方で必須の共通因子であることがわかったのです。フェロモン受容体はオスのアンテナにしか発現していませんが、BmOR2はオスとメスの両方にあります。オスのアンテナにおいて、フェロモン受容体はBmOR2の助けをうけて機能していますが、メスにおけるBmOR2は、主に匂いの受容体の支援をしていると思われます。
この論文のハイライトは、もうひとつのフェロモン物質であるボンビカルの受容体も発見したことです。しかも、ボンビカル受容体とボンビコール受容体は、決して同じ嗅細胞に発現していなく、感覚毛にある一対の嗅細胞にそれぞれ排他的に発現していることがわかりました。カイコガにおいては、ボンビコールが性誘引物質で、ボンビカルはその行動を抑制する効果があります。このように、ひとつひとつの嗅細胞で、ある特定の物質を認識するために特化した受容体が発現することによって、高選択性がうまれます。今回の成果からわかったことは、触角の感覚毛の2種類の嗅細胞が、それぞれ特定のフェロモン物質を認識し、それらの情報が脳(macroglomerular complex)へ伝わって、その二つの情報が適切に統合処理されることによって、行動が引き起こされるということです。カイコガでは、片方の神経細胞への刺激で行動が引き起こされてもう一方の神経への刺激で抑制されます。一方で、多くの昆虫では、構造異性体や鏡像体など2種類以上のフェロモン混合物を使っている場合があります。実は、今回カイコガでわかったように、嗅細胞にそれぞれ選択性の高いフェロモン受容体が発現していると仮定してみると、フェロモン混合物の作用を綺麗に説明することができます。以前から知られていた化学的知見と今回の分子生物学的知見が見事に一致をみたのです。
今回の成果は、地球最大の生物種である昆虫がどのようにして種の保存と分化をおこなってきたか重要な知見を与えるとともに、バイオセンサーや化学物質検定系の開発や、昆虫の新規制御方法の開発に応用できると思われます。
● Nakagawa,T., Sakurai, T., Nishioka, T., and Touhara, K.*
"Insect sex-pheromone signals mediated by specific combinations of olfactory receptors"
Science 307, 1638-1642 (2005)
● 仲川喬雄、桜井健志、西岡孝明、東原和成
"昆虫における匂いやフェロモンの受容メカニズム"
実験医学 23, 1210-1212 (2005)
● 福田七穂、仲川喬雄、東原和成
"嗅覚研究からわかった7回膜貫通型タンパク質の新規機能"
細胞工学 24, 492-493 (2005)
(仲川君は博士号を取得した後、Rockefeller大学Vosshall研のポスドクとして留学しています。) -
カイコガ性フェロモン受容体の発見 一世紀ほど前、ファーブルは、蛾の異性誘引現象を見て「におい」によって引きつけられているに違いないと提唱しました。その媒介となる「におい」物質は、半世紀ほどまえに、ブテナントらによってカイコ蛾で見つけられました。ボンビコールとよばれる低分子揮発性物質で、この発見を機に、フェロモンという言葉が使われるようになりました。我々は、雌で産成されるこの性フェロモンが、どのような機構で雄の蛾に作用し、誘引行動をひきおこすかに興味をもち、受容体の探索を手がけました。性フェロモンであるボンビコールは、売っている物質ではないので、我々の手で有機合成しました。アフリカツメガエル卵母細胞での発現クローニング法を試みましたが、なかなかうまくいっていなかったころ、京都大学の西岡教授のグループが雄のアンテナで特異的に発現している遺伝子をみつけたということで、フェロモン受容体候補として、リガンドと発現系をもっている我々と共同研究がはじまりました。最初はなかなか機能発現がうまくいかず苦労しましたが、アフリカツメガエル卵母細胞で応答がとれること、雌カイコ蛾に導入するとボンビコールの応答がとれること、この二つの結果で、我々はこの遺伝子が性フェロモン受容体をコードしているということを証明しました。西岡グループと東原グループの密接かつ協力的な共同研究が実を結んだ結果であります。昆虫が自分達の種を維持するとともに、数百万種類にまで進化した背景に、性フェロモンが深く関わっています。また、一方で、昆虫の制御にも応用がきく重要な発見であります。性フェロモン受容機構の全貌を明らかにした論文は、Science誌に掲載されました(成果12参照)。
● Sakurai, T., Nakagawa, T., Mitsuno, H., Mori, H., Endo, Y., Tanoue, S., Yasukochi, Y., Touhara, K.*, and Nishioka, T.*
"Identification and functional characterization of a sex pheromone receptor in the silkmoth Bombyx mori"
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101, 16653-16658 (2004)
● 桜井健志、仲川喬雄、東原和成、西岡孝明
"物質同定から半世紀、ついに見つけたカイコガ性フェロモン受容体遺伝子:絹王国日本が一番乗り"
細胞工学 24, 150-151 (2005) -
マウス精子に発現する嗅覚受容体の機能を解明 マウス嗅覚受容体MOR23は、成果20で紹介した単一匂い応答嗅細胞からの機能的クローニング法を使って、lyralというフローラルな匂い物質に応答した嗅神経からクローニングした受容体です。MOR23のlyralに対する応答は、アデノウイルスを使った手法と、培養細胞発現系を利用した方法で、再構成に成功しました(PNAS 1999; J. Neurosci. 2001)。このMOR23は、実は、精巣にも発現していることがわかったので、精子に発現していて何らかの物質を認識しているchemosensorとして機能しているのではと予測をしました。
そこで精子にlyralを投与してみると、精子が凝集する様子が観察されました。精子に発現する嗅覚受容体MOR23が匂いを認識して走化性を引き起こしたと考えられます。次に、MOR23が実際に機能していることを立証するために、MOR23を高発現するトランスジェニックマウスを作製しました。トランスジェニックマウスの解析により、(1)匂い刺激による精子細胞内カルシウムイオン濃度の上昇は、嗅覚受容体を介していること、(2)嗅覚受容体を介したカルシウム応答は精子鞭毛の屈曲を引き起こし、それが走化性の分子基盤となっていること、(3)cAMPやK8.6といった精子内カルシウム上昇を引き起こす試薬では精子の走化性が見られないことから、精子走化性には嗅覚受容体を介した局所的な反応が必要であるということ、を実証しました。
ドイツのHattのグループは、ヒトの精子においても、嗅覚受容体のリガンドBourgeonalによって走化性が引き起こされることを報告しました。しかし、LyralやBourgeonalは合成香料で、ヒトやマウスの体内に存在するとは考えられません。とすると、精子が子宮内に放出された後、卵巣や卵管からの何らかの内在性の物質を、嗅覚受容体が認識していると考えられます。今後、内在性のリガンドの同定が課題です。本成果は、鼻以外に発現している嗅覚受容体が、生理的な役割を担っていることを強く示唆するもので、他に、脳、発生段階の心臓、脾臓に発現していると報告されている嗅覚受容体の「匂い受容体」以外の機能を解明する強い動機付けとなるものと思います。
● Fukuda, N., Yomogida, K., Okabe, M., and Touhara, K.*
"Functional characeterization of a mouse testicular olfactory receptor and its role in chemosensing and regulation of sperm motility"
J. Cell Sci. 117, 5835-5845 (2004)
● 福田七穂、東原和成
"嗅覚受容体の鼻以外で機能しているか?"
生化学 76, 1462-1466 (2004) -
嗅覚受容体の糖鎖の重要性とGタンパク質共役に関わる部位同定 本論文では、嗅覚受容体の糖鎖修飾が細胞膜への移行に重要であること、そして、カルボキシル末端部分がGタンパク質との共役に関わっていることを生化学的に示しています。機能発現が難しい嗅覚受容体の細胞膜への局在を免疫化学的に明快に示した初めての報告でもあります。嗅覚受容体は、Galpha15が導入されている細胞ではGalpha15と共役してカルシウム経路を活性化し、Galpha15が存在しないとGsやGolfと共役してcAMP経路を活性化します。本研究では、Galpha15の結合部位と、Gs/olfの結合部位が違うことを示し、Gタンパク質との共役機構がサブタイプによって異なることを明らかにしました。また、嗅覚受容体のC末端には、ロドプシンと同様に8番目のへリックスがあり、Gタンパク質との共役に重要であるという新たな仮説を提唱しています。今後、受容体の活性化機構を解明する手かがりとなるでしょう。
● Katada, S., Tanaka, M., and Touhara, K.*
"Structural determinant for membrane trafficking and G protein selectivity of a mouse olfactory receptor"
J. Neurochem. 90, 1453-1463 (2004) -
嗅覚受容体アンタゴニズムを発見ー匂い混合物のコード形成機構、匂いの質を制御することが可能な概念を提供ー 本論文では、匂い物質を混ぜると、匂い同士がお互いの嗅覚受容体の活性化をブロックすることを示しています。受容体活性をブロックする物質はアンタゴニストと呼ばれ、このような現象をアンタゴニズムと呼びます。嗅覚受容体のアンタゴニズムの面白い点は、匂い物質は、ある嗅覚受容体を活性化するアゴニストとなりますが、別の受容体に対してはアンタゴニスト活性を有するということです。
A,B,2種類の匂い物質を混ぜ合わせると,A及びBに対応する全ての嗅覚受容体の応答が予想されます。しかし実際は,匂いアンタゴニズム、すなわちAに応答するはずの一部の受容体がBにブロックされるという現象が起きると,匂い混合物の受容体コードは、AとBの受容体コードを足したものではなく、新たな受容体コードができあがることになります。アンタゴニズムがおきた結果できあがった受容体コードが脳に伝わると、AとBを混合した匂いは、AとBが混ざったものではなく,AでもBでもない全く別の匂いとして感じることになります。この現象は、匂い同士の相互作用(odorant mixture interaction)と呼ばれ、心理学的には60年代から知られていたことです。つまり、匂い物質を混ぜると全く違う匂いになるといった現象や、香水のように匂い物質を混ぜて新たな匂いを作り出すこともできるといった現象に分子レベルでのメスがようやく入り、数十年にわたって議論されてきた匂い同士の相互作用のなかでも、特に抑制がおきるときの分子機構の一端を受容体レベルで明らかにしました。
一方、嗅覚受容体は、創薬の約半分の標的となるGタンパク質共役型受容体の最大のファミリーを形成しています。嗅覚受容体のアンタゴ二ズムのように、薬の標的の受容体へのアゴニスト活性に加えて、活性化したくない他のサブタイプの受容体のアンタゴニスト活性を同時に有する薬は、より特異性の高い薬として期待されます。このような考え方は創薬開発における新しい視点にもなります。嗅覚受容体は、鼻だけでなく、精巣や、発育段階における心臓や、脾臓や、脳にも発現していることが知られています。鼻にでている匂い受容体だからといってあながちあなどれない存在になる可能性もあります。このように、本研究で見出した嗅覚受容体のアンタゴ二ズムは、食生活、医療にわたって幅広く応用される基礎基盤を提供すると思われます。
この仕事は、2004年3月25日付けのNature誌のNews feature「The sweet smell of success」の記事のなかで紹介されました。
● Oka, Y., Omura, M., Kataoka, H., and Touhara, K.*
"Olfactory receptor antagonism between odorants"
EMBO J. 23, 120-126 (2004)
● Oka, Y., Nakamura, A., Watanabe, H., and Touhara, K.*
"An Odorant Derivative as an Antagonist for Olfactory Receptor"
Chem. Senses 29, 815-822 (2004)
● 東原和成
"生物がにおいを識別する仕組み"
化学と生物 41, 150-156 (2003)
● 東原和成
"におい受容の分子メカニズム"
生物物理 44, 26-31 (2004)
● 岡勇輝、東原和成
"匂い分子が嗅覚受容体をブロックする:その生理的意味と応用面"
細胞工学 23, 336-337 (2004)
● 岡勇輝、東原和成
"食べ物のおいしさを豊かにする香りの受容メカニズム"
日本味と匂学会誌 11, 129-136 (2004) -
嗅上皮の前額断生切片で匂い応答を測定するアッセイ系を確立 単一嗅神経細胞の匂い応答測定は、カルシウムイメージングおよび電気生理学的な手法を用いて行われてきました。しかし、嗅上皮レベルで匂い応答を可視化することは困難でした。嗅覚受容体は嗅上皮全体に発現しているのではなく、ゾーン特異的発現がみられるという特殊なパターンをしめします。私達は、ゾーンと受容体と匂い応答の関係を調べるために、嗅上皮の前額断生切片を乳児マウスから作製して、匂い応答の分布を測定できるカルシウムイメージング法を確立しました。この手法は、単離された嗅神経とは違って、本物の嗅上皮に近い状態で匂い応答をとることができるので、より生体内での匂い応答に近い状況を作ることができる画期的な方法です。嗅上皮での匂い応答の分布を見れるだけでなく、後述の匂いアンタゴニズムの解析にも威力を発揮しています。
● Omura, M., Sekine, H., Shimizu, T., Kataoka, H., and Touhara, K.*
"In situ Ca2+ imaging of odor responses in a coronal olfactory epithelium"
NeuroReport 14, 1123-1127 (2003)
● 東原和成、大村真代
"嗅覚受容体の構造・機能、嗅上皮分布"
日本味と匂学会誌 9, 33-41 (2002)
(大村さんは博士号を取得した後、Rockefeller大学Mombaerts研のポスドクとして留学し、現在マックスプランク研究所にMombaertsとともに移動。) -
嗅覚受容体の匂い応答を測定する様々なアッセイ系を確立 いくつかの嗅覚受容体の匂いリガンドは決定されましたが、多くの嗅覚受容体の匂いリガンドはまだ同定されていません。従って、培養細胞などのヘテロな系での機能的発現は急務と考えられます。私達はmOR-EGを使って様々な匂い応答アッセイ系を確立しました。まず、HEK293細胞で約80%の細胞で匂い応答がとれるまで条件を最適化しました。匂い応答は、カルシウムイメージングだけでなく、cAMPアッセイ、luciferaseリポータージーンアッセイによって測定できます。また、アフリカツメカエルの卵母細胞に発現させて電気生理学的な匂い応答をとることもできました。これらの様々な発現系を他の嗅覚受容体のアッセイに応用できると思われるので、世界中の嗅覚受容体研究者に役にたつ情報となっています。
● Katada, S., Nakagawa, T., Kataoka, H., and Touhara, K.*
"Odorant response assays for a heterologously expressed olfactory receptor"
Biochem. Biophys. Res. Commu. 305, 964-969 (2003)
● Touhara, K.
"Recent advances in functional expression of olfactory receptors: molecular basis for odorant recognition"
In Recent Res. Develop. Life Sci. 1, 47-56 (2003)
● Touhara K.
"Deorphanizing vertebrate olfactory receptors: recent advances in odorant response assays"
Neurochemistry Internatl. 51, 132-139 (2007) -
活性化される嗅覚受容体の組み合わせが匂い物質のコードとなることを立証 匂い応答をしめした単一嗅細胞のsingle cell RT-PCRによって、歯医者の匂いであるオイゲノール(eugenol)とバニラの匂いであるエチルバニリン(ethyl vanillin)の受容体であるmOR-EGおよびmOR-EVを同定しました。これらの受容体をヒトHEK293培養細胞に発現させると、匂い刺激によってcAMPの上昇が見られました。嗅覚受容体は嗅神経においてGalpha-olfと共役すると考えられていましたが、私達の結果は、嗅覚受容体がGalpha-sタイプのGタンパク質に共役することを初めて培養細胞で示したものです。また、様々なGタンパク質共役型受容体と共役するGalpha15と共発現させることによってカルシウム応答によって匂い応答を測定することができました。
mOR-EGとmOR-EVはアミノ酸配列で約80%の相同性がありますが、mOR-EGとmOR-EVのリガンドをさらにスクリーニングすると、vanillinを異なった親和性で認識することがわかりました。この結果は、匂い物質は、複数の嗅覚受容体によって異なった閾値で認識されることを示しており、匂い物質の濃度が変化すると受容体コードも変化することがわかりました。すなわち、匂い物質の濃度が濃いときと薄いときでは匂いの質が違うという私達が日常経験している現象を分子レベルで示したことになります。
以前から提唱されていましたが、数百種類もある嗅覚受容体のどの受容体で認識されるかという組み合わせが、個々の匂い物質の質を決定するコードになっていることを実験系で示したものです。オイゲノールとバニリンは構造が類似しているものの匂いの質は違います。mOR-EGは両者とも認識しますが、全体でみると活性化する嗅覚受容体の組み合わせは違うので違った匂いに感じられるのです。また、再現性良く嗅覚受容体の培養細胞での応答測定を可能にした初めての論文です。特にmOR-EGに関しては、現在、I7受容体と並んで世界で最も信頼されている匂い受容体で、世界中の多くの研究室でポジティブコントロールとして使われています。
● Kajiya, K., Inaki, K., Tanaka, M., Haga, T., Kataoka, H., and Touhara, K.*
"Molecular bases of odor discrimination: reconstitution of olfactory receptors that recognize overlapping sets of odorants"
J. Neuroscience 21, 6018-6025 (2001)
● Touhara, K.
"Odor discrimination by G protein-coupled olfactory receptors"
Microscopic Research and Technology 58, 135-141 (2002)
● 東原和成
"匂いを感じる:センサーとしての嗅覚受容体"
細胞工学 21, 1434-1438 (2002)
● 東原和成
"嗅覚受容体の匂い分子認識メカニズム:受容体遺伝子・構造・機能、そして「嗅覚」再考"
Aroma Research 2, 338-346 (2001)
(加治屋君は修士号を取得した後、資生堂に就職しました。) -
単一嗅細胞からの匂い受容体の機能的クローニング及び再構成 1996年、私が嗅覚プロジェクトを立ち上げたとき、1991年にBuck and Axelがクローニングした嗅覚受容体遺伝子ファミリーはまだputativeな匂い受容体でした。嗅覚受容体が実際に匂い物質を認識してシグナルを伝えることを立証するために、世界中の嗅覚研究者が嗅覚受容体を培養細胞に発現させて匂いリガンドを決定しようとしました。しかし、嗅覚受容体の発現が困難なことと、匂い物質がたくさんあることの理由により不成功に終わっていました。そこで、私達は新たな方法を考えました。
マウスにおいて匂い受容体は約千種類程度存在すると推定されていますが、興味深いことに、一つの嗅神経細胞には千種類のうち一種の受容体だけが選択的に発現しています。従って、個々の嗅神経細胞が応答する匂い物質とその細胞に発現している受容体とは対応していると考えられます。そこで、ある匂い物質に応答する単一嗅細胞に発現している嗅覚受容体遺伝子をクローニングする戦略をとりました。
ある特定の匂い物質に応答するマウス嗅細胞をスクリーニングするのに、匂い刺激に伴う嗅細胞内カルシウム濃度の上昇を複数の嗅細胞で同時に計測しました。その結果、各々の単一嗅細胞は違った匂い応答パターンを示し、各嗅細胞で異なった匂い受容体が発現していることが示唆されました。次に、single cell RT-PCR法を用いて単一応答細胞から発現嗅覚受容体遺伝子をクローニングしました。
応答細胞から単離した受容体遺伝子が、実際に応答を示した匂い物質を認識するという確証を得るためには、単離した遺伝子を再構成系で発現させ機能解析をする必要があります。しかし、嗅覚受容体は培養細胞などヘテロな発現系における機能発現が困難であるので、嗅細胞そのものを発現系として用いることを考えました。単一細胞からクローニングした受容体と蛍光タンパク質であるGreen Fluorescent Protein (GFP)を共発現させる発現アデノウイルスベクターを構築し、マウス嗅上皮上に感染させました。感染細胞は、GFPの蛍光で容易に区別でき、上記の細胞内カルシウム濃度測定装置を用いて匂い応答を計測しました。感染細胞は、受容体遺伝子を単一細胞から単離したときに応答した匂い物質にのみに反応をしめし、single cell RT-PCR法による受容体の単離技術の信頼性が確認され、嗅覚受容体の匂い応答の再構成に成功しました。この嗅覚受容体はMOR23という名称のもので、匂いリガンドとしてLyralなど三種類を同定しました。
本研究は、世界で初めて、嗅覚受容体遺伝子を機能的にクローニングし再構成実験によって匂い応答を確認したもので、1998年に匂いリガンドが決定をされたFiresteinらのラットI7嗅覚受容体に続くものとして評価を受けています。1999年同時期にBuckらは私達と同様のsingle cell RT-PCR法による受容体遺伝子の機能的同定論文をCell誌に発表していますが、現在、それらのいくつかはリガンドが違うことが他のアメリカのグループによって示されています。single cell RT-PCRによって得られた嗅覚受容体はあくまでも候補であり、私達が示したような再構成実験による検証が必要であるとの見解が世界的にも認められています。
● Touhara, K.*, Sengoku, S., Inaki, K., Tsuboi, A., Hirono, J., Sato, T., Sakano, H., and Haga, T.
"Functional identification and reconstitution of an odorant receptor in single olfactory neurons"
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 4040-4045 (1999)
● 東原和成 "匂いと受容体の対応付け"
実験医学 17, 961-964 (1999)
● 東原和成 "嗅覚受容体は匂いを嗅いでいるのか?機能的クローニングおよび再構成による新知見"
医学のあゆみ 194, 152-153 (2000)
● 東原和成"匂いを感知する分子機構:嗅覚受容体の生化学、分子生物学"
細胞工学 19, 111-119 (2000)