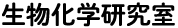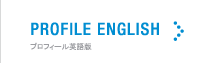手記
東原和成 ┃ Behavior meets biochemistry: Animal making sense of molecules making scents┃ 2014年2月2月18-20日
Behavior meets biochemistry: Animal making sense of molecules making scents (London, UK)
13年ぶりのイギリスである。野生マウスの行動に関する研究で有名なJane Hurstが、彼女の夫であり、ケミストリーでJaneの研究をサポートしているRob Beynonと一緒に企画したBehavior meets biochemistry: Animal making sense of molecules making scentsというシンポジウムに招待された。英国のBiochemical Societyがサポートするミニゴードン会議である。フェロモン業界では有名なPheromones and Animal Behaviorという本の第二版をだしたばっかりのTristrum Wyattをはじめ、哺乳類のフェロモン研究の最先端をいく研究者が一同に介した。揮発性のフェロモン、不揮発性のペプチド性のフェロモン、フェロモン受容体、そして様々な行動の研究まで広くカバーしており、参考になる発表が多かっただけでなく、ミーティング中には有意義なディスカッションがたくさんできた。
シンポジウムのあとは、JaneとRobがいるUniversity of Liverpoolを訪問した。Liverpoolはビートルズの出身地として有名なところである。今年のイギリスは異常気象で暖かく、雨が多く、洪水がいたるところでおきたようで、車窓から見える牧場にもかなりの水がたまっていた。寒くて大雪が降った今年の東京の冬とは対照的である。Janeは野生マウスを300平米ほどのフィールドで飼って研究をしている。施設内の行動実験セットも目を見張るものがある。Robは最新鋭の分析機器を多数所持しており、尿、唾液、涙液の分析を精力的に進めている。一方、JaneとRobは家でミアキャットとカワウソを飼っている。まるで動物園のようだ。滞在中は研究のことだけでなくいろいろなことを話すことができて、JaneとRobの人柄を改めて感じた時間であった。
LiverpoolのあとはCambridgeを訪問した。初期のころは研究の競争相手であったが今はとても親しい友人であるStuart FiresteinがサバティカルでKing’s collegeに滞在しており、来い来いというので、ケンブリッジも初めてということもあり、ちょっと足をのばした。University of Cambridgeは今までに80人ものノーベル賞受賞者をだしており、古き良き伝統がまだ根強く残っている世界有数の大学である。約30個のカレッジからなっており、そのなかでもKing’s collegeはケンブリッジの観光スポットのどまんなかにある。今回は、StuartがKing's collegeのゲストハウスをとってくれた。とても雰囲気のある築数百年の古い洋館である。暖炉のある部屋のなかには古い書物が本棚に並び、壁には肖像画がかけられており、まるでハリーポッターの世界のような幽霊でもでそうな部屋である。しばらく長い年月の歴史に思いを馳せながら、ひととき情報社会の喧噪から逃れてほっとした時間であった。
ケンブリッジの中心には、The Eaglesというイングリッシュパブがあり、そこでWatsonとCrickが飲みながらサイエンスの話を交わしたという。そこのオリジナルのThe Eagles DNAという地ビールで乾杯し、Stuartとしばし最近の話題で盛り上がった。夕食はHigh Tableでの食事である。High Tableに連れていってやるとStuartから言われていたが、なんのことだかさっぱりであったが、要するにCollegeの食堂である。ハリーポッターででてくる食堂をイメージもらうとわかると思うが、ダイニングホールのなかでも、学生が食べるところと教授が食べるところがわかれている。縦に並ぶ学生のテーブルとは違う、奥の一段高くなっているところにある横並びテーブルに教授達は座る。つまり、教授が食べる机は一段高くなっているのでHigh Tableというのである。そこに座って食べることができるのは教授とそのゲストのみである。このとき、教授はガウンを着なくてはいけない(Stuartもガウンを着た)。年長の教授があいさつをして食事をスタートするが、食事中は本を読んだりコンピューターなどで勉強したりしてはいけなく、みんなと話すことが義務付けられている。その他いろいろ厳しいルールがある。その場の写真をとろうとしたら怒られた(苦笑)。イギリスの古き格式のある伝統である。
イギリスでは、学生と教授との間には格差があるが、学生は教授をリスペクトし、教授は学生を心底から熱く教育をする。授業のなかには、教授と学生が一対一でディスカッションする時間がある。いわゆるtutorialという制度である。イギリスでは教授の権威が高いだけでなく、教育に対する責任も重い。一方で、最近の日本の教授の権威は失墜しているだけでなく、学生を教育するという点では、われわれはKnowledgeとPhilosophyのレベルが低いと感じる。King's collegeでは私もProfessorとして扱われたが、なんか自分の教員としてのレベルの低さを思って、とても恥ずかしく感じた。
さて、イギリスの料理である。一般的にイギリスの料理はあまり美味しくないと言われているが、その理由はあまり味付けをしないからである。テーブルには必ず塩と胡椒がある。ただ、食材自体が悪いわけではない。バターまみれにするフレンチと違って、素材の味を大事にしているという点では、健康的だと思う。でも、最近はきちんと味付けをしているようで、私が食べた範囲以内では、とても美味しいものばかりだった。ただ、味付け自体にはイギリスの特徴はなく、どちらかというと、いろいろな国のやりかたを取り入れているように思える。ビールはバーで飲むもので、食事と一緒に飲む習慣はなく、ワインもイギリス産のはほとんどない。ただ、バーでのウイスキーのラインアップはさすがだ。日本のウイスキーもきちんと並んでいる。いずれにしても、イギリスの食文化も進化していることは確かだ。
今回の出張は、研究面でいいディスカッションができただけでなく、イギリスの格式高い伝統に初めて触れて貴重な体験をすることができた。各々の国がもつ伝統は、リベラルへの流れとその時代の考え方に影響をうけながら変化をしていく。そのなかで、良き風習はきちんと守りながら、温故知新の精神で、新しい潮流を作ることが大切なのだなと感じる。欧米に追い付け追い越せの精神で走ってきた日本のサイエンスのこれからはどこに向かえばよいのか。Touhara labの研究は、トレンドにふりまわされずに、10年20年後の礎になる研究とそれを担う研究者の育成のなかにオリジナリティが生まれるような方向性をとりたい。それにしても、ヨーロッパから帰国すると時差で午前中が辛い。
平成26年2月25日