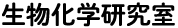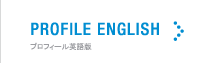過去の研究テーマ
卒業研究(1988年4月〜1989年3月)
植物ホルモンのアブシジン酸の誘導体であるファゼイン酸の両鏡像体の全合成
卒業研究は有機化学研究室(当時:森謙治教授、北原武助教授)で行いました。生命現象の中心的役割を担っている有機反応を最初に学んだことは、現在の私の研究のスタイルに大変影響を与えています。また、すばらしい先生方に研究者としての駆け出しの時期に出会えたという幸運にもめぐまれ、アメリカという大国の教育および研究の世界に飛び込む決心が固まったのもこの時期でした。昭和63年の研究室忘年会の翌日、幸運にも、表記テーマの最終物の合成に成功し、農芸化学会での発表の機会を与えてもらえました。そして、昭和も終わり、平成元年6月4日奇しくも天安門事件の当日、渡米をすることになります。
アメリカの大学院への留学のきっかけは以下のとおりです。
- 優秀な人達を相手に凡人が生き残っていくためには、彼等と違うことをしなくてはいけない
- アメリカに留学して落第したら潔く帰国して就職すれば良いという背水の陣的感覚があった
- 日本で博士を取ったところで自分がその分野に向いているかは日本にいたらわからないのではないか
などの動機でした。アメリカ留学して向こうで勝負したいなど、殊勝な心掛けはありませんでした。しかし、最近のようにウェブで簡単に情報を得れる時代とは違って、日本でも隣の研究室で何をやっているかわからなかった時代に、留学を現実化するのには、大変なエネルギーを使いました。一方で、全く情報がなかったので、怖いもの知らずで、若気の至りでつっこんでいけたということもあります。いずれにしても、アメリカの大学院で教育を受けたことは、今でも自分のオリジナリティーの基盤となっています。
サマーリサーチ(1989年6月〜1989年8月)
チャバネゴキブリの性フェロモンおよび前駆体のトリチウム標識品の全合成
渡米後、Glenn D. Prestwich教授(ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校化学科、現:ユタ大学教授)の研究室で、放射性同位元素でラベルした昆虫フェロモンおよびその前駆体の全合成を行いました。合成した前駆体をゴキブリの背中に投与すると、フェロモンに放射性同位元素が検出され、生物現象の解明におけるラベル化合物の有用性を知りました。その後、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校化学科博士課程に入学し、講義中心のアメリカ大学院1年目に突入します。
博士研究(1990年5月〜1993年7月)
昆虫幼若ホルモンの輸送タンパク質・代謝酵素・受容体の同定および単離
昆虫幼若ホルモンは、昆虫の成長・変態を制御する昆虫特有のホルモンのひとつです。幼若ホルモンがどのような作用機構で昆虫の幼虫形質を維持させるのかを解明するためには、1)幼若ホルモンを分泌器官から標的細胞まで輸送する役割を担うタンパク質、2)標的細胞において幼若ホルモンを受容するレセプター、3)標的細胞において幼若ホルモンを分解する代謝酵素、などの解析が必須と考え、それらのタンパク質の同定、単離、遺伝子クローニングプロジェクトを行いました。
これらのプロジェクトを通して、タンパク質の同定、精製、部分配列決定、そして、遺伝子クローニング、発現、機能解析(受容体、酵素)といった、基本的生化学、分子生物学的手法を取得しました。本一連の研究成果に基づいて、Ph.D in Biological Chemistryの学位をGlenn D. Prestwich教授から授かりました。また、余談ですが、Lee Myers Graduate Student Award (1993)(リーマイヤー優秀大学院生賞)をいただきました。
博士研究員(1993年8月〜1996年1月)
三量体Gタンパク質を介した情報伝達に関する研究:Gタンパク質共役受容体キナーゼ、プレクストリン相同領域、MAPキナーゼ活性化
NY州立大学で博士取得後、博士研究員としてデューク大学医学部のRobert J. Lefkowitz教授の研究室で研究をしました。Lefkowitz教授はアドレナリン受容体の研究を長年続けてきている人です。私が研究を始めたころは、アドレナリン受容体キナーゼ(βARK)が三量体Gタンパク質βγサブユニットによって活性化されるという知見が確立されていました。偶然にも、βARKにプレクストリン相同領域(PH domain)があることが発見され、私は他のPH domainもGβγに結合するのではという仮説のもとに研究を始めました。確かに様々なPH domainがGβγに結合することが明らかになりましたが、結合部位はPH domainと完全に一致しませんでした。その一方で、PH domainがリン脂質に結合するという報告がなされ、私達は、βARKのPH domainはGβγとリン脂質が相乗効果的に結合することを示し、PH domainは単なる脂質結合領域でなく、様々なファクターによってその結合が制御されていることを明らかにしました。
一方で、Gβγを介した情報伝達機構を解析し、チロシンキナーゼタイプの受容体を介したRas/MAPキナーゼの活性化および細胞増殖へのシグナル経路とGタンパク質共役型受容体との経路とのクロストークの重要性を示しました。つまり、Gβγを介したRas/MAPキナーゼ活性化機構の解明にとりくみ、チロシンキナーゼ、wortmannin感受性PI-3-キナーゼ、Shc、Grb2、SOSの関与を明らかにしました。
日本帰国後の研究の立ち上げ(1996年1月〜)
日本で嗅覚プロジェクトを立ち上げた経緯は?
さて、いつ頃から日本帰国を考えはじめたのでしょうか?アメリカでの大学院時代は帰国する意志はあまりなく、とにかく早くPh.Dをとってサイエンスの先端をいくアクティブな研究室でポスドクをしたいという気持ちばかりありました。また、アメリカのサイエンスの良いところをどんどん吸収したころでした。さて、ポスドクをはじめたころでしょうか、私は多くの日本人のポスドクのようにお客さん扱いは受けずに、対等の競争者として接され、また、英語力もそれなりについていたころ、結局本質的なところはアメリカも日本も変わらないのではないかという感覚を持ちはじめました。表面上は仲が良いようですが、よく見たり聞いたりすると人間同士の醜い争いはあるし、所詮、アメリカ人も日本人も同じなのです。では、研究の環境やスタイルはどうでしょうか?確かにアメリカの研究の環境は日本にくらべてはるかによく、また、最先端のサイエンスを引っ張っている感じを受けます。でも、日本でも贅沢を言わなければ研究はできるし、また、何が最先端のサイエンスかという判断をくだす根拠はどこにもないのです。アメリカには良いと言われている雑誌が多いので、いわゆるそれらの雑誌にだしているから最先端であるという幻想に陥るのです。
帰国の決心の理由はいろいろあります。
- 自分がアメリカで見てきたことを後輩達に伝えたい
- 日本の研究制度にアメリカの良いところを日本バージョンに改良した形で取り入れたい
- 研究はどこにいてもできるはずで、アメリカにいたからできたなどと言われたくない、日本でも研究ができるのだということを証明したい
- そして、最後に、少々日本傾国主義的になっていたことと、語学面などでかなりのストレスがたまっていたこと
さて、本題に入りますが、なぜ、嗅覚プロジェクトを立ち上げたのでしょうか?前述のように、私は、植物ホルモンや昆虫フェロモンのような天然物活性物質の合成研究からサイエンスの世界に飛び込みました。当時から一貫して興味の対象としてあったのは、いかにして生物は外界からのシグナルを受容するか、つまり化学受容(Chemoreception)という概念でした。大学院時代は、核内レセプター(幼若ホルモンの受容体)に関しての研究に携わり、ポスドク時代は、Gタンパク質共役型受容体のシグナル伝達および脱感作機構の研究をしました。様々な研究分野で実験を続けてきましたが、常に、「化学物質」がどのようにして「受容体」によって認識され、どのような「シグナル」が伝達され、どのような「現象」を引き起こすかという一連の流れに沿って研究をしてきました。その中でも、多種多様なリガンドを識別する嗅覚は非常にアトラクティブな分野として私の中に存在し続けました。
日本に帰国する前日のポスドク時代の師匠であるLefkowitz教授からの言葉です。
「私の研究室をでた人間の中には優秀な研究者がたくさんいる。しかし、Lefkowitz研究室の色から完全に脱して、自分自信の色を打ち出すことに成功した人間はほんの一握りだ。日本で著明な研究者も、アメリカなどでのポスドク時代の成果を引きずっている人がほとんどだ。Kazu、本当にオリジナリティをもった研究者として評価されるには、いかにして自分の領域というのを作っていけるかである。」と。
この時、私は決心しました。自分の今までの研究経験を最大限にいかした形で、今まで自分の中で暖めていた分野に飛び込んでいこうと。そして、今の私がいるのです。
東京大学医学部神経生化学教室助手(1995年10月〜1998年3月)
単一匂い応答嗅細胞からの嗅覚受容体遺伝子の機能的クローニング
当時、推定上の匂い受容体であった嗅覚受容体が本当に匂い物質を認識するかどうか、また、数十万といわれる匂い物質と数百個の受容体の対応のルールを明らかにすることを目的に研究をはじめました。単一細胞レベルでの分子生物学的解析やカルシウムイメージングなどの技術はもっていなかったので、実験系の立ちあげには苦労しました。しかし、1999年の3月にはようやくProc. Natl. Acad. Sci. USAに成果を発表して、嗅覚世界の研究者としてのデビューを果たしました。(最近の成果参照)神経生化学教室助手時代に研究室内外で知り合った様々な学生、研究員、先生方とは貴重な出会いとして今でも残っています。
神戸大学バイオシグナル研究センター助手(1998年4月〜1999年3月)
嗅覚受容体の機能的発現系の開発
東京大学での助手のポジションが2年任期ということで、神戸大学の吉川先生に助手として拾ってもらいました。東京大学で立ちあげた実験環境から去ったので、またいちから立ちあげがはじまりました。しかも、結果的に1年という短期間であったため、効率の良い実験結果をだすことはできませんでした。
東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻助教授
(1999年4月〜2009年12月)
嗅覚に関する分子細胞学的研究
これまでは、一緒にやってくれる大学院生もひとりか二人、しかも指導教官ではなかったので継続して共同研究をやることは困難でしたが、ようやく、大学院生をとれるようになり、研究テーマも広げることが可能になりました。しかし、新しくできた研究室ということもあり、またもやいちからの立ち上げがはじまりました。最終的な実験環境の立ち上げは、平成13年夏の東大柏キャンパスへの移転によって完了し、ようやく、研究を推進する環境が整いました。そして徐々に増えてきた一緒にやってくれる大学院生の指導の毎日がはじまり、現在にいたっています。
日本帰国以来、嗅覚研究をたちあげながら、研究室を転々とした結果、アメリカで創出できた数には到底追い付かないレベルまで論文数が減ってしまいました。しかし、自分のひとつひとつの論文に対する満足度と思い入れは上昇し、それとともに、一研究者としての対外的な評価を着実に獲得できてきている感触を得ています。今は、自分自信が研究のPIとして、育てた学生さん達がひとつひとつ立派な論文をだし始めていることに格別の喜びを感じています。
嗅覚受容体に関する研究とはいっても、その研究テーマを幅広く設定し、現在、10人程度の大学院生諸君に日夜がんばってもらっています。嗅覚研究は非常に難しく、また、テーマも大きなものが多いので、なかなか研究成果として創出できませんが、ひとつひとつの論文の重みを大切にして、オリジナルな研究を目指しています。一方で、研究室の雰囲気や人間関係に関しても気をつかっています。成果がたくさんでている研究室は、研究成果をだすために学生や研究員が歯車になってしまっているところが多いですが、私の目指す研究は、必ずしも研究成果が第一優先ではありません。人間性も大事にし、けじめのある研究生活をおくり、将来、どこへいっても立派にやっていけるような研究者にみんながなれるような環境作りへの努力もおこたっていません。
私が現所属する新領域創成科学研究科は、領域を超えた新しい分野を開拓していこうというスローガンを掲げて立ち上がった新研究科です。その中で、今後、どのような研究を展開していけるかが今後の課題です。(2005年)