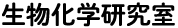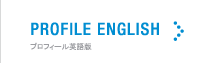手記
東原和成 ┃ 22nd Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology ┃ 2006年7月15-19日
2006 国際化学生態学学会(Chemical Ecology Meeting)
ニューヨーク州立大学の大学院生だったころ、Baculovirusの技術取得のために、UC DavisのBruce Hammock教授のところに一ヶ月間滞在したとき、Bruceの秘書の紹介で、二人のスペイン人が住むアパートに間借りしたことがあった。キャンパスから自転車で約30分くらい走ったところであったが、彼らはとても陽気で、夜な夜なサルサ(日本人のボーカルのノラのオーケストラ ・デ・ラ・ルスがはやっていた)をかけては盛り上がっていたのを覚えている。今年は、Chemical Ecology Meeting(化学生態学学会)に講演を頼まれて、そのスペインはバルセロナの土を初めて踏んだ。今ヨーロッパでもっとも危険(日本人がねらわれる)といわれている国である。
匂いの研究をやっている者にとっては、それぞれの国の香りの違いが興味深いのだが、バルセロナの空港についたとたんに、強い香水の香り。とにかく強烈である。市内にでると、それに加えて、肉系の匂いが強い。どうもワイルドな動物臭さのある香りの街といえようか。一方、今回スペインのあとに寄ったフランスはパリも、香水が香る街と感じたが、パリの香りのほうが洗練されたどっちかというとシャープな香りである。サンジェルマン・デ・プレ付近の歴史あるオープンカフェバーを潤すミストにもほのかに香りをつけているのではないかと思うほどである。
さて、Chemical Ecology Meetingは、バルセロナ大学生物学科の講堂で行われた。講演に招待されてから知ったのだが、学会の会頭は、偶然にも、私が大学院時代の指導教官であったPrestwich教授のところに1ヶ月ほど共同研究で実験をしにきていたAngel Guerrero教授であった。こんなところで15年の歳月を経て再会するなど思いもよらなかったことである。お互い変わらないなぁなどといって握手をしたが、いまさらながらに研究の世界はせまいものだと再確認した。どんな出会いが将来どんなつながりとなって活きてくるかわからないものだ。どんなときも常に手を抜かずに全力をつくして論文も発表もしなくてはと思う。
シンポジウムのタイトルは、Molecular Biology of Olfactory Receptionで、座長のWalter Leal、そして、Richard Vogt, Richard Newcomb, Heinz Breerと私の4名が講演者として招待された。私は昆虫の性フェロモン受容体の研究についての発表をした。午前11時半に話したが、ヨーロッパのこの時間は日本時間の夕方6時半なので時差も感じなく、アメリカと違って体力的に楽だ。ところで、H.Breer氏のグループの結果と若干矛盾するところがあるのだが、その点についてはまだ解決できていない。残念ながらH.Breer氏は今回は多忙のため代役を送ってきて再会ができなかった。ところで、少々驚いたのは、このシンポジウムではそんなに質問が飛び交うことがなかった点だ。私の発表には2-3質問がでたが、質問がでない発表もかなり多かった。この学会のメインは、昆虫のフェロモンの構造決定や植物との関連で生態学的な仕事をやっているひとが多いので、分子生物学がわかるひとが少ないせいなのか、それともどちらかというともともとほんわかとした学会のせいなのかわからないが、200名弱のこじんまりとした仲の良いのんびりとした学会という感じを受けた。
さて、今回は学会を少しぬけだしてバルセロナの街を散策した。バルセロナは、もちろん、建築家のガウディが有名である。そのなかでももっとも有名なのが、150年ほど前に着工し、いまだに建築中で完成までにあと100年はかかるといわれている、サグラダ・ファミリア寺院である。そのスケールには圧倒されたが、この作業をささえる背景となっている宗教の力に敬服せざるをえない。ガウディ建築の美しさの原点は、自然の姿であるという。その建築曲線の由来は、森林の木々であり、昆虫であり、動物であり、海の波である。自然界のもつ曲線は、偶然の結果ではなく、極めて厳密に設計されたものであり、それは逆にいえば、数学の式によって簡単にあらわせられる、つまり、最初から一番安定で強い設計図になっているのである。ガウディはそれを知っていた。実は、ガウディだけではない、レオナルド・ダ・ビィンチにしても、フェルメールにしても、芸術の美をもとめる過程で、自然の形、すなわち科学の力を使っている芸術家は少なくない。私はガウディ建築を眺めながら、その威風堂々とした安定感に科学の力を感じ、すなわち、自然の美というものを再認識した。
帰りは、バルセロナからの経由地であるパリに途中下車し、パリ中世美術館に寄った。そこに保管されている「貴婦人と一角獣:La Dame a la Licorne」は、人間の五感を寓話的に表現されたものと言われていて、五感それぞれの絵と、第六感の絵の6つの絵から構成されている。味覚と嗅覚の絵のなかでは、サルが砂糖をなめ、花の香りを嗅いでいるのであるが、視覚の絵には登場せず、触覚の絵では逆に鎖につながれていたのが印象的だった。芸術家と科学者、そして、建築と五感、そんな対照的でありながら表裏一体の言葉が私の頭のなかを呼応しながら、あらためて、五感・感性の研究の重要さを思った。私がサイエンスをやっているのは、実験から導き出される自然の摂理の美というものにやみつきになっているからである。逆に、その美しさを論文のなかで表徴させたい。それが常日頃から自分のサイエンティストとしての力との挑戦で願っていることである。ややもすると、多くの思想家や哲学者は科学をさけ、逆に科学者は思想を排除する。しかし、科学者はPh.D. (Doctor of Philosophy)であり、哲学をもつ人間であるはずである。嗅覚研究をはじめてから自分が責任著者としてだしてきている論文に、私特有の美のセンスの歴史が刻み込まれていたとしたら、とてもうれしいことだ。そんな思いをモーティべーションにひとつひとつの論文を学生達とともに作り上げていきたい。(平成18年7月末日)