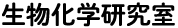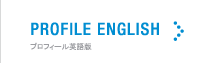報告記
以下は、2001年Aroma Researchに掲載されたシンポジウム参加日記です
東原和成 ┃ Molecular Biology of Chemosensory Receptors: The First Decade ┃ 2001年3月11~14日
『嗅覚受容体遺伝子クローニング10周年記念シンポジウム』に参加して
去る2月15日付けの分厚い「Nature」誌でのヒトゲノム全配列の報告はまだみなさんの記憶に新しいと思う。驚くことに、ヒトゲノム解析の結果、人間の遺伝子の約1%が嗅覚受容体であり、偽遺伝子を含めると数%にも及ぶことが明らかになった。五感のなかでも特に嗅覚が劣るといわれている我々人類の遺伝子の数%が嗅覚における匂い受容を担うタンパク質をコードしているとは興味深い。一方で、今年は奇しくも、Linda Buck (Harvard Univ.)とRichard Axel (Columbia Univ.)が推定上の嗅覚受容体遺伝子を単離して「Cell」誌に報告して以来、ちょうど10年である。それを記念して、Peter Mombaerts (Rockefeller Univ.)とStuart Firestein (Columbia Univ.)の呼びかけで、世界各国からの約30名の招待研究者が集まって嗅味覚受容体の最前線を語り合うシンポジウムが、2001年3月11~14日の4日間、コールドスプリングハーバー研究所Banbury Center(アメリカニューヨーク州)で行われた。日本からは、坂野仁教授(東京大学)と筆者の二人が招待され、アメリカを中心に進んできている嗅味覚受容体の分子生物学マフィアに日本代表として切り込みをかけた。
Banbury Centerは夕日の綺麗なコールドスプリングハーバーを見下ろすニューヨークはロングアイランドの最高級の場所に位置する。そこでは30人強の小グループによるシンポジウムを毎年20個くらい引き受け、素晴らしい食事とカクテルアワーなどいたれりつくせりのサービスを提供する。厳選されたミーティングのみできるそうでここで開催できるということは名誉でもあるらしい。参加者はすべて招待者のみ、学生の同伴も断られたほどである。そして、Proceedingsなども出さない未発表結果を交換する完全クローズドのものである。さて、まず、オーガナイザーのP. Mombaertsが、BuckとAxelのクローニング論文が飛躍的に嗅覚分野を発展させる引き金になったと祝福してシンポジウムは始まった。Opening lectureでL. Buckが匂いと受容体の組み合わせ論と嗅覚高次神経系の可視化についての新知見を報告し、最後は、R. Axelが嗅覚受容体遺伝子の発現制御に関するClosing lectureで締めくくるという演出が用意された。これらはいずれも日本の嗅覚研究グループとデッドヒートを繰り広げている部分である。その他は、哺乳類嗅覚受容体遺伝子ゲノム解析、哺乳類以外の化学感覚受容体遺伝子、味覚受容体、嗅覚受容体の分子生物学と発生、嗅覚受容体の機能、の5つのセッションにわかれ、それぞれ3~5人が講演をした。その中でも特筆すべきものをピックアップしてみる。
カリフォルニア州のSenomyx社らが、ヒトゲノム上の嗅覚受容体遺伝子ファミリーを検索した結果、347個の嗅覚受容体の存在が明らかになり、特に第11番染色体にその約半数が集中していることを発表した。人間の鼻でこれらが機能をもって発現しているかどうかは今後の研究によって明らかになるだろう。その後、ゲノム解析の終了しているショウジョウバエおよび線虫の嗅覚受容体についての発表のあと、様々な種における嗅覚受容体の存在意義および遺伝子進化についての激しい討論が交わされ、原始感覚として保存されてきた嗅覚という感覚系の深遠さをうかがわせた。次に、最近話題になっている苦味の受容体とうまみの受容体についての機能解析結果の発表があった。ここで、米国N.I.H.研究費担当者が現れ、アメリカにおける嗅覚研究に対する研究費が、1991年のクローニング以来急上昇してきたことを考慮すると、味覚受容体のクローニングが成功した今、今後10年は味覚に関する研究費が増大するだろうとの見解をだす。また話題は嗅覚にもどり、数百種類以上の嗅覚受容体遺伝子のうち一種類のみが単一嗅神経細胞で発現する分子メカニズムについて、特に、坂野仁教授らの遺伝子操作技術を駆使した相互排他的発現機構の研究は反響を呼ぶ。その他、嗅覚受容体タンパク質がいかにして機能的に膜に発現するかというブラックボックスに関する議論が交わされる。さて、長い間「putative」であった嗅覚受容体が実際に匂い物質を認識する機能をもつことは、筆者らを含めた数グループの研究成果によって証明されている。今回の学会では、ショウジョウバエの嗅覚受容体の機能解析に初めて成功したという発表があり注目される。また、筆者は、単一嗅細胞から機能的に同定した嗅覚受容体に関して、オーバーラップする匂いリガンドを持つ複数の嗅覚受容体の再構成とGタンパク質との共役実験に初めて成功したことを報告する(J. Neuroscience in press)。
嗅覚研究は、一昔前まではどちらかと言えばマイナーで地味な領域であったのが、近年、様々な種の生物を対象に各学問領域を総括する生命科学の最先端をいくものであると認識されつつある。招待者のなかでも、領域横断的な研究者が嗅覚研究をリードしているということもそれを物語っている。オーガナイザーのP. Mombaertsも坂野氏も、免疫抗体産生機構でノーベル賞をもらった利根川進氏の弟子であることは興味深い。明らかに、一昔までの閉塞的なアプローチでは解決されない事象が多くなっている。ゲノム情報科学時代が到来し、人類福祉への新たな応用を考えるときに、遺伝子というハードに埋め込まれたソフトの情報のなかでも特に「感覚」というものを原点に生物を見直すことは重要である。無臭志向にのってどちらかといえば蔑視されている嗅覚をもっと広義に考え、「空間を経験する感覚のひとつ」という概念を筆者は発表の最後で提唱し、Closing lectureでのR. AxelのSynchronyという言葉に表れる「時間軸」の重要さと呼応した。
主な嗅味覚の学会として、毎年4月にフロリダで開催されるAChemS学会、3年おきに開催されるISOT国際味と匂のシンポジウム、それと、数年に一度のゴードン会議があるが、本ミーティングのオーガナイザーのP. MombaertsとS. Firesteinは、FASEBやKey Stoneのシンポジウムにも嗅覚を参画させて盛り上げようとしている。少ないながらも小生の嗅覚研究にいち早く注目してくれ招待してくれた彼等に対する感謝として、私も力不足ながら貢献できたらと思っている。そんななかでも、純粋に日本から発信する研究成果を今後も多くだすことによって日本の嗅味覚研究の評価が高まるのだろうと、アメリカ大学院教育を受けたにも関わらず若干日本傾倒主義の小生は思う。
参考までに、本シンポジウムの参加者をリストしておく(アルファベット順)。Hubert Amrein, Richard Axel, Cornelia I. Bargmann, James F. Battey, Linda B. Buck, Nirupa Chaudhari, Andrew Chess, Barry Davis, Paul Feinstein, Stuart Firestein, Dominque Giorgi, Charles A. Greer, Hanns Hatt, Brian Key, Sigrun Korsching, Doron Lancet, Robert F. Margolskee, Timothy McClintock, Peter Mombaerts, Randall R. Reed, Hugh Robertson, Nicholas Ryba, Hitoshi Sakano, Gordon M. Shepherd, Jorg Strotman, Roberto Tirindelli, Kazushige Touhara, Barbara J. Trask, Leslie Vosshall, Mark Zoller, Sergey Zozulya(平成13年3月30日)