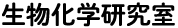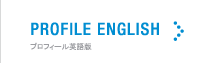以下は、最新医学に寄稿したものです
「におい受容体の発見で解けた嗅覚の謎ーリチャード・アクセルとリンダ・バックー」
においの神秘
人間の自我の形成には視覚と聴覚が必要であり、嗅覚は不必要であるという思想や哲学から、歴史的に、においの感覚である嗅覚はあまり重要視されてこなかった。また、中世ヨーロッパにおけるペストの流行がきっかけとなって、衛生志向でにおいの排除は徹底的にされた。一方で、どんな民族でも儀式や宗教の祈祷などで香りは重用されてきたという事実がある。われわれ日本の文化でも、歌舞伎役者が亡くなったときに書かれる死絵には必ずお香が炊かれている。おそらく、気持ちや情動に直接働きかけるというにおいの作用が神秘的であったため、われわれ人間はにおいの力を使うとともに、においに敬意を払っていたのであろう。
一方で、人間以外の動物にとって、嗅覚は、食べ物を見つける、敵味方の区別、異性の認識など、生存にとって不可欠な重要な感覚である。人間にとっての嗅覚は、そのような役割はなくなり、美味しいものを食べたり、生活空間で癒されたり、どちらかという幸せに生きるための感覚である。もっとも、臭いにおいに対しては行き過ぎる消臭をするのも人間である。いずれにしても、神秘的なパワーをもつにおいが、鼻でどのようにして感知されて、脳でどういったメカニズムで認知されるかは、自然科学者にとっては、とても魅力的な研究テーマであった。
においの受容の学説
匂いが感知されるメカニズムについては、受容体が発見されるまでは、大きくわけて、分子振動モデル、吸着モデル、立体構造モデルの三つの説があった。分子振動説とは、においの分子を構成する原子と原子の結合から生まれる特有の振動スペクトルを鼻のなかの嗅神経細胞が読み取っているという説である。古くは30-50年代にかけてDysonやWrightらが提唱したが、立体構造説が優勢な今なお、「匂いの帝王」(早川書房)の著者であるLuca Turinは本説を支持している。吸着モデルは、においが膜に吸着することによって膜電位が変化するという説であり、栗原博士(北海道大学)らが80年代前半に提唱している。そして、立体構造モデルは、におい物質の化学構造が認識されるという説である。例えばAmmoreは、50-60年代に、視覚における赤・緑・青の3原色と同様に、全てのにおいはその分子構造の特徴から、エーテル様,樟脳様,麝香様,花香様,ハッカ様,刺激臭様,腐敗臭様の7種の原臭に分類され,それぞれがあてはまる穴をもつ受容器が存在すると予想した。実は、この立体構造説は古代ローマに遡ることができる。哲学者のルクレチウスは、「においというものは、原子のつながった分子でできていて、分子の形や大きさの違いが、においの質の違いを生む」と言っている。これらの三つの説は、80年代まではどれもある程度の説得力があるものの、決定的な証拠に欠けていた。
嗅覚受容体の発見
80年代後半にかけて、嗅神経細胞内にアデニル酸シクラーゼが存在することや、におい刺激によって開くチャネルがcAMP依存性であることが見出されたのをきっかけに、においの受容にはGタンパク質共役型ファミリーが関わっている可能性が示唆された。そして、1991年にLinda Buckと Richard Axelは、Gタンパク質共役型受容体(GPCR)に保存されているアミノ酸配列をもとに設計した縮重プライマーを用いて、ラットの嗅上皮から,1000個近くもの多重遺伝子群を形成する新規の7回膜貫通型GPCR遺伝子のクローニングに成功した(図)。今までに二千回以上引用され続けているビッグ論文である。しかし、論文のタイトルは「A novel multigene family may encode odorant receptors: A molecular basis for odor recognition」とあるように、あくまでも嗅覚受容体遺伝子候補であった。その後、多くのひとが、実際ににおいの受容体であるかどうかの実証実験を試みた。しかし、培養細胞に受容体を発現させて機能を見るという一般的な方法ではうまくいかなかった。1998-99年にかけて、筆者らの研究グループを含めた世界4グループがほぼ同時に機能解析に成功し、BuckとAxelが発見した遺伝子群は、嗅覚受容体をコードしていることが実証された。方法としては、筆者ら2グループは、アデノウイルスを使って嗅覚受容体遺伝子を嗅神経細胞に導入して発現させて機能を解析する方法をとった。また、ひとつのグループは、嗅覚受容体のアミノ酸配列を改変して細胞膜発現を成功させ、残りのひとつのグループはアフリカツメカエル卵母細胞を使った機能解析で成功している。
発見からノーベル賞まで
機能の実証研究から5年後、2004年、BuckとAxelは「for their discoveries of odorant receptors and the organization of the olfactory system」(におい受容体および嗅覚神経系の構築メカニズムの発見)でノーベル生理学医学賞を受賞した。嗅覚受容体発見の1991年当時、BuckはAxel研のポスドクであった。普通は実際に実験をやった学生やポスドクがノーベル賞の対象になることはほとんどないので、極めて異例なケースといえよう。ただ、Buckは1991年にハーバード大学で独立後、Axelと並んで嗅覚神経回路の解明に多大な貢献をしている。具体的には、単一嗅神経細胞には1000個もの嗅覚受容体のうち一種類のみが発現している、そして同じ嗅覚受容体を発現する神経は軸索を嗅覚の一次中枢である嗅球の特定の糸球体に収束させているという、匂いを識別するために重要な神経回路を、Axelらとともに独自に発表している。そもそも、Axel研で嗅覚の研究を独自に立ち上げて成功させたのはBuckであり、誰が見てもBuckが同時受賞するのは当然であった。一方、BuckもAxelももともとは免疫学者である。後に嗅覚研究に参入した坂野仁氏(東大名誉教授)もAxel研出身のPeter Mombaertsも、利根川進氏(MIT)のところで免疫研究をしていたという共通点は興味深い。ところで、Axelは、70年代後半に、カルシウムを使って培養細胞にDNAを導入して形質転換させる方法を開発し、その技術の特許でコロンビア大学は年間一億ドルもの利益を得たと言われている。Axelは嗅覚でノーベル賞をもらわなかったら、こちらのほうでもらっていたかもしれない。
においを識別する神経回路
におい分子は、理論的には数十万種類もあると考えられている。これだけたくさんのにおいを区別したり識別したりできる仕組みはなぞであった。嗅覚受容体の発見と機能解析の成功によって、ラットで1000種類ほどある嗅覚受容体ひとつひとつは、ある特定のにおい分子だけでなく、構造的に類似した複数のにおい分子も認識できることがわかった。また、ひとつひとつのにおい分子は、複数の嗅覚受容体によって認識される。すなわち、におい分子が約1000種類の嗅覚受容体のどれと結合するかという組み合わせは、それぞれのにおい分子で異なる。例えば、1000本の線からなるバーコードをイメージしてもらえれば、数十万種類といわれるにおい分子それぞれに特有のパターンのバーコードがあるといえる。その組み合わせは2の1000乗という天文学的な数字になる。つまり、その特有のコードが、ひとつひとつのにおい分子のにおいの質を決定し、生物は、そのパターンで様々なにおい分子を識別していることがわかったのである。もちろん、前述のように、一個一個の嗅神経細胞には一種類の嗅覚受容体のみが発現し、同じ受容体を発現する神経は軸索を収束させていているという神経回路があるからこそ、受容体の組み合せパターンが混ざらないで一次中枢に伝わるのである。
ゲノム時代が明らかにした遺伝子ファミリー
その後、ゲノム時代が到来し、2000年頃から、さまざまな生物の全ゲノムが明らかになってきた。そして、ヒトは約400個の嗅覚受容体遺伝子をもつことがわかった。ヒトの全遺伝子数は約2万2千個なので、嗅覚受容体遺伝子は全遺伝子の約2%である。必要ないと思われている嗅覚に関わる遺伝子が約2%をも占めるというのは驚くべきことである。その後、ほとんどの生物で、嗅覚受容体は多重遺伝子ファミリーを作っていることがわかった。魚類は50-150個ほど、両生類であるカエルは約800個、犬も約800個、霊長類は300-400個である。現時点で最大数の嗅覚受容体遺伝子を持つ生物はアフリカゾウで、約2000個である。一方、海にもどった哺乳類であるイルカやクジラには機能している嗅覚受容体遺伝子はゲノム上に存在しない。水棲か陸棲かといった生活環境、そして五感のうちどの感覚をコミュニケーションや外界の情報の収集に主に使うかということが、嗅覚受容体遺伝子の分子進化に選択圧をかけて、遺伝子数が変動してきているのである。
臨床への期待
嗅覚障害にもいろいろな原因がある。そのなかでも、嗅覚受容体遺伝子の変異による嗅盲があることがわかってきている。また、個人個人において機能している嗅覚受容体のレパートリーもかなり差があることが明らかになりつつある。こういった遺伝子多型によるものは、ある特定のにおいに対するものが多いが、近年、全然あるいはほとんど鼻が利かないといって外来に訪れるひとが多くなっていると聞く。こういう嗅覚障害に対しては、なかなか良い治療法がないのが現状だという。嗅覚受容体が発見されて、においを感じるメカニズムが明らかになってきたが、まだ医療現場へつながる知見は乏しい。ただ、BuckとAxelによる嗅覚受容体の発見以降、嗅覚分野で研究する研究者や臨床医が増えていることは確かである。今後、嗅粘膜、嗅神経細胞の再生、嗅覚中枢などの研究が進むことによって、嗅覚障害を治せるようになることが期待される。
参考文献:
・アラン・コルバン:「においの歴史」(藤原書店)
・Buck, L., and Axel, R. Cell 65, 175-187 (1991)
・Touhara, K, and Vosshall, L.B. Annu Rev Physiol 71, 307-32 (2009).
・東原和成編:「化学受容の科学」 (化学同人、2012)