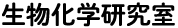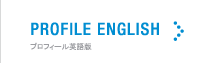巻頭言
以下は、におい・かおり環境学雑誌の巻頭言として掲載されたものです
東原和成 ┃ におい・かおり環境学雑誌 ┃ 2013年1月号
「化学感覚シグナル」という言葉
歴史を遡ると、19世紀後半に、チャールズ・ダーウィンは、動物同士のコミュニケーションには、視覚や聴覚など物理的信号に加えて、においなどの化学的信号が重要な役割を担っているという概念を提唱している。そして、同じ頃、ファーブルが、昆虫記のなかで、オスの蛾がメスに引き寄せられる現象を記述し、その現象は、視覚ではなくて、においのような揮発性の化学信号によるものだと分析している。そして、1932年、アルブレヒト・ベスが、ホルモンのような機能をもつ物質で、外に分泌されてなんらかの情報を担っているものを「エクトホルモン(Ectohormone)」と命名した。さらに、1959年、ブテナントらによる、メスカイコ蛾が放出するオス誘引物質ボンビコールの発見で、実際にエクトホルモンが存在することが実証され、種同士のコミュニケーションに使われる物質は「フェロモン」と定義された。
その後、研究は進展し、嗅覚や味覚など化学信号を受容する感覚はChemical senses(化学感覚)と総称されるようになり、その信号を媒介する物質をChemosensory signal(化学感覚シグナル)と呼ぶようになった。そして、ローレンツ以来の動物行動学の潮流が、化学感覚の研究に合流し、化学感覚のアウトプットである行動のうち、生得的なものと、経験的なもの、またそれによって引き起こされる好き嫌いなどといった情動を、神経レベル、分子レベルで語れるような時代になりつつある。まさに、それは、この20年間の分子生物学と神経科学のすさまじい技術革新による、ゲノムと脳レベルの理解の進展によるものである。最近発刊された「化学受容の科学」(化学同人)では、化学感覚研究の最先端の知見が網羅されているので、興味あるひとは参照されたい。
バックとアクセルが1991年に嗅覚受容体遺伝子を発見して以来、ちょうど20年が過ぎた。それにあわせたように、本年10月より、科学技術振興機構(JST)の大型予算である 戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)で、匂い、フェロモン、味に関しては初めてのプロジェクトである、「化学感覚シグナル」がスタートし、小生が研究総括リーダ-を務めさせていただくことになった。においやフェロモンを感じて行動が制御される脳神経回路は?においの好き嫌いの分子神経基盤は?においと味がマリアージュしておいしさを感じる仕組みは?ヒトにフェロモンはあるか、ヒトがだす体臭に意味はあるか?そもそも嗅覚の起源はどこにあるのか?ようやく、視覚や聴覚だけでなく、嗅覚や味覚などの化学感覚の学術的重要性が認知されてきたといえる。
化学感覚は、ほとんどの動物にとっては、敵味方を判断するなど、生きていくために必須の感覚である。一方、われわれ人類は、料理のおいしさを感じたり、花や新緑の香りで季節感を感じたり、お香でリラックスしたり、ちょっと贅沢な化学感覚の使い方をしはじめている、ある意味進化しつつある動物種である。つまり、化学感覚を理解することは、学術的な意義があるだけでなく、人間社会への実用・応用面などの展望もある。また、バランスの良い五感を育む教育が求められているという側面からも、化学感覚に関する研究に対して、今後、大いに期待が高くなっていくのは間違いない。