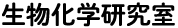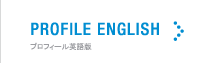寄稿
以下は、内藤財団時報に寄稿したものです
東原和成 ┃ 内藤財団時報 ┃ 2011年第87号
研究立ち上げに走った10年間
研究奨励金をいただいた10年前、日本帰国後立ち上げた嗅覚研究の初めての論文がPNASにでてからまだ間もないころで、私はまだ嗅覚研究者として認められていなかった。なかなか研究費も当たらず、一匹狼で新しい研究を立ち上げる際の厳しさと自分の申請書作成能力のなさを感じては苦しい時期であった。そんな時代にいただいた奨励金の嬉しさは今でも支えになっている。
その時に植えた研究の種は、がんばり屋の学生さん達の力で大きく育ち、Nature 3報、Science 1報を含む30論文ほどの成果となっている。成果がでると同時に、学生は卒業する。せっかく実験が上手になり、ロジカルシンキングができるようになりプロダクティブになったときにでてしまうのはこちらとしては痛手だが、その成長を見るのが指導教員冥利につきる。それが嬉しくて、やはり学部生が来るところがいいと願っていたところ、昨年12月から古巣の東大農芸化学に戻る幸運をいただいた。
現在私が担当している生物化学研究室は、1893年に東京大学に農科大学が設置され農芸化学科ができたときの3つ講座のひとつである。初代の教授はオリザニン(ビタミンB1)を発見した鈴木梅太郎先生である。柏キャンパスからのラボの引越しは今年の3月におこなったが、研究室の倉庫から貴重なサンプルが見つかった。鈴木先生が単離したオリザニンの結晶などのサンプル群が納められた箱である。そこには、「ビタミンB1の発見:このケースを三組作り、一組は皇室に献上し、一組はドイツ学士院に贈った」と記載されている。伝統をよいプレッシャーにして、自分が培ってきた研究基盤をもとに、農学に資する嗅覚研究を推進したいと思う。
さて、この10年間走ってきた過程で感じたこととして、サイエンスでいい仕事をするためのキーワードは、Question, Approach, Logic, Colorの4つであると思う。自分の研究環境を見て、今できることは何か?という視点から研究をするのではなく、何が現在その領域で本質的なquestionなのか?というスタンスでテーマ設定をすること。Approachに関しても、自分達が持っている技術で何ができるか?という考え方をしがちだが、そうではなく、自分のたてたquestionに対してベストのapproachは何かと考えて、その技術を自分で立ち上げる態度でのぞむこと。日本人は英語が母国語でないから論文を書くのにハンディがあると思いがちだが、それは言い訳にすぎず、共通の国語力がlogicの強い研究成果および論文をだすのに必要であるということ。そして、独立したとき、それまでの仕事を引きずらずに、自分のcolorのある研究を立ち上げようと思うこと。この4つのキーワードがきちんとしている論文は芸術作品のように美しいものである。
鈴木梅太郎先生は、留学から帰国時にフィッシャー教授から「欧米には追いつけないのだから、帰ったら東洋でしかできないことをしなさい」と言われ、そこで米の研究を始めたのがビタミンB1の発見の契機になったと言われている。もうそのような時代ではないが、独立研究者として日本から世界に通用する研究成果を発信するためにはどうしたらいいか、いつも思案にくれている。