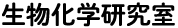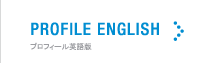コラム
以下は、「ワイナート」2010年1月号に掲載されたコラムです(京大伏木先生と見開き連載第5弾)
東原和成 ┃ ワイナート ┃ 2010年1月号
ワインと料理のマリアージュの科学
ワインの品評会では、ワインそのものの色、味わい、香りなどでワインを評価する。しかし、ワインは、もともと食事とともに楽しむお酒であり、それだけで完成されている必要はない。例えば、それだけではたいしたことはないが、天婦羅とあわせたら、お互いの風味を引き立てるようなワインもある。また、海の幸の臭みを消すような効果をもたらすワインは、それはそれで相性がいいといえる。料理あってのワイン、ワインあっての料理という、本来のワインの位置づけは忘れがちである。
日本酒にしても同様である。日本酒の品評会というと、ほとんどが大吟醸であり、香り高く、雑味のない、すきとおったような日本酒に評価がいく。それだけを飲むのであれば大吟醸は素晴らしいお酒である。しかし、往々にして、香りの主張の激しい大吟醸は、洗練された日本の料理の風味とぶつかる。伏木教授が前号で述べた通りである。
ワインと料理のマリアージュ。最近、よく使われる、ちょっとかっこいい粋な言葉である。マリアージュという言葉は、英語で「結婚」という意味であるが、ワインと料理が合う、相性がいい、というときに表現する言葉である。ワインの造り手も、一緒に食べる料理を思い浮かべながら造るといいし、飲むほうも「このワインはどの料理とマリアージュだろう」と思いながら飲み食べすると、食の愉しみも格段と広がる。
では、マリアージュの科学的根拠はなんであろう。ワインと料理が合うときは、味(味覚)や香り(嗅覚)どうしの相性がいいときであることがほとんどである。相性がいいときは、良い風味が新たにできたり増強されるとき、あるいは、悪い風味が抑制されるときである。相性が悪いときは、良い風味が抑制される、あるいは悪い風味が新たに作られたり増強されるときである。
これらの相乗や抑制の現象は、口腔内での味物質や香り物質などの化学反応、それらの物質を認識する受容体レベル、そして、それらの情報を統合する脳レベルといった三つのレベルでおきている。化学反応の現象の例としては、ソーウ゛ィニオンブランの黄色香のように、ワイン中の物質が唾液の酵素と反応して新たな香り物質が生まれたり、白ワインと魚介類のようにワインに含まれる物質が食材の物質と反応して新たな臭み物質がうまれたりする。受容体レベルでは、ワインと食材に含まれる香り物質の相乗効果が起こり、良い香りをより強く感じさせたり、一方で、受容体の鍵穴をお互いにふさぐことによって悪い香りの抑制がおきる。脳レベルでは、香り情報の統合の際に、神経活動の相乗および抑制がおきる。
こういったメカニズムを考えると、相乗や抑制現象というものは、往々にして、同じような構造をもつ香り物質同士でおきる。また、香りや味物質だけでなく、なかに含まれるミネラル(金属類)にも影響されるので、ブドウや食材の作られた土地の環境(土や水)も重要な因子である。地産地消とはいうが、同じ土地環境で作った食材同志は相性がいいというのも、科学的に理にかなったことであるといえる。
当然、自然酵母で作った自然派ワインは、その土地の料理と合う確率は高くなる。それだけでは癖のある自然派ワインは、料理とあわせると、とんでもないワインに化けることもある。私がワインを飲む理由は、この突然化けるワインに出会いたいから。その瞬間が何よりの至福である。先日、イタリア出張で、イタリアワインとイタリア料理を楽しんだ。そして、帰国して、日本のワインと日本料理を楽しんだ。その土地その土地でのワインと料理のマリアージュは、味と香りの相性を基盤に生まれる、高度生命体である人間の感性のなせる技なのである。