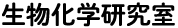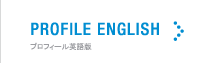コラム
以下は、「ワイナート」2009年7月号に掲載されたコラムです(京大伏木先生と見開き連載第2弾)
東原和成 ┃ ワイナート ┃ 2009年7月号
鼻先と喉から味わう香り
「原始人の嗅覚は文明人の嗅覚より優れており、進化とともに人間の嗅覚は解剖学的にも機能的にも退化した」。チャールズ・ダーウインの言葉である。確かに、人間は、ネズミや犬に比べて、鼻のなかで匂いを感知する嗅上皮の面積は小さいし、匂いを感知するセンサーをだしている嗅神経の数も圧倒的に少ない。では本当に人間の嗅覚は退化しているのか。人間では五感のなかでも視聴覚が優位であるが、人間も目隠しして犬のように這いつくばってクンクン嗅ぎながら、匂いの跡をたどることができるほどの嗅覚能力を持っていることが実験でも示されている。
また、人間にしかできない嗅覚能力がある。私たちは、肺への気道と胃への食道が、喉で交差しているため、呑み込むときに喉から鼻へ抜ける匂いを感じることができる。鼻をつまんでものを食べると味もそっけもないのも、この喉の構造が原因である。ワインを聞くとき、まず鼻先から入ってくる匂いを楽しみ、次に口に含んで舌のうえで転がして飲みながら、喉越しから鼻にぬける匂いを楽しむ。前者を「たち香」(オルソネーザル)、後者を「口中香」「あと香」(レトロネーザル)などと言うが、この2つの経路からの香りの楽しめるのは人間だけである。興味深いことに、同じチョコレートの匂いを嗅ぐのでも、鼻から嗅ぐのと喉ごしから嗅ぐのとでは、脳の反応部位に違いがでる。私たちは、「たち香」より、喉ごしの「あと香」で美味しいと感じているようである。
匂いは、常温で気化しやすい分子(物質)であるが、温度が上がると、より多くの匂い分子が空気中に飛んでくる。ワインの「たち香」と「あと香」では、匂いの強さも質も違うが、それは口中でワインの温度が上昇して、より多くのワイン中の匂い分子が気化してくるからである。また、湿度も大きく影響する。湿度百パーセントの口のなかでは、喉越しからあがってくる「あと香」には、「たち香」にはないより多くの種類の匂いが含まれる。また、ソーヴィニオンブランのように、唾液中の酵素と反応して、新たな香りができあがることもある。このように、鼻先からの「たち香」を感じ、喉越しからの「あと香」の変化を楽しみ、そこに咀嚼によって食べ物のなかからでてくる香りが出会い、マリアージュする。ワイン好きにとっては至福の瞬間である。
さて、フランスで美味しいと感動したワインを、日本に買って帰ってきて開けて「たち香」を嗅いでみると、あれ、こんなワインだったかな?と思った経験のあるかたも多いのではないかと思う。本場と空間が違うという心理的なものも大きく影響するが、これも湿度のイタズラのこともある。前述のように、湿度が違うと、気化して飛んでくる匂いの種類も量も違うので、違った香りに感じる。乾燥したカリフォルニアでは心地よい革ジャンの匂いが、日本の梅雨の時期にはいやに鼻についたりするのも同じ理由だ。また、高山のように気圧が低くて空気が薄くてきれいなところでは、あまり匂いがたたない。気圧も湿度も低い飛行機のなかでは、ワインの風味も異なる。このように、土地の気候や地理的環境によってワインの「たち香」は大きく変わるのである。
ダーウィンは、環境要因などによってその土地に適した生物が自然選択され、生物の多様性が生まれるとしているが、一方で、育種家などの人為選択による進化も存在すると言っている。テロワールという言葉にあるように、土地の気候などブドウを取り巻く環境によって、生産されるワインに多様性が生まれると同時に、そこにいる生産者の「力」も大きく影響する。さらには、今回紹介したように、風土の違いによって、ワインを飲むときの「たち香」の匂いの多様性をもが創りだされる。それは、とりも直さず、ワインは、それをとりまく人間や環境に応じて変化しうる「生き物」だからなのである。