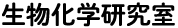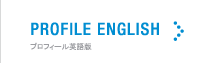コラム
以下は、「化学」2009年6月号に掲載されたコラムです(連載第6弾、最終回)
東原和成 ┃ 化学 ┃ 2009年6月号
評価システム、学生支援、そして意識改革
近年、報告書そして評価と書類まみれである。競争的研究費の成果報告と評価、大学の教育研究目標とそれに対する評価など。評価をすることもされることにも慣れていない日本人は悲鳴をあげている。しかし、元来、あうんの呼吸であいまいに物事が進むのが日本人の良いところでも悪いところでもあったが、それでは分野外のひとに説明がつかない。きちんと評価をしなければ、もとはといえば税金である研究費が無駄になることもあるだろう。研究の透明化をはかり、研究者としての責任感と意欲を持続させるためにも、評価システムは必須である。
ところが、評価のための報告書作りで研究の時間が圧迫されるなど、本末転倒的になっているケースが多い。さらには、それだけ時間をかけて報告書を作っても、きちんとした評価がなかなかできていないと聞く。それは、欧米人は小さいときから自分の主張をして議論をすることによって絶対的な評価ができるような教育を受けているのに対し、日本人は、相対的な観点から自分や他人を見て、比較することによって評価をしてしまうことが多いことが原因のひとつであると思う。一方で、書類をつくれば安心してしまう日本人の気質もあろう。今後、効率良く、かつ健全に行われる評価システム構築が望まれる。
さて、すこし話しがずれるが、アメリカの大学院では、学生の多くが授業料免除と奨学金(給与)をもらっている。大学によって多少違うものの、月に10万円程度。この額は、シャワートイレ共用の大学寮に入って、必要な教科書等を買い、栄養失調にならない程度に食べ、そして、毎週末ささやかなビールパーティーと5ドルの映画で息抜きをしながら、毎日勉学と実験に勤しむのに必要な最低限のサポートである(筆者の経験談)。最近は日本でも博士課程の学生は、TA, RAに加えて、COEとか大学からサポートがでるようになっている。まだまだ全員が十分生活していけるほどの金額のサポートからはほど遠いが、大学法人化以降、日本の大学でも資金運用面がしっかりしてきており、いずれかなりの学生がサポートをうけられるようになるだろう。このような時代になると、奨学金の評価システムの構築が必要になってくるだけでなく、もらえる学生側の意識改革も必要になってくる。
アメリカの大学院生は博士をとりに真剣勝負でいく。就職か博士かなどという選択肢をもちながら大学院に入らない。また、大学に入るときから親から金銭面では独立して自立するカルチャーがあるので、奨学金に対する責任的意識も高い。一方、日本では比較的親のサポートが寛容なので、奨学金もお小遣い的な感覚でついもらってしまう。つまるところ、奨学金制度が充実してくればくるほど、もらう学生側の意識改革も必要になってくる。会社でもらう給料と違って、大学院でお金のサポートをうけるとすれば、それは研究生活を充実させるものである。博士をとる、立派な研究者になるという目標のためのものである。
大学法人化以降、各大学がイニシアティブをとって様々な教育制度を導入できるようになっている。アメリカの研究環境や大学院教育制度のいいところを学ぶのはいいが、カルチャーが違う日本にそのままで導入するとひずみがでて破綻する。ポスドク問題などはアメリカかぶれの結末である。日本の伝統と欧米制度を融合させた新日本バージョンが望まれる。いろいろ課題は多いなか、適切な評価ができるような考え方の確立と、大学教員側と学生側の両者の意識改革とが、今、大きく変遷しつつある日本の研究社会に求められているのでは、という提言で本連載を締めくくろうと思う。