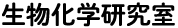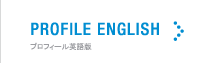コラム
以下は、「化学」2009年3月号に掲載されたコラムです(連載第三弾)
東原和成 ┃ 化学 ┃ 2009年3月号
アイデンティティを探しに国際学会
私はアメリカの大学院に留学したので、はじめての国際学会はアメリカの「国内学会」であった。私のなかでの国際学会の定義は、いろいろな国の世界のひとが一同に集まり、それぞれの価値観や文化をぶつけあえる学会である。だから、アメリカの「国内学会」はそれ自体で国際学会となっている。学生が国際学会を一度経験すると化けるとよくいうが、これ本当であり、ほぼ単一民族である日本人がはじめて経験する国際社会だからである。だから、日本も負けじと多くの学会を英語発表にしつつあるが、私としては、いくら英語で発表をしても、いくら外国人スピーカーを招待しても、地理的にも文化的にも精神的にも日本の学会は決して国際学会にはならないと思う。私は母国語で学会をやる意味もあると思っていて、日本の学会を無理してすべて英語にする必要はないと思っている。要はいかにして日本の学会を国際社会的な意識のレベルにするかである。
私は1996年に助手として日本に帰国して、現在の嗅覚研究をひとりで立ち上げた。もちろん最初はうまくいかず、ようやく成果がでだしたのは2年後くらいである。その間、国際学会はもちろん国内学会にもいかなかった。学会は研究領域の同業者達と出会って世界を広げ、刺激しあって研鑽しあって自分を成長させることができる場である。しかし、発表しないで参加するのと発表するのとでは大違いである。ただ勉強したいのであれば、論文や総説を読めばいい。当時、私が意固地になって学会にいかなかったのは、多少極端な考え方ではあるが、データをもっていないのなら自分のこの領域での存在価値がないと思っていたからである。ただ学会を取材するサイエンスジャーナリストではない。国際学会とは、自分の研究成果を発表して議論することによって、自分の研究者としてのアイデンティティというものを確認できる場でもあるからである。
自分がこつこつ積み重ねてだした実験結果を世界のひとに見せて評価してもらえると、嬉しくて脳内ホルモンが分泌され、発表ごとに快感とともにやみつきになっていく。すると、ややもすると学会発表するために実験をするという動機になりがちである。それはそれでいいと思うが、一方で、いくら国際学会で発表しても、原著論文を書かないと後世にその仕事や成果は残らない。だから未発表のデータを国際学会でポスターや口頭発表で迂闊にだしてしまうのは往々にして危険である。研究者にとって、メインディッシュは論文、学会はスパイス程度に。
ともあれ、国際学会の楽しみのひとつとして、なかなかバケーションがとりにくい大学人にとっては貴重な観光のチャンスでもある。異国の街並や文化に触れることは、ある意味、何でも屋さんである研究者としての人間の知恵の幅を広げてくれる。また、国際学会は、ポスドクやファカルティーのリクルートとか平気でおこなわれる場でもあるので、そういったチャンスも是非活用したいものである。