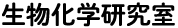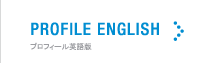解説
以下は、「香りの愉しみ、匂いの秘密」ルカ・トウーリン著、山下篤子訳(河出書房新社)の解説の一部改変したものです
東原和成 ┃「香りの愉しみ、匂いの秘密」┃ルカ・トウーリン著、山下篤子訳(河出書房新社、2008年)
解説-「香りの愉しみ、匂いの秘密」
匂いは心地よいというよりかは不快なものと考えられがちだ。特に、衛生志向の強い日本では匂いの排除が顕著で、これほど消臭剤が売れている国はないという。確かに腐っているものは悪臭を発するので、「匂う=不衛生」という方程式はある程度当てはまるが、匂いそのものは病気を媒介するものではない。また、「匂い=くさいにおい」は間違えで、「におい」を辞書でひくと、芳しい香り、悪臭、輝かしいさま、おもむきと様々である。匂いは、季節感を感じる芳しい香りや至福感を与える料理の香りなど心地よい香りと、どぶ川や汚物から発する不快な臭いと、良い匂いと嫌な匂いの両方の意味を含む嗅覚感覚を刺激するニュートラルな物質としての意味をもつ。
いわゆる「くさい」という感覚は、個人差があり心理的なものでもある。例えば、納豆の匂いを嫌いなひとと好きなひとがいるし、納豆の匂いが好きなひとでも、実は足の裏の匂いですよ、と言われると、同じ匂いなのに心理的に嫌悪感を感じる。このように、匂いというものは、曖昧で表現の仕方も難しいものであることに加えて、心理的生理的な効果をもたらす力をもっているので、古くから神秘的なものとして扱われてきた。
そんな不思議な感覚である嗅覚のメカニズムは、匂いを感知するセンサータンパク質(嗅覚受容体)の発見によってにわかにそのベールがはがされた。そして、嗅覚受容体の情報をコードする遺伝子を発見したリチャード・アクセルとリンダ・バックの二人は、2004年にノーベル医学生理学賞をもらっている。それは、鍵と鍵穴の関係のように嗅覚受容体が匂い物質の形や構造を認識することによって、多種多様な匂いを感じることができるという仕組みである。しかし、これで嗅覚の全貌が明らかになったと考えられているが、これでは説明できない現象がたくさんある。それを説明するには別のメカニズムの存在が必須である。そのように主張しているのが、本書の著者であるルカ・テューリンである。
歴史をさかのぼって匂いに関する記述を探してみると、古代ローマの哲学者であるルクレチウスが、「匂いというものは、原子のつながった分子でできていて、分子の形や大きさの違いが、匂いの質の違いを生む」と記述している。現在の匂い物質に関する知見を如実に表した的確な表現である。その科学的根拠は、前述の嗅覚受容体の発見によって明らかになったが、一方で、「形」だけでは説明がつかない匂いの不思議を説明できるのが、分子振動説というものであるとルカ・テューリンは主張する。分子振動説というものがどのような説なのかは、本書と、彼のサイエンス界での活動のドキュメンタリーともいえる既刊書「匂いの帝王」(早川書房)で詳細に記載されているのでここでは説明しないが、量子化学あるいは量子物理学の観点から見れば、確かに説得力のある部分もある。しかし、一方で、そのためには鼻のなかが「分光器」になっていなくてはいけないという主張にはやや無理がある。ただ、視覚と聴覚と並んで、匂いの嗅覚を「分子振動」という物理信号として共通概念にとらえているところは、まさに、ボードレールが「万物照応」で色、光、音、匂いのアナロジーを詠っているのと同じ考え方でもあり、科学的には無理があっても、人間の心を振るわせる哲学的そして美的な力を感じる。
実をいうと、私はルカ・テューリンという人物には会ったことはない。会ったことがないのに、私は彼のことをとてもアグレッシブで攻撃的なひとだと思っていた。というのも、「匂いの帝王」では、アクセルやバックをはじめとする私の友人達を、実名や匿名で中傷をしている。ところが、今回の本を読んで、その印象はまったく変わった。もっとも、「匂いの帝王」はジャーナリストが書いたものであり、嗅覚にまつわる内容そのものが評価されたというよりは、その英語の語り口が巧妙でベストセラーになったとされている。一方で、本書は、ルカ・テューリン自身が書き下ろした、嗅覚のメカニズムを解明したいという彼の執念の歴史がつづられている力作である。さらには、香りに興味をもっている方々にはとても参考になる内容である。
嗅覚研究において匂いと構造を考えるときに、生物学、物理学、化学の3つの領域をおさえないといけないが、最近の最先端の嗅覚研究を進めている研究者達の多くは、香りの分子構造などには見向きもしない。ルカ・テューリンは、本書で、香りの不思議を身をもって実感して、その化学的な視点から嗅覚の研究を始めたと語る。その経験から織りなす個々の香りの表現はとてもユニークでわかりやすく、例えば、香水が作り出す匂いの空間を「化学の詩」と表現したり、「ランドスケープ」と呼んだりしている。様々な匂いや香りを知っているひとなら、本書を読みながら、「香りの大合唱」をその場で経験できるだろう。もっとも、その匂いを嗅いだことのないひとにはなかなかピンとこないかもしれない。そういう意味では、本から匂いや香りがでてくればなんとよかったことかと思わせる。
嗅覚は、香りが作り出す不思議な化学の世界だけでなく、過去の記憶や風景が瞬時にして匂いによって呼びもどされるといった高次脳機能に関わる脳科学の分野でも重要なターゲットである。そして美味しさや嗜好につながる脳内回路との関係で食品科学との関連性も深い。さらには、微生物から高等動物までのほとんど全ての生物は、嗅覚を使って食べ物を見つけてエネルギーを獲得し、また、嗅覚を使って交尾相手を認識して子孫を残す。このような栄養学や生態学との関連を考えると、生命の本質を理解するための近道の研究領域でもある。本書で、ルカ・テューリンは、化学と物理の視点から香りの不思議さと魅力を、彼の人生観とからめて力説するが、生物学の視点を加えるともっともっと嗅覚の重要性を知ることができる。
嗅覚は感覚のすべてを支配してしまうようなポテンシャルをもったものであり、顔面に威風堂々とそびえたつ鼻を制するひとは、人類の本質を制すると言っても過言ではないかもしれない。日本でも、イザナギが穢れを落としたときに鼻から生まれた神である須佐王尊は、現世と来世をいききできる特別の神であった。そういう意味では、嗅覚のメカニズムの解明に大きく貢献した嗅覚受容体遺伝子を発見したアクセル&バックは、文字通り「匂いの帝王」なのかもしれない。ただ、私が思うに、あえて「匂いの帝王」は誰であるかを決める必要はまったくない。科学の飛躍的な進歩がいずれ全貌を明らかにするであろうというルカ・テューリンが最後にしている主張に同感する。確かに、「形」として匂いという鍵が嗅覚受容体の鍵穴にはまるまではよいが、そのあと「何かが鍵をまわさなくてはならない」。そこは未知の領域だ。匂いと嗅覚受容体の関係だけでなく、薬の受容機構にも関連する普遍的なメカニズムであると予測される。ルカ・テューリンは、創薬における薬のデザインと香料化学界における香りのデザインに共通性を感じている。
嗅覚に関して、特に匂いというものに関しては、冒頭で述べたように、人間社会のなかでは誤解だらけで、そのせいで、匂いがいじめの原因になったり、口臭を気にしたり、異常なほどの消臭をしたりする。一方で、アロマセラピーなど香りに求めることも多い。こういった匂いにまつわる様々な社会現象は、老若男女問わず、匂いや嗅覚に関して正しい知識と意識を持てば解決することである。毎日の食生活で美味しいと至福な幸福感を得られるのは、香りがあるからである。本書では、食における香りの意義についてあまり述べられていないのが残念であるが、料理を口に含んだとたんに発する様々な香りと、ワインやお酒との華やかな香りのマリアージュは、コンピュータと情報の社会の喧噪から私たちにほっとした癒しを与えてくれる。身近にありながら、その恩恵をたくさん受けていながら、軽視され排除されがちな匂いや香りの重要性をいまやもう一度再確認する時代が到来している。そんな気持ちを持たせる香り高い読み物である。