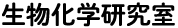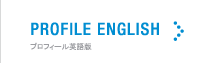雑誌掲載
以下は、「ミクロスコピア」2007年第四号に掲載された原稿を若干改変したものです
東原和成 ┃ ミクロスコピア ┃ 2007年第4号
匂いとフェロモンの不思議 -その受容メカニズムに挑む-
私の匂いとの出会いは、大学の卒論実験に配属された有機化学研究室である。慢性鼻炎気味だったので、それまで匂いや香りというものを、とくに意識したことがなかったが、研究室にある溶媒や合成品の匂いがとてもバラエティーに富んでおり、多種多様であることに驚いた。なぜ、私たちは匂いを感じるのか?なぜ、これほど、いろいろな匂いがあるのか?そんな素朴な疑問を抱き、それと当時に、研究室で合成されたフェロモンの、わずかな構造の違いを鋭敏に識別する昆虫の嗅覚能力にも魅了された。こうして、匂いの不思議が私の学問的な興味をひきつけていった。
化学から生物へ
昭和が終わり、天安門事件・ベルリンの壁崩壊が起きた激動の1989年、大学を卒業した私は、すぐにアメリカ大学院に留学した。そして、研究室で生理活性物質(ホルモンやフェロモン)を合成するだけでなく、作った「もの」の作用を自分の手で調べてみたいという欲求から、生化学の分野へ入っていった。それ以来、一貫して私の胸中にあるのは、「生理活性物質が、どのようなメカニズムで受け取られるのか」、すなわち、受容体のしくみへの興味である。
1991年、コロンビア大学のリチャード・アクセルとリンダ・バックが嗅覚受容体遺伝子を発見して「セル」誌に発表した。この発見は、卒論時代の私の素朴な疑問に答えるものであったのと同時に、私はこの論文に深い感銘をうけ、嗅覚の研究を決意したのである。もっとも、この決意を実行できたのは、5年後の1996年、東京大学医学部脳研究施設の助手として帰国したときである。
一念発起、覚悟の立ち上げ
嗅覚研究をはじめるにあたって、まず、やらなくてはならない関門があった。バックとアクセルが見つけた遺伝子から翻訳されて細胞膜に発現する蛋白分子が、本当に匂い分子を認識して細胞内にシグナルを発する匂い受容体であるのか。それを実証する実験であった。当時、嗅覚受容体は、培養細胞の表面に出現させて匂いに対する応答を測定することが極めて困難であり、遺伝子の発見から5年たった1996年に至っても、まだ誰も、受容体の機能を実証する実験には成功していなかったのである。
そこで私は、一つの嗅細胞には一種類の嗅覚受容体しか発現していないという分子生物学的な証拠をもとに、単離した匂い応答細胞から嗅覚受容体遺伝子をクローニングするという、これまでの研究法とは正反対のアプローチをとることにした。そのためには、鼻の周辺の解剖を学び、嗅細胞(匂いを受容する繊毛をもつ神経細胞)を取り出す技術を学ぶ必要があったし、刺激を受けた細胞のカルシウムイオンの増減を計測するカルシウムイメージング装置、一個の細胞を釣りあげるためのマニュピレーターなど、一連の装置も必要だった。多くの研究者は、ポスドク時代の仕事を持ち込んだり、移動先で可能な範囲内で実験をするのだが、私の場合は、経験も技術も何もない、一からの立ち上げだった。もちろん、数年成果が出ないことは覚悟の上だった。しかし、立案から実験まで、すべて自分がやった仕事に対して、評価がほしい。そんな思いを抱いて、戦士として加わってくれた、ひとりの大学院生とともに前進した。
嗅覚研究の第一報へ
嗅細胞を取り出してカルシウムイメージングにかける技術は産総研の方々に教わり、高価なカルシウムイメージング装置は農学部の共通機器を借り、マニュピレーターは、なけなしの研究費で買い、なんとかスタートした。マウスの嗅上皮の取り出しは医学部3号館でやり、農学部に細胞を持ち込み、イメージング後は医学部にもどり、逆転写PCR(DNA増幅)反応をやるという、東大本郷キャンパスを何往復もする作業を毎日やった結果、一年後には、ある特定の匂いを認識する嗅覚受容体の候補を、いくつか単離することが出来た。そして、そのなかのひとつがリラールというスズランの香りを認識する受容体であることを実証した。
世界ではじめて嗅覚受容体の機能が実証できたと意気込んで、さて、論文投稿!と思った矢先に、1998年1月、コロンビア大学のファイヤースタインのグループが、I7というラットの嗅覚受容体を活性化する匂い物質 を同定したという論文をサイエンス誌に発表した。それでもめげずに二日で論文を書き上げ、ネーチャー誌に投稿、査読に回ったものの、サイエンス論文が発表された直後だったせいかリジェクト。すぐに米国科学アカデミー紀要(PNAS)に送る。しかし、ここでハマった。いつのまにか産総研の共同研究者が競争相手のリンダ・バックに情報を流し、私たちがやってきたのと同様の研究を、彼女と一緒にやりはじめていたのである。PNASの査読者のひとりは、ほかならぬリンダ・バック。論文を一年近くとめられて、結局、彼女たちは私たちの論文と同月にセル誌に発表。日本から裏切り者がでたことよりも、アメリカという大国のパワーに屈したことの悔しさのほうが大きかった。しかし、私たちのPNAS論文は後になって大きく評価され、結果的には、世界の嗅覚研究者が、私たちの存在に気づいてくれるきっかけとなった。でも、いつかは必ず、日本からいち早くトップジャーナルに発表できる、いい仕事をすると誓ったのである。
助教授ポジションを得てテーマを拡張
ひとりで実験をやるのは限界がある。色々なことに挑戦するために、なんとかチームを作りたい。指導できる大学院生をもちたい。そう願うなか、幸いにも、1999年、現ポジションにつくことが出来、2000年春には卒論生を含めて7~8人というチームを持つことが出来た。それまでは、マウスの嗅覚受容体に関連する研究に絞ってきたが、仲間が増えたので、暖めていたいくつかのテーマに取りかかることが出来た。
嗅覚受容体を培養細胞に発現させる方法の改善や、嗅細胞の匂い応答を計測する新しい方法の確立、嗅覚受容体分子のどの部分が匂いを認識するのかなどの他に、新たにいくつかの研究をスタートさせた。精子に発現する嗅覚受容体の機能、マウスのフェロモン、昆虫の性フェロモンの受容メカニズム、植物の匂いの問題などである。
どのテーマもチャレンジングなものだったので、手法の立ち上げには時間がかかった。どれも手探りで進めたこともあり、協力してくれた学生たちは私の指導方針に不安や焦りを感じたのではないだろうか。しかし、指示通りにいくような課題は、誰でも出来るものであり、つまらないものであると思う。当時の学生たちは、今や皆、国内外に羽ばたいているが、私のもとでいい経験をしたと思ってくれていると信じている。
マウスの嗅覚受容体の働きぶり
当時、嗅覚における本質的な問題として、数十万種類あると言われる匂い分子と、数百種類の嗅覚受容体は、どのような対応関係になっているのか、匂い分子と嗅覚受容体の相互作用のメカニズムはどのようなものか、という二つの大きな課題があった。
第一の問題に対しては、上記の単一細胞機能的クローニング法によって、ひとつの匂い分子が複数の受容体によって認識されることを実証することが出来た。こうして、受容体の組み合わせで匂いが区別されるということが分かって決着がついた。
第二の問題は、コンピュータモデリングとアミノ酸に変異を導入した受容体の機能解析を組み合わせることによって、匂い分子は、受容体分子との疎水的相互作用によって認識されていることが明らかになった。分子振動説や吸着説など様々な説が提唱されていたなか、匂い分子は立体構造によって認識されるという、立体構造説が正しいということを実証することが出来たのである。また、この結果から、他のGタンパク質共役型受容体の研究にも役立つ知見を提供することが出来た。
最近は、研究を脳のレベルにひろげ、嗅覚の一次中枢である嗅球における匂い応答を、生きたマウスで測定する実験系を確立した。そして、嗅球から逆行性に色素を導入する手法を使う、新規の嗅覚受容体遺伝子のクローニング法も開発し、より詳細な匂い感知メカニズムの解析が可能になった。嗅覚受容体という蛋白分子の機能解析とそのシグナル伝達に関する私たちの成果は、嗅細胞における匂い認識機構を解明するのに貢献できたと思っている。
精子の嗅覚受容体は何を嗅ぐのか?
嗅覚受容体は、鼻だけにあるのではなく、精子にも存在していることが、1992年に報告されている。匂いやフェロモンは、雌と雄が出会うために必須だが、精子と卵子の出会いにも必要であるとしたら、とても楽しい。そう思い、私たちは、精子に発現している嗅覚受容体が、どんな物質を認識する(嗅ぐ)ことが出来るか、探索をはじめた。手はじめにマウスの嗅覚受容体の匂いリガンド、つまり鼻が感じる匂い物質を精子にふりかけてみると、カルシウムイオン濃度が上昇する。そして、精子の運動性に影響を与えていそうだ。
それでは、体内の物質で精子を刺激するもの(内在性のリガンド)がないだろうか?よし、それを見つけようと思った矢先に、ドイツの研究グループがサイエンス誌に、ヒトの精子は匂いに惹きつけられるという結果を発表した。私たちは内在性のリガンドを見つけてから投稿しようと思っていたのがまずかった。とりあえず、マウスの精子の嗅覚受容体の匂い応答に関する論文をまとめた。精子には、いろいろな蛋白質が、機能とは関係なく無駄に発現していることが知られているので、精子の嗅覚受容体を刺激するリガンドは、身体のなかには見つからないかも知れない。しかし、きっとあると信じて、本命をねらっている。
マウスの涙からフェロモン!
哺乳類のフェロモンに関しては、まだまだ未知な部分が多い。マウスでは、第二の嗅覚器である鋤鼻器(ヤコブソン器官)がフェロモンの感知に関わっている。実際、マウスの鋤鼻器を除去すると、性行動に異常が見られる。一方、フェロモン候補物質として、異性に生理的効果を引き起こす物質が、尿からいくつか見つかっていたが、信憑性の低い論文が多かった。このような背景もあり、フェロモン受容体の機能の研究をしたかったのだが、原点にもどって、マウスの鋤鼻神経を刺激する物質を、ちゃんと同定するところからはじめた。
ブレークスルーのきっかけとなったのは、異性の床敷きに対してマウスの鋤鼻神経の興奮が見られたことである。こうして、農芸化学出身の私にとって懐かしい、「ものとり」(生理活性物質の抽出、同定)の作業がはじまった。学生ががんばってくれた。しかも、その学生は運が強く、とれた分子は今まで知られていなかった新しいペプチドであっただけでなく、巨大な遺伝子ファミリーを作っていた。
ゲノム解析が進んでいるマウスで、手つかずの遺伝子ファミリーが残っていたのは驚きである。古典的な「ものとり」でのみ見つかり、やみくもな網羅的な遺伝子解析では決して得られなかった結果である。
さらに驚くべきことに、そのペプチドは予想された尿にではなく、涙のなかに含まれていた。涙にフェロモン!願っていた日本純品のネーチャー論文である。しかし、ヒトではその遺伝子は消失している。残念ではあるが、ヒトでは鋤鼻器が退化しているので、当然の結果ではある。
昆虫の性フェロモン受容体
有機化学研究室に所属していたころから、昆虫のフェロモン受容体の構造には興味をもっていた。とくに、カイコの性フェロモンであるボンビコールは、1959年、ドイツのブテナント博士によって発見され、フェロモンという言葉が生まれるきっかけにもなったものである。また、カイコは絹王国の日本の象徴ともいえる蛾である。
ボンビコールの受容体を見つけるための実験に、私たちが選んだのは、受容体の発現の成功率が高いと言われていた、アフリカツメカエルの卵母細胞である。カエルの卵母細胞の電気生理は初めてだったので、これも、いろいろな先生方に教わってラボに導入した。
これが当たった。京都大学の西岡孝明先生と共同研究で、候補遺伝子を導入してみると、わずかながらもボンビコールに対する応答が見られた。心強い結果だが、効率は悪いし、応答幅も小さい。その改善は、もうひとつの嗅覚受容体を導入することによって得られた。ボンビコール受容体としての決定的証拠である。論文は、サイエンス誌に掲載された。西岡グループと東原グループの密接な共同研究の結晶である。これも日本純品の成果である。
昆虫は、哺乳類と違って、一つの嗅細胞に二つの嗅覚受容体が発現している。片方は昆虫でよく保存されているもので、どうやら膜に受容体を移行させる働きをもっているようだ。
ところが、最近、昆虫の嗅覚受容体の解析をとおして、既存の概念を覆す大きな発見をした。現在、論文として投稿して奮闘中である。
なんでもやってやろう!
この半世紀は、ワトソン・クリックからはじまったセントラルドグマの時代であり、コンピュータの高精度化に伴うゲノム解析の進行とともに、遺伝子をしらみつぶしに解析することが可能となった。しかし、これからの時代は、いわゆる遺伝子にコードされているハード情報だけでは理解できない、例えば、感性とか快不快などといった定量不可能な感覚を、どのように処理するかという、「ポストセントラルドグマ」の領域に挑戦する時代にはいったと思われる。嗅覚の不思議などは、まさにその申し子とも言えるようなテーマである。
冒頭で書いたように、私は、有機合成化学からサイエンスの世界に入った。そのときに、「物質・もの」という視点から生命現象を見ることを学んだことは、今の私の研究スタイルに大きな影響を与えている。よく「分子から行動まで」というキャッチフレーズを聞くが、本当に分子を見て、そこから行動といった個体の表現系までもっていける科学者は小数である。私は、今後も常に、「もの」という視点を忘れずに研究をすすめたい。
そして、もうひとつの私のなかの特徴として、米国大学院などマルチ社会を経験したことで、人とはちょっと変わった考え方ができるということである。こういった経験と視点に基づいた嗅覚研究は、手前味噌ながら、今年頂いたライト賞に反映したと思っている。常に、強い信念と意志をもって、貪欲に自然の摂理を解明していきたい。
最後に、一緒に汗を流してくれた、そして現在も協力をしてくれている学生やポスドクの皆さんと、お世話になった多くの先生方に感謝したい。この研究が、文部科学省、日本学術振興会、生研センター、民間財団から頂いた研究費で支えられたことも付記したい。