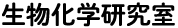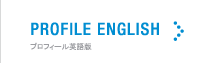雑誌掲載
以下は、におい・かおり環境学会誌に掲載された「特集にあたって」の巻頭原稿です
東原和成 ┃ におい・かおり環境学会誌 ┃ 2005年Vol.36
においとフェロモンがつむぐ空間コミュニケーション
平成13年、環境省は、全国のなかから「かおり風景100選」を選定した。豊かなかおりとその源となる自然や文化・生活を一体として、将来に残し伝えていくためであるという。興味深いことに、特に「かおり」についての選定基準はなく、自然的、歴史的、文化的な景観のなかにかおりの存在が浮かび上がるような風景であるということが選定のポイントとなっている。
感性の歴史家アラン・コルバンは著書「風景と人間」(小倉考誠訳、藤原書店)でいう。「風景の保護はある風景解釈を選択することである」。自然環境・景観保護運動のありかたに対する問題提起のなかに、周辺環境との調和のなかで地域が育んできた文脈を読み解くために、人間が親しめる無意識下の記憶、すなわち、嗅覚を含めた五感を重視する姿勢に共感できる。
かおりの風景とは、そこに住む人間達が創り出す表徴であり、人間の存在意義にもつながる風景である。畑の肥溜めも、焼き魚も、古本も、社寺も、すべて、人間の人間たるゆえんの風景であり、その存在を否定しては、人間自体を否定することになる。ランドスケープとともに最近少しづつ注目されてきているスメルスケープといわれる景観は、人間が「住める空間」なのである。
人間以外の生物にとってもにおいの風景は生存に関わる必須なものだ。多くの哺乳動物は、自分のにおいと他人のにおいを正確に識別し、自分達の生活空間・個体空間の大きさを作り出すだけでなく、交尾時期を的確に把握して種の保存に努めている。植物は動けないからこそ、独自なにおい空間を設計し、生存に必要な情報交換をしている。もちろん陸棲生物だけでない。魚は自分の生まれた川にもどるためにも嗅覚は必須であり、また、放精誘起なども水溶性の「におい」物質によって引き起こされる。そこに居住する人間達が、自然的、歴史的、文化的な「かおりの風景」を創成しているように、それぞれの生物のまわりには、我々が見えない、本能的、進化的、生態的なにおいの風景が構築されているのである。
におい物質とは、分子量30-300の低分子揮発性物質である。ただし、揮発性であれば必ずしも匂うというわけではない。例えば、二酸化炭素や一酸化窒素はわれわれ人間には感知できない。では、二酸化炭素は「におい」ではないかというと、ショウジョウバエや蚊などの昆虫にとっては、二酸化炭素も立派なにおいなのである。そういう意味では、広義でいう「におい」とは、「揮発性の分子で、空間を飛んできて、生物によって受容される物質」と定義できるかもしれない。最近問題になっているVOCもその部類に入るかもしれない。中世においては「にほひ」という言葉を光の意味でつかっている。空間からの情報という共通の意味があったのだろう。
におい分子は嗅覚受容体によって認識される。信号は脳に伝わるとともに、しばらくするとそのにおいに対しては順応して信号はオフになる。近年、分子レベルでのにおい認識とその後の受容体の脱感作・順応のメカニズムはかなり明らかになっている。一方、受容体による認識という立体構造説に対峙するものとして、「匂いの帝王」(早川書房)で有名になったルカ・テューリンが主張する分子振動説がある。分子振動説によると、普通のにおい分子と重水素化されたにおい分子とでは同じ物質でもにおいの質が異なることになる。最近、ヒトの官能試験では「No」という結果になった一方で、犬は区別できると主張する研究者もいるのでまだ決着はみていない。私個人的には、どっちかだけで全てを説明できるとは思わない。
嗅覚における分子認識は、ある意味、究極の識別センサーかもしれない。複雑な混合臭は、特有のにおいを呈し、その複雑さが、芸術ともいえる香水の存在を可能にしている。混合臭が織りなすにおいの創成メカニズムもそのベールがはがれつつある。また、嗅覚受容体は、鼻のなかでにおいセンサーとして機能しているが、鼻以外の組織でも機能していることが明らかになってきている。広義でいえば、嗅覚受容体は、一般的な化学物質センサーと考えてもよいだろう。将来、嗅覚受容体の化学センサーとしての機能をいかして、バイオセンサーの開発も夢ではない。特に、昆虫の性フェロモン受容体の解析で明らかになった、高感度・高選択性をうみだすメカニズムは、応用面に期待がかかる知見である。
フェロモンとは、「ある個体から発せられ、同種の別個体が受容し、その個体に、ある特定の行動を引き起こしたり生理的効果をもつもの」と定義される。その代表的なものが、ファーブルも記載した、メスの蛾から放出される性フェロモンによるオスの蛾の誘引現象である。この定義によると、フェロモンも必ずしも「におう」ものである必要はない。例えば、カイコガの性フェロモンであるボンビコールは少なくとも私には特ににおいはしない。昆虫におけるフェロモンの受容メカニズムに関しては、最近、受容体が明らかになって急展開をみせている。
においは揮発性で空間をとんでくる分子でなくてはいけないが、フェロモンは、必ずしも空間を飛んでくるものである必要もない。イモリなどの爬虫類、また、マウスなどげっ歯類では、不揮発性のペプチド性物質がフェロモンとして機能していて、直接接触によって個体から個体へ伝播されることが知られている。揮発性のフェロモンと不揮発性のフェロモンが鋤鼻器官で認識され、攻撃などの行動や妊娠阻害や発情などの生理的な効果が引き起こされる。近年、フェロモン分子の精製・構造決定がぞくぞくとなされ、フェロモン受容体の遺伝子も明らかになり、フェロモンの神秘がベールを脱ぐのもそう遠い将来ではない。
ヒトにはフェロモンがあるか?百億円相当の質問である。常識的に考えて、昆虫であるようなヒト共通の性誘引物質があっては大変なことになる。しかし、すくなくとも、アロマセラピーなどで知られているように、様々なにおいがヒトの身体に作用して、心理的生理的な効果を持つことが知られている。一方、フェロモンの定義をみたすためには、ヒト自体が発しているにおいでなくてはいけない。腋臭のにおいでも、体表の微生物の代謝産物であっては、フェロモンとはいえない。ただし、ドーミトリー効果などの知見をふまえると、ヒトもお互いにおいで情報交換をしている可能性は極めて高い。
このように、においやフェロモンがつむぎだす生物の空間コミュニケーションをみてくると、もともとにおいやフェロモンは偶然的にランダムに空間に存在するのではなく、それぞれの生物の生活環境において必然的に存在し、生物時計(時間)と生存空間(距離)が厳密に制御された形で設計された「目に見えない力」をもつ情報網であるといえる。そして、生物は、水棲生物から陸棲生物にかけての進化の過程で、それぞれの種に特有なにおいやフェロモン分子を選択し、それらを受容できるシステムを獲得し、その結果、種の進化と保存が適切に行われてきたのである。
今回の特集は、協会の方々のご好意で、私の研究室で推進している嗅覚プロジェクトを紹介させていただく機会を得たものである。それぞれのプロジェクトに関わってくれている大学院生・博士研究員諸君に執筆してもらった。これらをお読みになると、においやフェロモンに対する理解が今までとは違ったものになるのではないかと思う。また、その生体に対する作用も、冗談ではすまされないレベルのものであることがご理解いただけると思う。
衛生志向と嗅覚否定によって軽視されてきたにおいの歴史が、いまや、さらにエスカレートして、教育現場でのいじめの対象になったり、飲食街におけるにおい問題(良い匂いでも悪臭になる)など、人間が快・不快の意識に敏感になるとともに社会問題までに発展してきている。これらのにおいの問題に対する現状のような対処方法では結局いたちごっこになって根本的解決策にはならない。私が提唱したいのは、においやフェロモンといったものに対して正確な理解をするための、嗅覚教育の必要性である。まずは、今回の特集で、われわれ大人達がその理解を深めることができ、社会問題になっている様々なにおいの問題も意識のもちようであり、いずれそれらも「かおりの風景」になることを願ってやまない。