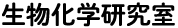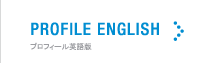解説
以下は、細胞工学12月号に掲載された原稿です
東原和成 ┃ 細胞工学 ┃ 2004年12月号
“匂いの帝王”はアクセルとバック:嗅覚復権
2004年度のノーベル医学生理学賞は、米コロンビア大学のRichard Axel博士と米フレッド・ハッチンソンがん研究センターのLinda Buck博士に授与された。受賞理由は、匂いの受容体遺伝子の発見と嗅覚感覚の分子メカニズムの解明である。AxelとBuckは、1991年、匂い受容体をコードしていると思われる遺伝子ファミリーをみつけ、Cellに発表した。この発見は、それまで生理学中心に進んできた嗅覚研究に分子生物学の潮流をいれることによって新たな展開のきっかけとなる大ブレークスルーであった。この論文をきっかけに、特にAxel研出身の研究者達が中心になって、嗅覚神経系のメカニズムがどんどん解明されていった。このCell論文は、当時、アメリカはニューヨーク州立大学の大学院2年生だった私が大変感銘を受け、将来独立して研究ができるようになったら嗅覚研究をやろうと心のなかできめるきっかけになった論文でもある。
一方、この遺伝子が本当に匂い受容体をコードしているという実証は遅れた。実に、遺伝子発見から7年もの歳月を経た後、米コロンビア大学のFiresteinのグループがオーファン嗅覚受容体のひとつのリガンドを決定し(Science論文)、ほぼ同時期に、筆者らのグループが単一嗅神経細胞レベルで匂いリガンドと受容体遺伝子を対応づけることによって(PNAS論文)、はじめて、1991年にAxelとBuckが発見した推定上の嗅覚受容体は、匂い受容体としての市民権を獲得した。私としては、自分が嗅覚研究をやろうと志すきっかけとなった論文の実証に関わることができ、今回のノーベル賞を後押しする研究ができたことに幸せを感じる。この我々のPNAS論文は、AxelがTrack IIのEditorとしてハンドリングしてくれた。そして、Buckがそのreviewerのひとりであったことを私は確信している。余談になるが、PNAS論文がでたあと、アメリカの学会でAxelと話す機会があった。彼は非常に変わったひとで、学会ではいつもひとりでふら~と歩きまわり、学会会場にあるクッキーやお菓子などをぽりぽり食べている。あまり人とは話さないが、それは、みんな恐れ多くて近づけないということもある。私はそんなオーラをがんがんに周りにだしているAxelがクッキーをつまみ食いしているときに話しかけ、「Thank you very much for handling our paper.」彼は「I am sorry for taking so long in reviewing process. But it is an excellent work.」と言ってくれた。大学院生のときの夢がひとつかなったような気持ちになったのを今でも覚えている。
Buckとは、ある意味、競争相手であったので、学会でもぴりぴりとした空気が私とBuckとの間で流れていたが、今ではもう親密で(私がそう思うだけか?)、学会でもいろいろな話をするようになった。Buckは10年近くAxel研のpost-docとして働いていた。当時のAxel研の研究の主流は、mGlu受容体遺伝子クローニングであったが、日本の中西研に先を越されてアップアップしていたときであった。ある日、Buckはサザンの実験結果を見て、これは大発見だと確信したらしい。全く見たこともない配列の遺伝子で、多重遺伝子群を形成しているようだ。Buckはそのとき、Axelにはすぐには報告しにいかなかった。彼女は、今Axelにもっていったら、Axelのかわいがっている同僚の研究員に話して、私の発見が彼らにもっていかれてしまうだろう、と思ったらしい。そして、そのときの結果は、ゴミ箱に捨てたらしい。それくらい、彼女は、発見にふるえたらしい。しかし、彼女はここは踏ん張りどころだと奮起して、ひとりで全てのデータをだして、ノーベル賞受賞対象論文となるCell論文を書いたのである。彼女にとっては、実に、4年近くもデータがでていなかった時であった。偉大な発見の陰には、必ず苦労と執念がある。そこに偶然が必然となる瞬間が導かれる。
今回の受賞は、実は、話題性が豊富である。御存知のように、日本でも翻訳されている「匂いの帝王」という本がある。全米ではベストセラーになっている。AxelとBuckの匂い受容体説というものに真っ向から立ち向かい、匂いの分子振動説を提唱したルカ・テューリンのサイエンスドキュメンタリーである。重水素化された物質は違う匂いがする、炭素鎖が偶数と奇数のアルデヒドそれぞれ匂いが似ている、などを根拠とした分子振動説はすでにいくつかの検証実験で否定されている。しかし、私個人的には、すべての匂い受容が、AxelとBuckの嗅覚受容体で説明がつくとは思わないが、やはり、“匂いの帝王”はAxelとBuckであるということで決着がついたと思われる。
彼らの受賞が決まりPress releaseになった1分後に、新聞社各社から問い合わせの電話が入った。まず、最初の質問は、共通して、「今回の受賞はどんな研究なのでしょうか?匂いに関することであることはわかるのですが、何がなんだかわからないので、説明していただけるでしょうか?」。いかに身近な感覚であるにも関わらず嗅覚のことを知らなかったか、そして、嗅覚を臭覚と書いてしまうようなミスをする。新聞では嗅覚の「嗅」の字は多くの人が読めないので使わない。19世紀末に、匂いが病気を蔓延させるという迷信にたつ衛生志向とフロイトを中心とする思想家哲学者による嗅覚否定によって、それ以前は崇高で神秘的な感覚として扱われていた嗅覚の蔑視と軽視がはじまった。もちろん、政治的な背景はあるものの、二世紀を経て、ようやく、その嗅覚が復権したのではないかと思う。もうひとつ、マスコミからの共通の質問は、「この発見は何に役立つのですか?応用面はなんでしょう?最近世の中に役立つものに対する受賞が多かったものですから」であった。これには困った。まだ脳機能の解明につながる基礎研究レベルであるとしかいえない。役立つことや応用面を考えてミッション主義で研究を発展させようとする現代サイエンスの方向性と考え方をよく反映した質問である。今回の受賞は、そんな実利主義の風潮を真っ向から否定し、科学研究においてわれわれ人間の生命というものを理解するという基礎研究の原点にたつという初心を忘れるなという主張の表れではないかと私は思う。釈迦に説法だが、発見は発明の母。今回のAxelとBuckの受賞は、われわれ基礎研究を推進している研究者にとって非常に勇気づけられるものでもある。まだ嗅覚はわからないことだらけ。そこには生命科学の神秘の一片一片が潜んでいる。(平成16年10月15日)
「細胞工学」マニアのための隠れ情報:細胞工学vol.20, no.6, 2001年にこのシンポジウムの学会報告があるが、その図1の建物の左に電話をしているRichard Axelの姿が、図2にコーヒーをもつLinda Buckの姿がなにげなく写っている。