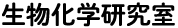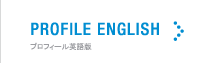解説
以下は、現代化学12月号に掲載された原稿です
東原和成 ┃ 現代化学 ┃ 2004年12月号
匂い受容体遺伝子の発見:香りを感じる嗅覚の全貌解明への手がかり
●はじめに
我々は、目でものを見て、耳で音を聞き、舌で味わい、そして、鼻で香りをかぐ。においの感覚である嗅覚は、古代から、五感のなかで最も神秘的で崇高なものとされてきたにも関わらず、そのメカニズムの解明は遅れていた。2004年度ノーベル医学生理学賞は、その嗅覚感覚の解明にブレークスルーをもたらした発見が対象となった。受賞理由は、「匂い受容体遺伝子の発見と嗅覚メカニズムの解明」。コロンビア大学のRichard Axel博士とフレッド・ハッチントンがん研究所のLinda Buck博士である。対象となったオリジナルの発見が記載されているのは、1991年の米国セル誌の論文である(文献1)。この発見を機に、それまで生理学中心で進んできた嗅覚研究に分子生物学の旋風が吹き込まれ、飛躍的に嗅覚系の分子レベル・神経回路レベルでの理解がすすんだ。なぜ、この発見がノーベル賞の受賞の対象になったのか。新聞報道も含めて、多くのひとが、「きゅうかく嗅覚」を「しゅうかく臭覚」と間違えたり、「匂い」を「勾い」と書いたりするほどの認知のなさで、どちらかといえばマイナーで、しかも「あの臭い匂いの研究ですか」と軽視されていた領域に光りがあたったのはなぜか。
●匂い受容体候補遺伝子の発見
一般的に匂い物質とよばれるものは、分子量で約30-300くらいの揮発性の低分子有機化合物である。世の中には数十万種類もの匂い物質が存在するといわれているが、嗅覚が退化している人間も1万種類くらいは嗅ぎ分けられる。このように多種多様な匂い分子を感知する実体はなんであろうか?半世紀以上の間、この大問題に、多くの嗅覚研究者が取り組んできた。その間提唱された匂いの感知メカニズムとして、立体構造モデル、分子振動モデル、吸着モデルの三つに大別できる。すなわち、それぞれ、匂いの形がにおいの質を決めていてそれを受容するタンパク質のようなものが存在する、匂いの分子振動そのものが嗅神経に作用してにおいの質を決定している、匂いの違いを感知するのは細胞膜の脂質二重層そのものである、という説である。そのなかで、立体構造モデルは、時代とともにAmooreらの特異受容体説に収束していき(文献2)、最終的にBuck & Axelの匂い受容体遺伝子クローニングによって実証された。一方で、匂い分子の分子振動が匂いの質を決定しているという分子振動モデルは、最近、ベストセラーになった「The Emperor of Scent」(「匂いの帝王」早川書房?)に紹介されているように、提唱者であるLuca Turinを中心にまだ残っている(文献3)。しかし、Buck & Axelのノーベル賞受賞によって、匂いの帝王はBuck & Axelということで決着をみたとでもいえようか。
Buck & Axelの匂い受容体遺伝子発見は、70~80年代にかけてのいくつかの知見が出発点になっている。まず、匂い刺激をうけた嗅神経細胞では、cAMPなどの細胞内セカンドメッセンジャーの上昇がみられるということ(文献4,5)、また、セカンドメッセンジャーによって開口するチャネルが存在するということである(文献6)。これらの知見は、匂い受容体がGタンパク質共役型受容体であるという仮説を提唱するのに十分な知見であった。80年代後半、当時、Axel研のポスドクをしていたBuckは、匂いの受容体遺伝子を見つけるために、三つの仮説をたてた。視覚受容体ロドプシンファミリーに属するGタンパク質共役型受容体である、匂い受容体遺伝子は嗅神経特異的に発現している、匂い受容体遺伝子は多重遺伝子ファミリーを形成している、の三つである。そこで、Buckはロドプシンファミリーに保存されている配列から縮重プライマーをデザインして、当時は最先端の技術であったDNA増幅法(PCR法)を用いて、嗅神経細胞特異的に発現しているGタンパク質共役型受容体遺伝子をクローニングすることに成功した(図1)。そして、この遺伝子は約千個からなる多重遺伝子ファミリーを形成していていることを見出したときに、これは匂い受容体をコードしている遺伝子群だとBuckは確信したらしい。発見は1991年に米国セル誌に投稿され、投稿から掲載まで1ヶ月という当時としては異例の速さで掲載された(文献1)。これが今回の受賞対象となったオリジナル論文である。この発見を機に、当時、神経伝達物質の受容体遺伝子のクローニングがメインテーマだったAxel研は、嗅覚研究のほうへシフトしていったのである。
●匂い受容体が作り上げる嗅神経ネットワーク
匂い受容体候補遺伝子の発見後、最大の課題であったのは、これらが本当に匂い受容体をコードしているのか、すなわち、この受容体は匂いを認識するのか、であった。しかし、当時、いわゆる培養細胞などでの発現機能解析が困難であったことから、その実証は遅れた。一方で、ハーバード大にポジションをえてAxelから独立したBuckと、Axelのグループは、ほぼ同時に、以下の二つの興味深い知見を発表する。約千種類ある匂い受容体は、それぞれの嗅神経細胞で一種類のみが発現して発現領域ゾーンを形成しているということ(文献7,8)、そして、同じ受容体を発現する嗅神経細胞は数万から数十万あるが、それらはすべて収束して、ある特定の糸球体に神経軸索が集まっていること(文献9,10、11)、である。この二つの事実は、嗅覚が多種多様な匂い分子を識別する仕組みを示唆する重要な発見であり、受容体遺伝子の発見に匹敵するくらいのものであった。すなわち、もしひとつの神経に複数の受容体が発現していたら、それぞれの受容体が受け取る匂い分子は違うのに、同じ匂いとして処理されてしまう可能性があるが、ひとつの神経にひとつの受容体しかないことによって、違う匂い分子を細胞レベルで正確に区別できるということである。また、同じ受容体を発現する神経は、ある特定の場所に集まっているので、末梢における信号が混ざりあわずに、そのまま二次神経回路へ保存されたまま伝わることを示している。匂い受容体候補遺伝子は約千種類あり、単一の嗅神経細胞には一種類の受容体が発現し、同じ受容体を発現する神経は集まっているということは、嗅覚の識別能力を説明する十分な状況証拠であった。しかし、やはり、最終的な結論は、この受容体遺伝子が、本当に匂い受容体であることを証明し、さらに、どのようなメカニズムで匂いを認識しているかを明らかにするこが必要であった。
●匂い受容体であることの証明
Buck & Axelが同定した匂い受容体候補遺伝子が本当に匂い受容体をコードしているという実証実験は、筆者らのグループを含めた世界3グループがそれぞれ独立した手法を用いて成功して、98-99年にかけて発表した。コロンビア大学のFiresteinのグループは、あるラット匂い受容体遺伝子をアデノウイルスに組み込んで嗅神経に感染させ、感染細胞で匂い応答を電気的に測定することによって匂いリガンドを特定した(文献12)。筆者らのグループは、上記の一細胞・一受容体の知見をもとに、ある特定の匂いに反応をしめした嗅神経細胞に発現している匂い受容体遺伝子を単一細胞RT-PCR法を用いて機能的にクローニングし、さらに、嗅神経あるいは培養細胞での発現系でその匂い応答を再構成した(文献13)。ドイツのHattのグループは、匂い受容体のアミノ末端にタグ配列をつけることによって培養細胞での受容体膜移行を成功させて匂い応答を測定することに成功した(文献14)。これらの発表以外にも成功したと報告している論文がいくつかあるが、その後、検証実験の結果、再現性がない部分をもつ論文なのでここでは紹介しない。これらの実証によって、1991年以来の候補遺伝子が、本当の匂い受容体遺伝子であるということがわかったのである。この実証実験が今回の受賞を早めたといっても過言ではない。
さらに、実証した3グループは実験を重ね、ひとつひとつの匂い受容体は複数の匂い物質を異なった親和性で認識しており、逆に、ひとつひとつの匂い分子は複数の異なった組み合わせの受容体によって認識されていることを明らかにした。三原色や五味といわれるように少数のカテゴリーに分類される視覚や味覚と違って、匂いの質の多様性はある意味では無限である。なぜ、このような多様性が生まれるのか。上記の、匂い受容体発現神経がつくりだす投射ネットワークと、受容体解析からわかったリガンド認識機構をあわせて考えると、受容体の組み合わせによって匂いの多様性を区別する仕組みが見えてきたのである(文献15,16、17)。抗体産生機構発見以来の、生物がもつ多様性識別を実現する巧妙なシステムの発見である。
●匂い受容体遺伝子の発見がもたらしたもの
匂い受容体遺伝子のクローニングがなぜここまでセンセーショナルだったのか。まず、最大の遺伝子ファミリーで、特異的な転写制御があり、また、匂い識別以外にも軸索投射にも関わっているという知見だけでも、基礎生物学的には非常に魅力がある。また、PCR法が開発された直後で、今となってはあたりまえの手法なのだが、このようなホモロジークローニング法の先駆けとなったものである。1991年のクローニング論文は、今までに千以上の引用回数を誇る化け物論文である。一方で、嗅覚は人間でこそ退化しているが、他の生物では一番重要な感覚であり、この仕組みの全貌を明らかにすることは、生物そのものを理解することにつながるといっても過言ではない。ゲノムプロジェクトの結果、ヒトでも匂い受容体遺伝子は約350個あることが明らかになっている(文献18)。嗅覚を広義で考えれば、フェロモンも含まれる。BuckとAxelは匂い受容体遺伝子だけでなく、フェロモン受容体遺伝子も発見している(文献19,20)。今、脳研究の時代といわれているが、匂いの記憶や学習は、脳研究には最適のシステムである。われわれが何を感じ、何を思うか、そんな感情や情動の変化には、嗅覚が密接に関わっている。嗅覚研究は「くさい臭い」ものでも「かぐわしい芳しい」ものでもなく、われわれが「感じる」脳の機能の本質までせまる研究である。
●おわりに
生物がどのようにして多種多様な匂い分子を感知して識別するのかという20世紀の大命題は、1991年の匂い受容体遺伝子の発見から芋づる式に紐解かれていった。そして、彼らの1991年の論文は筆者が嗅覚研究をやろうと志すきっかけになったものでもあり、また、彼らの発見した受容体遺伝子が本当に匂いを認識するのだということを示す研究に独立して関われたことに喜びを感じる。2001年にコールドスプリングハーバーで開催された匂い受容体遺伝子発見10周年記念シンポジウムに、嗅覚受容体研究の日本代表として筆者と東大坂野教授の二名が招待され講演を行った。そのシンポジウムの冒頭講演をBuckが行い、最後の講演はAxelによって閉められた。彼らの発見に感銘をうけてこの領域の参入した人たちが集まり、議論をかわし、飲みながら将来を語った一週間であった。Axelはとても背が高くて近寄り難いオーラをだしているが、その語り口はやわらかい。天才肌のAxelに対して、Buckはどちらかといえば努力家であるが、彼女の着眼点はいつも先端をいっている。彼らの今回の受賞を契機に、ますます嗅覚研究者が増えるだろうと予測できるが、一方で、嗅覚は、有機化学、細胞生物学、神経科学、分子生物学、生理学と領域横断的な研究なので、ある特定の専門的な考え方や技術では全貌を明らかにするのは難しい領域である。逆にいえば、どんな切り口でも入っていけるこの領域に、多くの若い諸君に興味をもってもらって参入してチャレンジしてもらいたいと思う。(平成16年11月1日)
参考文献 1) Buck, L. and Axel, R. (1991) Cell 65, 175-187 2) Amoore, J.E. (原俊昭訳)(1972) 匂いーその分子構造、恒星社厚生閣、東京 3) Turin, L. (1996) Chemical Senses 21, 773-791 4) Kurihara, K., and Koyama, N. (1972) Biochem. Biophy. Res. Commun. 48, 30-34 5) Pace, U. et al. (1985) Nature 316, 255-258 6) Nakamura, T., Gold, G.H. (1987) Nature 325, 442-444 7) Ressler, K.J. et al. (1993) Cell 73, 597-609 8) Vassar, R. et al. (1993) Cell 74, 309-318 9) Ressler, K.J. et al. (1994) Cell 79, 1245-1255 10) Vassar, R. et al. (1994) Cell 79, 981-991 11) Mombaerts, P. et al. (1996) Cell 87, 675-686 12) Zhao, H. et al. (1998) Science 279, 237-42. 13) Touhara, K. et al. (1999) Proc Natl Acad Sci U S A. 96, 4040-5. 14) Wetzel, C.H. et al. (1999) J Neurosci. 19, 7426-33. 15) Touhara, K. (2002) Microsc Res Tech. 58, 135-41. 16) Mombaerts, P. (2004) Nat. Neurosci. Rev. 5, 263-277 17) 東原和成 (2003) 化学と生物 41, 150-156 18) Zozulya, S. et al. (2001) Genome Biology 2(6):research/0018.1-0018.12. 19) Dulac, C. and Axel, R. (1995) Cell 83, 195-206 20) Matsunami, H. and Buck, L.B. (1997) Cell 90, 775-784