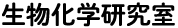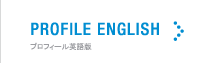書籍掲載
以下は、「香りの研究エッセイ」(フラグランスジャーナル社)に掲載されています
東原和成 ┃ 「香りの研究エッセイ」 ┃ (フラグランスジャーナル社、2005年)
空間を把握する力ー嗅覚ーの総合理解を求めて
昭和が終わる年、私は東京大学農芸化学科有機化学研究室で天然物合成研究に昼夜明け暮れていた。当時の研究室では、植物ホルモンや昆虫フェロモンなど天然生理活性物質の両鏡像体の全合成を目指しており、実験室は様々な有機化合物が発する香りだけでなく、風呂に入る暇も惜しんで昼夜実験に明け暮れていた研究室メンバーの身体からでる臭いであふれていた。そして、様々な微生物が発する発酵臭と活気あふれる議論がかわされる部屋から酒の香りと煙草の薫香がただよっていた。昭和初期に立てられた歴史的建築物でもある農芸化学棟は、無意識のうちに心地よさを感じる空間を形成し、若者の身体のなかをめぐる血を激しく涌き立たせ、それは、いうまでもなく極めて厳密に使いこなされた匂いが創り出す嗅覚空間であった。初めて科学の世界に足を踏み込んだこの年に受けた感覚が自分のなかで形として具現化されたのは、それから7年の歳月がたったあとである。
私が大学院生活の場として選んだニューヨーク州立大学ストーニーブルック校は、これまた様々な匂いが入り乱れるニューヨーク・マンハッタンから車で約1時間の場所にある。初めての国際線でアメリカに降りたときに空港で匂った、あの洋書の匂いに似た甘い香りは、今でもマルセル・プルーストのマドレーヌのように私の記憶に刻み込まれている。食文化と気候と民族の遺伝子の違いから生まれる各国特有の匂いに遭遇し、自分のなかの狭い嗅覚空間が広がり始めた。そんななか、推定上の嗅覚受容体遺伝子の発見があり、卒論生のときに感じた嗅覚に対する興味が再燃した。そして、デューク大学での博士研究員を経たのち、日本で嗅覚研究を立ち上げて日本オリジナルな研究として世界に発信したいという希望とともに日本帰国を決意する。サリン事件、阪神大震災からまもないバブル崩壊後、一匹狼として帰国したが、嗅覚コミュニティーに属さないゆえの辛さと気楽さが複雑に交錯する。しかし、それらもしだいに快感に変化して、アメリカという大国のなかで見失いかけていた自分のアイデンティティーがようやくできてきたのは、嗅覚界でもとりあえずは存在に気づいていただけるようになったつい最近のことである。
私が嗅覚研究をはじめた1996年頃は、BuckとAxelが発見した嗅覚受容体候補遺伝子が本当に匂いを受容するという証拠はまだなかった。培養細胞における発現がうまくいかないということで世界的にも停滞していた時期である。私は、2年間の試行錯誤のすえ、単一嗅神経細胞からの受容体遺伝子の機能的クローニング法を立ち上げて、匂いと受容体との対応付けに成功した(米国アカデミー紀要1999年)。FiresteinグループのラットI7受容体、HattグループのヒトOR17-40受容体とともに、機能解析が詳細におこなわれている数少ない嗅覚受容体である。しかし、嗅覚研究の世界の新参者であったので、この論文をとおすのに非常に苦労した。それだけでなく、アメリカと日本の共同研究グループによって、我々が論文を投稿した時期から水面下で同じアイデアで同じような仕事が推進されて、結果的に我々日本からの純品の論文がつぶされ陰が薄くなってしまった。少々日本傾倒主義的になって帰国した私のなかの日本人魂がますます燃えた。そのエネルギーが、京都大学の西岡教授と共同研究で進めたカイコガ性フェロモン受容体の発見につながった(米国アカデミー紀要2004年、サイエンス誌2005年)。世界発のフェロモンの同定は、50年ほど前、日本のカイコをつかったドイツのグループに先を越されたが、そのときの日本人としての辛酸のリベンジといえよう。ともあれ、BuckとAxelによる1991年の嗅覚受容体候補遺伝子の発見が、私が嗅覚研究にはいるきっかけになり、結果的に彼らと競争することになりながらも、日本からのオリジナルな成果の発信をできていることに喜びを感じている。有機化学を最初に学んで、「もの」を合成することの大切さを知り、そういった化学的アプローチを基盤に嗅覚受容体に関する研究を立ち上げてきた賜物であると信じている。
現在、私は、動物、昆虫、植物といった地球上の三大生物種を研究対象として、空間を把握する力をもつ感覚系を統合して考える基本原理を模索したいと考えている。下等動物においては味覚(舌)と触覚(皮膚)といった身体のすぐ表層の変化に感じる近接受容感覚が主流をしめるが、高等動物においては、視覚(目)、聴覚(耳)、嗅覚(鼻)による遠方からの化学的な変化(匂い)や物理的変化(音や光)に反応する遠隔受容が発達している。ここで、遠隔受容をおこなう空間感覚のひとつとして嗅覚を広義に考えると研究に広がりがでてくる。「におい」を国語辞典でひくと、「香り、臭い、光り、色、おもむき、感じ」とある。嗅覚的な意味をもつ「香り、臭い」と、視覚的な意味をもつ「光り、色」と、雰囲気をあらわす「おもむき、感じ」と多岐にわたっているのがわかる。万葉集や源氏物語における「にほひ」の使い方も様々である。嗅覚においては、「におい」は匂い物質からでるもので、その受容は嗅覚受容体が担う。視覚における「におい」は、白黒といわゆる赤緑青(RGB)の三原色からなる光と色からでるもので、ロドプシンやオプシンがその受容を担う。雰囲気は五感でうけとるが、そのなかでも匂わない「におい」であるフェロモンがその媒体になっていると言えようか。これら空間を把握する「におい」感覚における受容体はすべて、七回膜貫通型のGタンパク質共役型受容体であるのは単なる偶然だろうか。私が思うに、空間からやってくる「におい」を受容し、その信号を脳へ正確に伝達させる仕組みは、ある共通性をもって機能構築されているようだ。
早く伝える必要のある信号は往々にしてチャネル型受容体経路が使われる。例えば、痛みにしても音にしてもしかりである。遅い経路として、細胞増殖因子などの受容体型チロシンキナーゼを介した経路、ステロイドホルモンなど核内受容体を介した経路が存在するが、感覚系には適さない。さて、本能や情動を瞬時にして呼び覚ます嗅覚やフェロモン系において、本来ならば信号伝達の早いチャネル型受容体が使われてもよさそうなものの、やや情報伝達スピードが遅いGタンパク質共役型受容体が使われているのはなぜだろう。チャネルは興奮の伝達のみをおこなう。しかし、Gタンパク質共役型受容体は活性化されてから数百ミリセカンド後に電気的な興奮に信号を変換させるだけでなく、セカンドメッセンジャーやタンパク質リン酸化や遺伝子発現などを介して細胞の伝達効率の変化などモニター系を発動させる。すなわち、興奮の伝達だけでなく、細胞制御系の機動も同時に行っているのである。このように精巧なモニター系であるGタンパク質共役型受容体を介した情報伝達系の存在は、脳の神経系においては大変重要なことであり、特に記憶や学習とも関連の深い嗅覚系における基本原理を提供しているのではないかと私は勝手に考えている。すなわち、空間を把握する力としての嗅覚だけでなく、記憶や学習といった時間軸を制御するという視点からみた嗅覚も大事なのである。時空間をさまよう千と千尋に、強く「におい」の風景を感じたのは私だけだろうか。
「におい」の空間を大事にした映画監督は少なくない。奇しくも、2003年は、日本映画界の巨匠、小津安二郎の生誕100周年にあたる。小津は、カメラ目線に視覚トリックをとりいれ、研ぎ澄まされた嗅覚感覚をちゃぶ台を中心とした食卓の風景に映し出した。人と人が出会い、目線が交差し、そして、次に、耳をそばだてて会話がはじまる。すぐに、その場の空気の流れのテクスチャーと鼻をつうじてにおう雰囲気など五感をフルに活動してコミュニケーションが成立する。現代人の中には、そんなともすればささいなことができない人達がたくさんいる。なぜか。私が思うに、インターネットを通じて何でも手に入る情報過多の時代において、コンピュータに向かってハードな情報を「選別」するといった、能動的のようで実は受動的な行動にエネルギーを費やすようになり、その結果、ソフトなコミュニケーション感覚が鈍感になってしまったからではないかと思う。人間の共同生活空間においてコミュニケーションを器用に行い、自分のアイデンティティあるいは主体性といったものを確立するためには、小津映画のちゃぶ台にその原点を見いだせる空間を把握する力を常に研ぎ澄ませていこうという能動的な努力が必要なのではないかと思う。
ポストゲノム時代といわれる21世紀に大事なことは何か。私が一番にあげるのは、ナノテクノロジーでも遺伝子治療でもない、「五感」である。「におい」は匂いである必要はない、五感を震わせる手段でありさえすればよい。忘れてはいけない。動物の本能を失いつつある人間も、無意識のうちに、気持ちよさを感じる空間というものは、極めて厳密に設計された「におい」の風景であるはずなのである。わずかな芳しい香りは、我々の精神の奥深いところを刺激し、「豊かで勝ち誇り無限のものの広がりを示し、精神と感覚の熱狂を詠う」(ボードレール)。そして、無限の組み合わせからなる香りは、それ自体で動物を喜ばせる力をもつ。空間を把握する力をもつ嗅覚を多角的に理解することによって、理知や理性では説明がつかない動植物間のコミュニケーションの手段としての「におい」の絶大なる潜在性が模索でき、人間が人間たるゆえんにせまることができるような非線形系の価値判断を定量化することが可能になるだろう
とりわけ、日本人は闇に強い。江戸時代までは一歩外は闇の世界であった。「匂ひも、ものの音も、ただ、夜ぞひときはめでたき」(徒然草)。まばゆいばかりの人間が創り出した光の空間がもたらした恩恵は計り知れないが、一方で、失ったものは多い。その最たるものが、嗅覚なのではないか。嗅覚礼賛。闇に強い、すなわち、嗅覚にすぐれていた古代中世日本人の子孫として、嗅覚基礎研究をとおして人間を人間たらしめる嗅覚の復権に貢献できたら、日本オリジナルの嗅覚研究を志して帰国した小生にとって、これ以上の喜びはない。