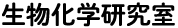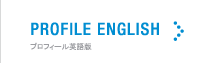雑誌掲載
以下は、2001年3月「細胞工学」(秀潤社)に掲載された原稿です
東原和成 ┃ 細胞工学 ┃ 2001年3月号
アメリカ大学院の教育カリキュラムとの比較
単一民族の宿命的習性なのか、日本では物事の評価を自分達の国内の絶対評価で行わず、外国との比較をすることがよく行われる。もちろん、比較して参考にすることによって既存の制度を改良して日本独自のシステムを構築していけばよいのだが、残念なことに、外国の制度を単純に導入することによる日本の風土や伝統的なシステムとの不協和音を解消できないまま歪みが生じる結果におわっている。例えば、日本の研究体制の整備に関しては、科学研究費はアメリカのそれに比べて少ないといって審査制度の改善を行わないまま大型予算を注ぎ込んだり、外国の研究成果の動員力となっているポスドク制度をその後のキャリアパスを考えずに強引に導入したりすることによって欧米諸国に追いつけ追い抜けを目指している。果たして、教育体制に関しては、どのような外国との比較検討ができるのであろうか?文部省大学審議会の答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」では大学の教育研究が目指すべき目標、理念が提言されているが、具体的には現場の各大学が個々の改革方策に取り組むことが求められている。本稿では、過去3回に渡って紹介された東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻の教育面での新しい試みとアメリカ大学院の教育カリキュラムとの比較をおこない、この2年間の成果を教官側と学生側の両観点から分析することによって、今後の日本の大学院における教育システム改善に向けての問題提起をしてみたい。
さて、大学院入学時の日本とアメリカの大きな違いの一つは、すでに研究室の配属が決まっているか否かである。アメリカでは入学時には配属先研究室は決まっておらず、大学院1年目は、講義を主体に、ローテーションと呼ばれる研究室回りをして実験をする。すなわち、1年目に基礎科学の知識をつめこまれ、同時に、複数の研究室で現場の実験にふれることによって希望の研究室を1年かけてじっくり決めることができる。これは修士と博士コースにわかれていないアメリカだから可能なシステムで、日本では修士2年間のうち1年間をこのように過ごしては修士論文研究実験の時間が少なくなってしまう。それが理由かどうかはわからないが、入学と同時に研究を始めるために日本のシステムでは大学4年生の春という研究経験もほとんどない時期に希望の研究室を決めて夏の院試にのぞまなくてはいけない。さらに、希望の研究室の定員枠をはみだしてしまうと、第2志望以下の研究室に、ひどい場合は第5、第6志望といったところまでまわされることもある。各研究分野にある程度均等に学生が配属されるためには良いシステムであるが、学生側にとっても受け入れる教官側にとっても満足がいくかといったら疑問である。そこで、先端生命科学専攻がとりいれた新しい制度として「入学後配属」というものがある。これは、院試時に希望研究室を指定せず、入学後に配属先を決めるという選択肢を選べるという制度である。そして、大学院1年の4月にプレスクール(先端生命科学研究論)と称して各研究分野の教官が自分の研究領域の話しをする必修講義期間をもうけ、その後に自分のいきたい研究室を決めるというものである。研究室をじっくり決めることができるという点や希望度の低い研究室への配属が防げるという点で画期的であるが、希望分野を最初から指定した学生との関係や各研究室の学生定員から生じる問題など問題点はある。また、どちらにしても4月のプレスクール後に決めなくてはならないため、本当の意味でじっくり決められるかどうかも疑問である。しかし、院試における志望分野の決定時期だけでなく、ろくに大学院で研究をしないうちに修士1年生の秋には就職か博士課程進学の選択をせまられるというある意味では先手先手とおさえていくせっかちな日本の社会形態ではやむを得ないところではあろう。従って、この入学後配属という制度は、アメリカの大学院カリキュラムの利点を取り入れながら日本のシステムに適応させようとする試みであるといえる。大学院重点化に伴い修士博士一貫教育を奨励し欧米諸国のポジティブな研究者の流動性を目指しながらも、研究室選択ミスによって不幸になってしまった学生が博士課程で研究室を変えるようなネガティブで逃げの流動性を生んでしまったという矛盾と、日本の企業の過熱ぎみともいえる就職内定の早期化がその混乱に拍車をかけてしまっているという現状を重要な問題として考える時期ではないかと思う。
さて、講義はどうだろう?まず大きな違いは時間である。アメリカの講義は長くても60分だが、日本では最低1時間半である。また、時間の長さだけでなく、講義のはじまる時間もアメリカでは遅くとも朝8時半で、午前中にはほとんどの講義が終わる。そして午後から実験をするのである。しかし、日本では講義が実験の支障をきたすような中途半端な時間に組まれたりする。また、アメリカでは毎週型の講義(週に2~3回のもある)がほとんどだが、日本ではひとこまの時間が長いだけでなく、集中講義などは一日中講義室に缶詰めである。この点に関する改善は日本のいくつかの大学院で行われているようである。一方、内容に関しては日本の講義のレベルは高い。アメリカは基礎の基礎の部分を徹底して一年目にやるが、日本では各領域の著明な先生方を招いて最先端の科学の話しを受けられる。ここで日本の学生が忘れてはならないのは、基礎がないままに先端の知識ばかりをいれては、本当にオリジナルな研究を遂行できる力が身につかないということである。いわゆる「基礎」というものは例えばストライヤー生化学の教科書を丸暗記していればつくものではなく、実験操作の意味がわかり実験計画と結果の考察を論理的に組み立てられる力のことをいう。知識は教科書や論文を読めばつくもので、わざわざ時間をさいて講義というものがあるのだから、教官側もその点を意識して授業を組み、学生側もそれを意識しながら聴講するのが有効な講義の仕方と聞き方なのであろう。
少し話しがずれたが、連載第2回で紹介されたように、先端生命科学専攻では、英語の論文の書き方やプレゼンテーションの仕方を教える講義がある。英語の論文の書き方は、実は、アメリカの大学院では講義では教えない。母国語であるということもあるだろうが、大学時代から常に「書く」ということのトレーニングは十分に受けているし、各指導教官にまかされているというふしがある。一方、プレゼンテーションを練習する講義は存在する。それほど体系だって講義として教えることはしないが、学生が持ち回りでやるセミナーがあったり、博士をとるまでに何度となくプレゼンテーションの機会がある。また、毎週、学科のセミナー(コロキウム)があり、その出席は必修となっているので、様々な研究者のプレゼンテーションを聞くことによって、どのように発表すればよいかというのを学ぶ。もちろん、セミナーのあとは、コーヒーとクッキーの小さなレセプションで交流をはかる。金曜日の夕方のセミナーだとビールもでたりして盛り上がる。また、有志で集まる小さなジャーナルクラブなどもあり、そういうところに参加しては発表の機会が与えられる。プレゼンテーションの重要性を子供の時から教え込まれるアメリカでは、大学院においては当然のごとくに自然に身につけられるようなシステムになっているのだろう。日本では、日本人が英語の講義するのであるから、そんなに高度な英語講義はできないが、少なくとも、早い時期から「論文を英語で書く」という科学者の使命に触れ、また、自分の成果に自己満足で終わらず世の中の人達にわかってもらうために、いかにプレゼンテーションが大事でなおかつ難しいかを体験するという意味で大変有意義な講義であると思う。我々の初年度の英語の講義ではネイティブの先生にいくつか講義を依頼したが、内容以前に英語が聞き取れないといった意見や、高度な洗練された英語表現は日本人は実際問題使えないといった意見も聞こえ、修士レベルでは日本人が教えるほうが実用的であると思われる。
一方、連載第1回目で紹介した科学倫理に関する知見を深めるのが目的の講義なるものや地球生命科学論などといった講義は、先端生命科学専攻オリジナルなものとして位置付けられる。もちろんアメリカでも医学倫理などの講義はあるが、一般の理学系の学科の教育カリキュラムには見当たらない。大学審議会答申のなかにあるように、学術研究の著しい進展の中で、地球環境や生命倫理などに関する新たな課題に対する対応として画期的な講義であるが、先端生命科学専攻におけるこれらの講義に対する学生側の評価は、非常に刺激的で新鮮さをもつ講義である反面、講義形式に無理がある、コンセプトが不明などといった厳しい批判もある。また、実際に研究生活をしたことのない学生にいきなりこのような講義を受けさせることは、考えを混乱させるばかりという意見もあるので、今後検討すべき問題を残している。
前回紹介した中間発表や研究費申請(プロポーザル)の練習は、もちろんアメリカの大学院にもある。中間発表として自分の研究進行状況を発表するものや、また、一年目の講義のあとにまとめのテスト(Qualifying exam)があって、これに合格しないと博士課程に残れないというような資格試験みたいなものもある。プロポーザルも、National Institute of Healthのグラントプロポーザルの規定を練習台に書き、実際にプレゼンテーションも行う。早くから独立した研究者になって、グラントをとってくるために必須のトレーニングとみなされている。先端生命科学専攻においては、中間発表とプロポーザルを修士2年目に課しているが、上記の英語、倫理論などの講義も含めて、修士の2年間につめこみすぎている点を今後検討していくべきことかと思う。ただでさえ就職活動などで忙しいのに、ここまでやらされては学生も実験がろくにできない。アメリカでは博士をとるまでの約5年間の間にやっていることであるのだから、日本でも修士・博士一貫の教育理念を遂行してもう少しゆっくりやるのもよいのではないかと個人的には思う。また、先端生命科学専攻で見られる現象として、学生側も講義を取り過ぎる傾向がある。学融合をスローガンとして結集した学科であるがゆえに研究領域も幅広く、必然的に講義科目も多くなっている。そのために能動的かつ好奇心旺盛な先端生命科学専攻の学生は様々な講義に興味をもつのは当然のことであろう。前述のようにアメリカの大学院では研究指導教官が最初にいないので、小生の通った大学院では教育指導教官という人がいて、入学直後に講義についてのアドバイスをもらえる。その時に自分の興味にあった講義を現実的な数とるように指導される。先端生命科学専攻にも、他大学ではみられない教育指導委員のシステムが設置されているので、今後、履修科目登録の上限設定と個々の学生の興味を考慮した適切な科目選択の指導を行うことにより、広く浅い知識を得るよりは、広く興味を持ちながらも焦点は絞っていくといった本来の勉強の仕方が可能になると思われる。
アメリカ大学院の教育システムは「研究者創成工場」とも言われるくらいであるから、かなり綿密に練られた教育カリキュラムに乗せられて否応無しに勉強させられ試験を受け、必修の課題をこなしていく。明らかに受動的強制的教育システムである。そんな中で能動的に研究を行える資質をもった研究者が育っていくという一見すると矛盾した現象を見ると、果たして、各学生の自由な希望を尊重して勝手気侭にやらせることによって能動的な研究者がうまれるのかという疑問をもつ。ある時期にかなり強制的に受動的に勉強させられたり実験させられたりすることによって、自分なりの学問に対する考え方や実験の仕方を取得したり見つけていくのではとも思う。アメリカ大学院におけるそんな時期が上記の基礎つめこみ講義とローテーションの一年目なのであろう。先日、意気揚々としてアメリカはインディアナ大学へ留学して、凄まじく忙しい大学院1年目を経験している日本人学生からもらった手紙のなかにあった文章は印象的だったので引用させていただく。『彼等(アメリカ人)は本当にものすごく勉強します。よく言われるオリジナリティというものがどこから生み出されるのか知りませんが、こちらの大学院教育の強みは、大学院生に特に最初の2~3年間の間にものすごくストレスとセレクションをかける点でしょうか。』
新領域創成科学研究科先端生命科学専攻が学生を受け入れはじめて2年たった今、その教育カリキュラムにおける新しい試みの評価が高まると同時に、内在的にでてきた矛盾も含めて改善及び再編成の時期にきている。テニュア-を持っていても研究費がとれずに学生もこなくなってしまって講義専門になった教授(Teaching Professor)がいるようなアメリカのシステムをそのまま真似することはできないし、それらのシステムが良いとも限らないが、世界各国の例を参考に、よりよい新領域創成科学研究科先端生命科学専攻独自の大学院教育システムを全教官が一団となって構築していきたい。アメリカでテニュア-を取得するためには、教官側も講義の評判がよくなくてはいけないが、逆に学生側も、出席など取られる必要もないように(小生の経験ではアメリカの大学院講義で出席は取られなかった)、各自自覚をもって講義に望み、教官側と研鑽しあっていくような意気込みがほしい。講義を批判する前に、講義を最大限活用して自分のなかの糧にしていくようなポジティブな態度が望まれる。飽食の時代でなんでもやろうと思えばできる贅沢な社会のなかで、ただ楽しそうとかおもしろそうなものだけを求めて徘徊していては、「能動的アティテュード」をもった学生であるはずがミーハーな受動的な学生になってしまう。自分自身の存在価値を作っていくためには、じっと腰を据えてひとつひとつ確実に咀嚼して自分固有の概念を作り上げていく態度が必要である。こういった姿勢は、海外ポスドクの研究内容を引きずらずにオリジナルな研究成果を日本から世界へ発信していくために、教官側も常に念頭におくべき共通の理念であると思われる。学生も教官もお互いにそんな地道な努力をすることによって、研究の楽しみのほうも倍増し、当研究科のスローガンである「学融合」のもと、オリジナルな研究成果が附随してくることはまちがいない。