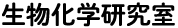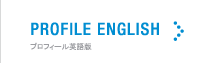寄稿
以下は、「蛋白質・核酸・酵素」2006年10月号50周年記念号に掲載された原稿です
東原和成 ┃ 蛋白質・核酸・酵素 ┃ 2006年10月号
サイエンスにおける私にとっての日本語
昭和が終った年、バブル絶頂期目前の時代、私は学部卒業後すぐにアメリカ大学院に留学した。その頃は、インターネットもなく、ようやくコンピュータが普及しだしたころであり、唯一日本語の活字にふれることができる場所は図書館の新聞コーナーだけであり、そこは同時に留学中の日本人との「出会いサイト」でもあった。その7年後、アメリカ留学に終止符を打ち、日本に帰国した。いろいろな人になぜアメリカに残らなかったのかと聞かれた。ある確固たる意思があって帰ってきたのだが、どんな理由もどこか自分のなかの本当の理由とは違うような気がしていた。そんななか、最近、やはりアメリカ生活が長かった数学者の藤原正彦氏がだした本「国家の品格」のなかに、私の心の奥底に眠っていた日本に帰国した本当の理由がまさに適確に表現されているのを発見した。それは、「論理より情緒、民主主義より武士道、英語より国語」という視点である。
私は日本の大学では体育会でテニスばっかりやっていてろくに勉強をしなかったので、ほとんどの知識をアメリカの大学院で得た。すると英語で覚えた知識を使って英語で考えるように必然的になっていたのだが、ポスドクの生活も終盤にさしかかり、アメリカで独立するか日本に帰国するか悩み、自分の将来的な研究の方向性を考えていたころ、高度で複雑な考えをしようとすると、自分の英語思考回路があるところでとまってしまうことに、ふと気付いた。外国語としての英語力の限界である。そこで日本語で考えようとしたところ、科学単語を英語で覚えているので日本語でも考えられないというジレンマにはまってしまったのである。これはどちらか選ばないと自分を失うと思い、そして選んだ国語は母国語である日本語である。―外国語より母国語―
もっともサイエンスの共通語は英語だから、英語力が勝負であることは当然である。そのためにもラボの公用語は英語としている日本の研究室もあると聞く。しかしアメリカ国内ならまだしも、日本でサイエンティストを育成するためにはそのような方針は逆効果であると私は思っている。私はアメリカ大学院の経験者だし、某英会話本などをだしているので、「先生のところでは修士論文は英語で書かせて英語教育をしているのでしょうね」とよく言われるが、そんなことはなく、英語で書きたいという学生にも修士論文は日本語で書かせて真っ黒になるくらい添削をする。日本語のできない日本人に英語なんてできっこない。もちろん母国語を英語とするアメリカ人のなかにもちゃんとした英語が書けない人がたくさんいて、アメリカ人でも論文をEnglish editing(英語添削)にだすくらいだ。サイエンス英語は論理性が大事だが、母国語である日本語をきちんと書けて、母国語できちんと話せて、はじめて美しい英語の論文が書けたりディスカッションできたりするのだと思う。―語学力は国語力―
10年ほど前までは、一ヶ月に最低一日は図書館にこもり、ジャーナルを読み、必要な文献をコピーするという作業を必ずしていた。今は、インターネットを通じて、自分のコンピュータにいつでも論文をダウンロードすることができるが、自分の領域の論文、すなわちキーワード検索でひっかかってくる論文だけしか見ない。図書館通いの時代は、すぐとなりの論文をみて偶然にアイデアが浮かんだり、時には普段手にとらない雑誌をちらちら見ることによって自分の興味が広がったりして視野が広がるときが多々あった。インターネット・コンピュータ時代で失ったもの、それは、活字を読み、想像力を働かせ、自分で考えるプロセスではないかと思う。印刷された活字を読むのと、コンピュータ画面上で字を読むのでは、使う思考回路は全く違う。文章の校正をするときに、液晶画面上では気がつかない誤字をプリントアウトしてはじめて気付いた経験をもっている人も多いだろう。―液晶より活字―
最近、ノートをとることが苦手な大学生が増えたと聞く。コンピュータ時代の負の産物とも考えられるが、どうも講義体系の変化が原因ではないかと思う。一昔前までは、プリントを補助資料として板書で講義をした。今は、学生からの評判もいいためか、パワーポイントで講義をする場合が多い。板書の講義では、聞くほうも能動的に頭を働かせながらノートをとる。一方、パワーポイントによる講義は、綺麗にアニメーションもできるので視覚的にわかりやすいことは確かだが、聞くほうは受動的にしか頭を働かせない。汚い字の板書を読み解くために想像力を働かせてノートをとり、先生のまとまりのない言葉を自分の言葉に落とす作業は、一見効率が悪いようで、実は、論理的な思考の育成に役にたっていたのではないかと感じる。講義が面白くなったことによって想像力の育みが失われるとはなんとも皮肉なことではないか。ここでも失われつつある活字のパワーを感じざるを得ない。-パワーポイントより板書―、という自分も去年くらいからついパワーポイントに頼りがちでよくないと思っているのだが。
さて、アメリカにいたときに、アメリカにはなくて日本にあるものでとてもいいなと思ったのは、母国語の一般科学雑誌が多くあるということである。「ニュートン」など一般市民や中高校生向けの科学雑誌から、いわゆる「蛋白質・核酸・酵素」を代表とする研究者向けの雑誌までさまざまなレベルの科学雑誌がたくさんある。アメリカではサイエンティフィックアメリカン(日本語訳:日経サイエンス)がそれに相当するが、日本のように母国語で書かれた科学雑誌がたくさんあってそれらを読むだけでさまざまな分野の最先端を知ることができる国は他にないと思う。もちろん英語総説を読めばいいじゃないかという意見もあると思うが、母国語でしか伝わらないニュアンスというものがあり、私も日本語で執筆するときは英語では表せないような母国語の力をふんだんに織り込むように心がけている。そして、これらの科学雑誌を読んで、多くの学部学生がサイエンスに夢を感じてこの世界に入ってくる。また新進気鋭の若い研究者の存在にも気づくことがある。そして何よりも活字にすること、活字を読むこと、そのプロセスを通じて、駆け出しの大学院生が想像力を膨らませる。一昔と違って、ブログなどで意見をリアルタイムで発信できる現代において、われわれは、活字として印字される文章を読むことによる脳への影響力の多大さを再確認するべきである。逆に言えば、活字として情報や知見を発信する出版社側も、実はとても責任がある立場にいるということを再認識する必要もある。
アメリカの図書館の隅で日本語の新聞を読み、英語で飽和した頭が癒され、その喜びのなかに自由な発想が育まれたころを思い出しては、今、活字離れが進む現代に、活字の大切さを思う。私にとってのアメリカ大学院留学というものは、美しい日本語と国語の大切さの再確認のきっかけであり、武士道的発想で欧米に英語論文を発信していきたいという眠っていた日本人魂を呼び起こしたものであった。もし、もう一度大学院生をするとしたら日本とアメリカのどっちを選ぶ?と聞かれたら、間違いなくまたアメリカを選ぶだろう。ただ、帰国という選択肢は自分のなかのアイデンティティの置き場所を模索した結果である。現在、捏造などで問題になっているサイエンティストとしての品格の低下を危惧しながら、もっと大事なものが、インターネットの時代、活字離れによって失われつつあるのではと心配になる今日この頃である。
(美しい日本語の活字を半世紀に渡って印字し続けてきた「蛋白質・核酸・酵素」の50周年記念特集に寄せて、平成18年5月22日)
追記:実は、執筆テーマは「過去」「現在」「将来」「自由題」のいずれかを選択ということであったが、自分の過去や将来を語れるほど研究者として確立していないし、一匹狼としていまだ不安定な立場で現在を語るほど余裕はない。そこで、英語英語とうるさい世の喧騒のなか最近切に思う国語力について書いたところ、結果的に自分の過去や今の話になってしまった。一方で、自分の研究について何も語れていない。東原って何をやっているどこの何者?というかたも多いと思うが、最近、生化学会誌2005年12月号に「多事争論」的な執筆をしたのでそちらを参考にしていただきたい。図書館にいくのがめんどうくさいという現代人は、「別刷り希望」と、ktouhara[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jpまで。また、ホームページを参照されたい。