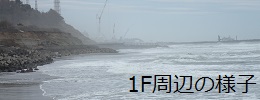災害時復興支援の救世主「ラボカー」を作りたい! - ご寄附のお願い -
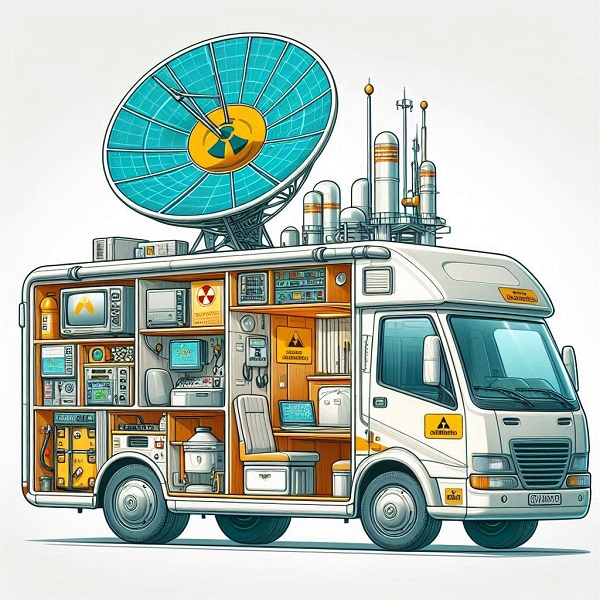
ラボカーとは、大学にある研究室の放射線測定の機能を全部まとめて車両に搭載したものです。専用のラボカーが構築されれば、電気や水道などのインフラが回復していない中でも機材や防護服や水など必要なだけ積んで効率よく測定・分析・発信することができるようになります。
2024年1月の能登地方の地震では、幸いなことに環境中から放射性物質は検出されませんでしたが、志賀原発周辺で一時的に測定できない地点が発生しました。今後、災害が発生した際に、ラボカーがあれば迅速に測定して安全が確認できます。
この装置も搭載予定!車載カメラで線量率を記録しています(2014年当時の帰還困難区域内)
ご寄付の方法1:クレジットカードによるご寄付
(その場での決裁をご希望の場合はこちら)

クレジットカードによるご寄付のご質問
ご寄付の方法2:寄附申込書によるご寄附
(振込用紙によるお振り込み)
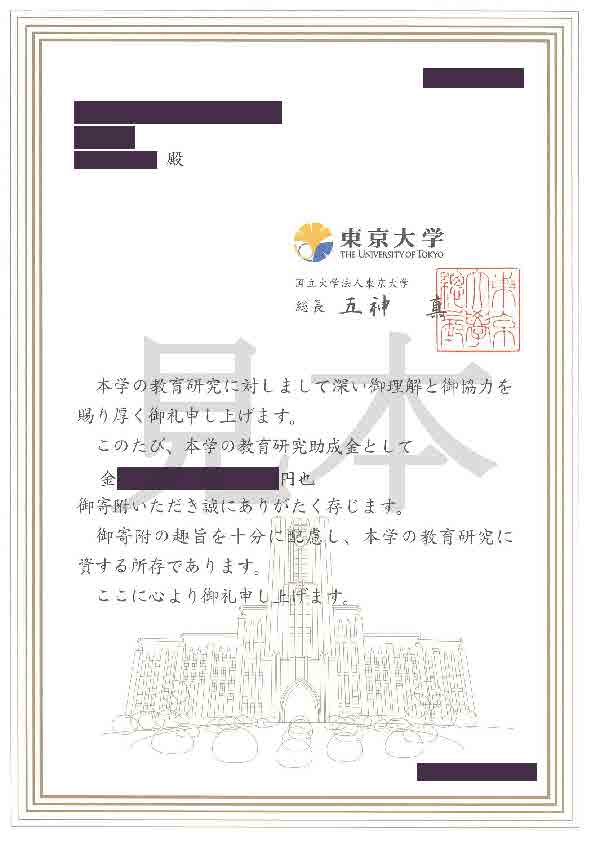
寄附申込書によるご寄附でよく頂くご質問
活動報告
帰還困難区域内やその周辺での取り組みを動画でお伝えしています
ご寄付いただいた方には月に1回研究の裏話や進捗をメールでお知らせしています.タイトルはこちら
米に放射性物質が移行しない工夫 2023年の実証実験(1分)
なおこの実験結果(特異的な137Cs吸着能を有する重粘土を用いた白米への放射性セシウム移行係数低減の試み)を日本環境化学会年会で発表する予定です(2024年7月広島).
モニタリングポストの数値って信用できるの?(4分)
福島第一原発周辺の様子(帰還困難区域内)(53分)
現場の様子を論文や学会で報告しています
論文と引用数の一覧はこちら(Google Scholar)
[1]研究機関や職位によって状況は大きく異なりますが、私の知る限りこれでも手厚い待遇です。
[2]Scientific reportsという雑誌の場合、掲載料金として2,490ドル(=約35万円)が必要です(2023年現在)。
[3]2018年末時点。なおこの論文は2018年のScientific reportsのEarth Science分野で閲覧数32位となり年間TOP 100に選ばれました。