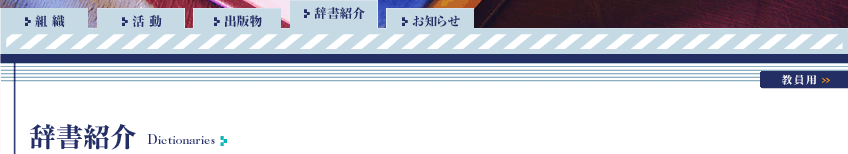英和辞典
大学入試の準備など高校レベルでもよく使用される学習英和中辞典は大学での英語学習でも大変重宝する。ただし、単に語義を調べるだけでなく読む辞典として活用すると良いだろう。辞典によっては、構文の使用頻度の違いや日本語と英語のコロケーションの違いなども説明されていて学ぶことが多い。例えば、大規模言語情報のコーパスに基づいた説明が充実した辞典も多い。試みに、手元にある『プログレッシブ英和中辞典』(第5版)のbodyの項を引いてみると、ボディーチェックに該当する英語としてsecurity checkやbody searchといった英語が紹介されており、自然な英語を学ぶ際にも中辞典が役立つことが分かる。入試が終わって学習英和中辞典は卒業という考え方もあるかもしれないが、英語学習には便利な辞典なので大切に使い続けてほしい。その上で、大学レベルともなれば、古い語句や専門用語に接することも多く、中辞典では太刀打ちできない場合もある。そのようなとき役立つのが英和大辞典だ。下記に挙げた1〜3の辞典は収録項目数の充実した大辞典の定番。4と5は専門用語も含めできる限り多くの言葉を収録した辞典で翻訳のプロもよく使う定評のある辞典だ。6は小ぶりな体裁ながら30万を超える収録項目数を誇り現代語もよく網羅されている。尚、理系は分野ごとに英和大辞典が発行されていることも多く、利用価値については専門の先生の助言を受けると良い。
- 新英和大辞典
(竹林ほか編・研究社・2002年第6版・並装19800円) - ランダムハウス英和大辞典
(小西ほか編・小学館・1993年第2版・14400円) - ジーニアス英和大辞典
(小西ほか編・大修館・2001年・16500円) - リーダーズ英和辞典
(高橋ほか編・研究社・2012年第3版・並装10000円) - リーダーズ・プラス
(松田ほか編・研究社・2000年・10000円) - グランドコンサイス英和辞典
(三省堂編纂所編・三省堂・2001年・8800円)
英英辞典
言葉の細かいニュアンスを英語で説明してくれる英英辞典は、英語を日本語に置き換える癖から抜け出すのに重宝する。ただし、いきなり外国語学習者向けではない英英辞典を使いこなすのは難しい。英英辞典を引き慣れていない場合は、まずは学習者向けに編集された7〜9のような英英辞典がお勧めだ。収録項目数はある程度限られるが、丁寧な説明と豊富な用例は英文を書く際に大きな助けとなる。10〜12は項目数の多い一般向けの英英辞典。特に12は北米圏の英語を念頭においた辞典で所謂アメリカ式の綴りに親しんでいる場合は利用しやすいかもしれない。13はOEDと略される文句なしの世界最大の英語辞典。特に古い文献を読む際に重宝する。同じ単語でも言葉の意味は時代によって変化することも多い。OEDでは用例とともに古い語義から新しい語義が網羅されているので、目的の単語が書かれた時代にどのような意味を有していたのか調べるのに大変便利だ。例えば、niceが昔は「愚かな」「みだらな」といった意味を有する単語であったことが実際の用例とともに掲載されていたりする。東大の学生なら大学図書館のウェブサイトでオンライン版を利用できるので、まだ見たことがない人は一度覗いてみるとよい。
- Oxford Advanced Learner's Dictionary
(OUP・2020年第10版) - Longman Dictionary of Contemporary English
(Pearson・2014年第6版) - Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary
(Collins・2023年第10版) - Concise Oxford English Dictionary
(OUP・2011年第12版) - Chambers Dictionary
(Chambers・2014年第13版) - American Heritage Dictionary of the English Language
(Houghton Mifflin・2011年第5版) - Oxford English Dictionary
(OUP・1989年第2版/オンライン版利用可)
和英辞典
和英辞典は英語を書く際に便利ではあるが、使い方にはやや注意が必要だ。和英辞典こそしっかり読むことが大切な辞典といえる。周知の通り、日本語で「牛」とひとことで言っても英語の場合、雌牛(cow)、去勢してない雄牛(bull)、去勢した雄牛(ox)集合的な牛(cattle)、子牛(calf)などによって言い方が異なるように、自分の意図する言葉が的確な英語であるか和英辞典をしっかり読んで最適の表現を選ぶことが何より重要だ。その意味で、14は項目数が多いうえに用例が充実しておりお勧めの辞典だ。電子辞書では1とセットで収録されていることも多い。15は語法解説の充実した中辞典サイズの学習者向け和英辞典で類語のニュアンスの微妙な違いも丁寧に解説されており、読む和英辞典としても充実している。
- 新和英大辞典
- ウィズダム和英辞典
(岸野編・三省堂・2019年第3版・3500円)
コロケーション辞典・類語辞典・その他
英語を書くための辞典として特にお勧めなのがコロケーション辞典と類語辞典だ。コロケーション辞典は英語における異なる品詞間の自然な結びつきの例を豊富に示してくれて極めて便利。特に16は初版の刊行からかなりの年数が経過したとはいえ38万の用例を誇る頼れる辞典だ。17も定評のあるコロケーション辞典で、日本の学習者向けに内容を編集した日本語版も出ている。また、英語は繰り返し同じ言葉を用いることを避ける傾向のある言語だ。結果、多くの類語辞典(シソーラス)が出版されている。中でも18、19は英語圏の書店でも必ずと言ってよいほど置いてある定評のある辞典。20はOxford Learner's Thesaurusを日本の学習者向けに編集し直した学習用類語辞典で、解説も充実している。また、英文法や語法の解説書の類はそれこそゴマンとあるが、ここでは定評のある文法・語法の解説書として21と22を挙げておく。英語の文法用語をいきなり理解するのが難しい場合は、定評ある語法辞典の日本語版の22がお勧めだ。
- 新編 英和活用大辞典
(市川ほか編・研究社・1995年・16000円) - Oxford Collocations Dictionary for Students of English
(OUP・2009年第2版)/日本語版:小学館 オックスフォード 英語コロケーション辞典(八木監修・小学館・2015年・4800円) - Oxford Thesaurus of English
(OUP・2009年第3版) - Roget's International Thesaurus
(Kipfer編・HarperCollins・2019年第8版) - 小学館 オックスフォード英語類語辞典
(田中監修・小学館・2011年・4500円) - A Communicative Grammar of English
(Leech・Svartvik著・Routledge・2003年第3版) - Practical English Usage
(Swan著・OUP・2017年第4版)/日本語版:オックスフォード実例現代英語用法辞典(吉田訳・研究社・2018年第4版・6000円)
電子媒体
昨今、教室や図書館で紙の辞書を使っている学生を目にすることはあまりない。自宅外では電子辞書やタブレット端末やスマホ、自宅ではダウンロード版やオンライン版の辞典をPCで利用する学生も多い。ここで紹介した辞書の多くは電子媒体での利用も可能なだけでなく、複数の辞典の同時検索や成句・例文検索など電子媒体ならではの機能もあり便利なことも多い。大事なことは、紙版であれ電子版であれ、語義の「チラ見」だけで満足するのではなく、語義や用法の解説、例文にしっかり目を通すことである。そして、ときには目当ての単語の周囲にリストされている言葉も眺めてほしい。派生語や関連語など一つの単語がもつ言葉の世界の拡がりを感じるはずだ。ページを繰る手間もなく目的の単語に瞬時にたどり着いてしまう電子版は便利な一方、目的以外の言葉と「思わぬ出会い」をしにくい場合もある。その意味で電子版と紙版の違いは、ネット書店と実際の本屋さんの違いに似ている。両者の特徴を理解しつつ活用してほしい。
※この記事は教養学部報第653号に掲載されたものを一部修正の上、教養学部報委員会の許可を得て転載したものです